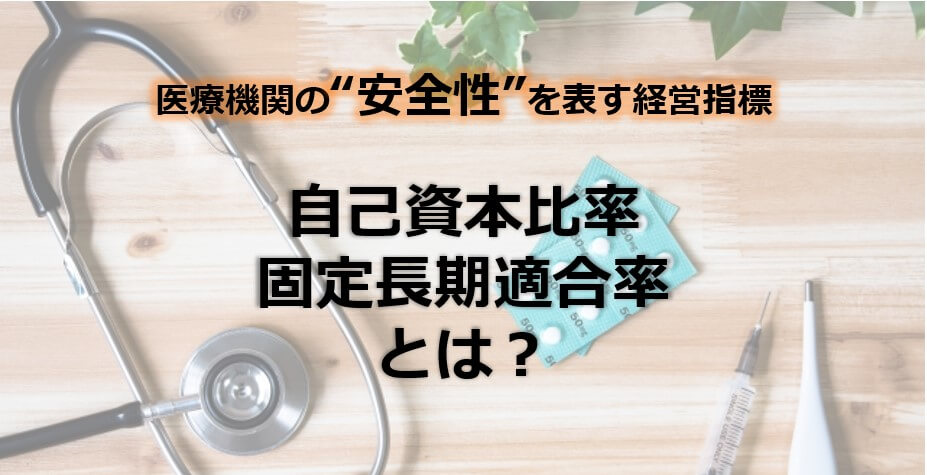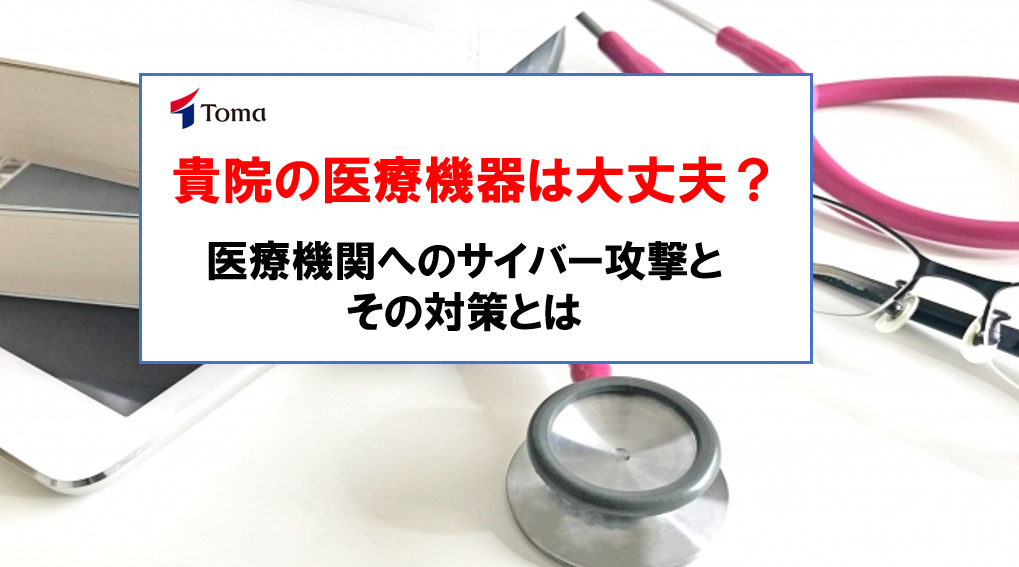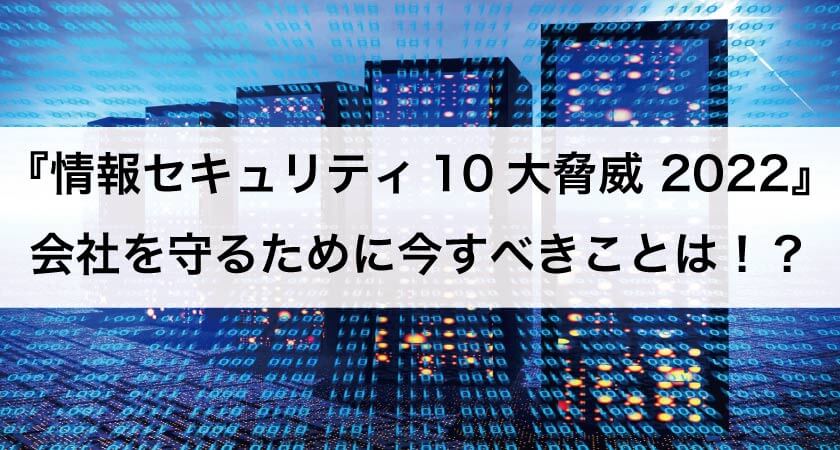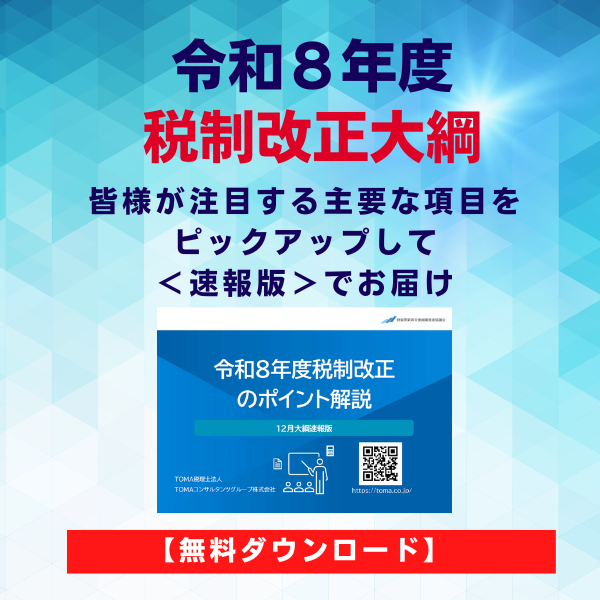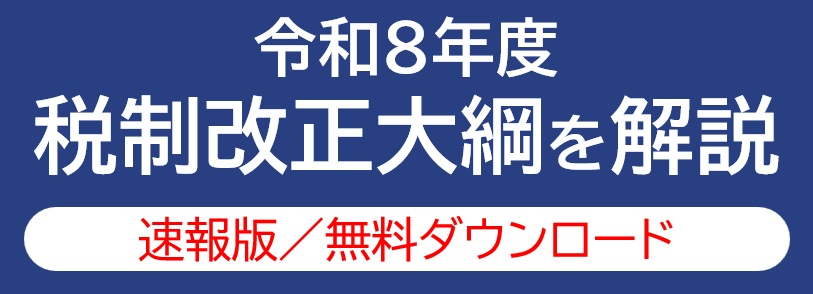病院・医院の経営の安全性を表す指標のうち、固定資産への投資を安全な資金で賄っているか判断する長期的な安全性の分析指標として、「自己資本比率」と「固定長期適合率」があります。今回はこの2つの指標についてご説明いたします。
自己資本比率
自己資本比率とは、総資産の中での自己資本(純資産の合計)の比率を示します。算式は下記となります。自己資本比率により、どれだけ借入金に頼らずに経営できているかがわかります。
自己資本比率=純資産÷総資本×100
病院・医院の建物、敷地を借入により取得しているか、また法人設立時、開業時に高額な設備投資をしているかによって、この比率は大きく異なります。借入により設備投資等をすると、借入金の割合が増え自己資本比率は低下します。
固定比率、固定長期適合率
両指標とも固定資産における、安定した調達資金の割合を示すものです。算式は次のようになります。
固定比率=固定資産÷純資産×100
固定長期適合率=固定資産÷(純資産+固定負債)×100
固定比率は100%以内であれば問題ありませんが、100%を超えると借入金も使って、固定資産を購入していることを意味します。しかし、病院・医院は多額の設備投資を要する事業であり、自己資金のみで固定資産を賄うのが難しいため、長期借入金など固定負債も含めた指標である固定長期適合率を用いて分析します。
〈医療福祉業と全産業における各指標の平均値〉

(財務総合政策研究所ウェブサイトより)
固定長期適合率が100%を超えてしまうと、固定資産を流動負債で賄っていることになります。その場合は、過剰な設備投資はないか、自己資本、長期借入金が不足していないか、または短期借入金が過剰ではないかなど、検討が必要となります。
以上、安定性の指標を紹介しましたが、これらもひとつの目安にすぎません。他の病院・医院の数値や平均値と比較して、差の原因を把握することがもっとも大切です。