事業承継でしばしば問題となるのが、後継者以外の相続人からの反発です。特に、遺産のうち一定割合の取得を保証する「遺留分」は、自社株式など遺産の大部分を占める事業用資産をを後継者へ引き継がせたい経営者にとって悩みの種になりがちです。ほかの相続人からの反発を避け、スムーズに事業を継がせるためにも、遺留分について知り対策を講じておきましょう。
この記事では、遺留分の概要と遺留分に関するトラブルを防ぐための方法について解説します。事業承継を検討している方はぜひ参考にしてください。
関連記事
・事業承継とは?3つの方法とメリット・デメリット、注意点、成功のコツなどをまとめて紹介
目次
遺留分とは?
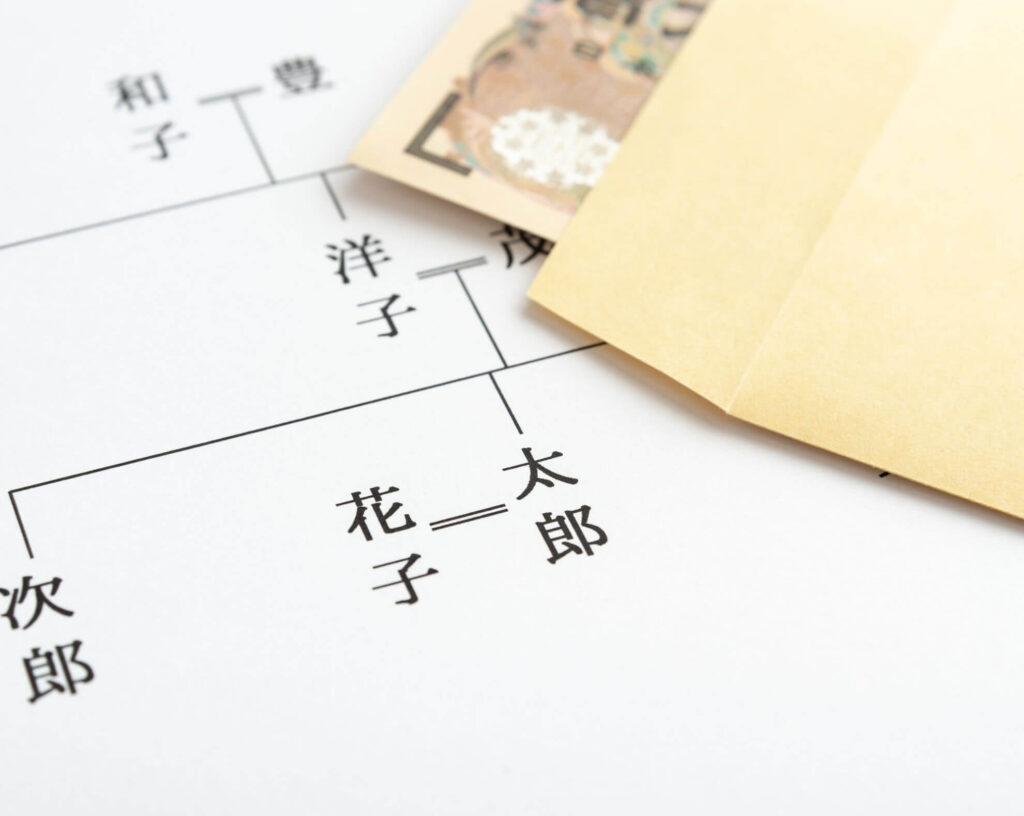
まずは、遺留分の概要を、具体例を含めて解説します。
遺留分の概要
遺留分(民法第1042条)とは、民法で定められている相続人(兄弟姉妹を除く。以下同じ)が最低限確保できる相続分のことをいいます。 例えば、配偶者・長男・次男がいる社長が「自分が亡くなったときには自分の財産をすべて長男にあげる」という遺言書を作成した場合、配偶者と次男の最低限度の相続人間の平等が確保できません。相続人間の平等を確保するため、民法では最低限相続できる権利を遺留分として保障しているのです。
遺留分を害された相続人は、遺留分侵害額の請求(民法第1046条)を行なうことによって遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができます。ただし、遺留分侵害額の請求権には期限があります。「遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき」または「相続開始の時から10年を経過したとき」、請求権は時効によって消滅します。(民法第1048条)
遺留分の具体例
遺留分をどのように算出するのか、遺留分算出の具体例をみていきましょう。被相続人の全財産が9,000万円の場合、各相続人が遺留分侵害額の請求を行なえる額は下記のとおりです。
前提:被相続人の全財産9,000万円の場合
遺留分侵害額
配偶者のみ:4,500万円(1/2)
子供のみ:4,500万円(1/2)
父母のみ:3,000万円(1/3)
配偶者と子供:配偶者 2,250万円(1/4)、子供 2,250万円(1/4)
配偶者と父母:配偶者 3,000万円(1/3)、父母 750万円(1/12)
配偶者と兄弟:配偶者 4,500万円(1/2)、兄弟 遺留分なし
事業承継の際には、遺留分のトラブルに要注意
事業承継の際は、遺留分によるトラブルに十分注意しなければなりません。後継者以外の相続人からの遺留分侵害額の請求により、事業承継が危うくなる可能性があるためです。
例えば、経営者である父が長男を後継者とし、経営権とともに自社株などの資産を長男に集中させて会社を承継させるつもりでいたとします。経営者の意向どおり、後継者へ全資産が承継できるのであれば特に問題はありませんが、実際には長男以外の相続人(長女、次男など)の「遺留分」を考慮しなければなりません。
この例の場合、長男以外の相続人は、遺留分侵害額に相当する金額を長男に請求する権利があります。遺留分侵害額に相当する金額を求められた長男は、その分の金銭がない場合は自社株や事業用資産を処分せざるを得なくなるのです。
相続人からの請求により、予定していた資産の承継ができなくなれば、円滑な事業承継・会社運営が危うくなります。遺留分に関するトラブルは実際に発生しているため、遺留分でトラブルを起こさないためにはどうすべきか、早めに検討しておく必要があります。
遺留分トラブルの対策として、経営者ができること
遺留分トラブルのおもな対策としては、遺留分の事前放棄や、経営承継円滑化法の民法特例の活用が考えられます。あらかじめこういった対策を施すことで、他の相続人による紛争や自社株式・事業用資産の分散を防止することが可能です。
遺留分トラブルの対策(1)遺留分の事前放棄
相続人は、被相続人の生前に自分の遺留分を放棄できます。しかし、遺留分を放棄するには、放棄しようとする他の相続人が自分で家庭裁判所に申立て、許可を受けなければならないため、他の相続人にとっては手間がかかります。
遺留分トラブルの対策(2)遺留分に関する民法特例の活用
遺留分に関する民法特例(経営承継円滑化法の民法特例)を活用することで、経営者から後継者に生前贈与された自社株式について、遺留分算定基礎財産から除外できます(除外合意)。また、経営者から後継者に生前贈与された自社株式について、遺留分算定基礎財産に算入する際の価額を固定することもできます(固定合意)。
この特例は、いずれも後継者を含む現経営者の推定相続人全員の合意を前提とするもので、経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可が必要となっています。後継者が単独で手続きを行うことができるため、現行の遺留分の事前放棄に比べて、他の相続人の負担が大きく軽減されます。
遺留分に関する民法特例の詳細と具体例
前項で触れた遺留分に関する民法特例は、適用にあたって満たすべき要件があります。遺留分に関する民法特例について、適用要件や除外合意と固定合意の違い、具体例などをみていきましょう。
遺留分に関する民法特例を適用するための要件
遺留分に関する民法特例を適用するには、以下の要件をすべて満たしていなければなりません。特例を利用する際には、まず要件を満たしているか確認しておきましょう。
会社
・中小企業者であること。
・合意時点において3年以上継続して事業を行なっている非上場企業であること。
先代経営者
・過去または合意時点において会社の代表者であること。
後継者
・合意時点において会社の代表者であること。
・現経営者からの贈与等により株式を取得したことにより、会社の議決権の過半数を保有していること。
引用:遺留分に関する民法特例のポイント(会社向け)|経済産業省 中小企業庁
除外合意とは?
遺留分に関する民法特例を活用すると、経営者から後継者に贈与等をされた自社株式について、「除外合意」または「固定合意」、もしくはその両方を適用できます。
除外合意を適用すると、後継者と他の相続人の間で、後継者が経営者から生前贈与等によって取得した自社株式を遺留分算定の基礎財産から除外できます。
これにより、他の相続人は遺留分を請求できなくなるため、相続紛争のリスクを回避し、後継者に集中的に株式を承継できるのです。
固定合意とは?
一方、固定合意では、後継者と他の相続人の間で後継者が経営者から生前贈与等によって取得した自社株式について、遺留分算定の基礎財産に算入する価額を合意時点の価額に固定することができます。固定合意を適用すれば、自社株式の価額が上昇しても遺留分への影響がなくなるため、相続時に想定外の遺留分の主張を受けることもなくなります。
ただし、固定する合意時の時価については、合意時に相当な価額であることを税理士、公認会計士、弁護士などの専門家に証明してもらう必要がある点に注意が必要です。
遺留分に関する民法特例の具体例
続いて、遺留分に関する民法特例の具体例について以下の前提をもとに、3つのケースに分けてみていきます。
・ケース(1)生前贈与なし・遺留分対策なしの場合
Aが死亡した場合、下記の計算式により、2,000万円分がCの遺留分の対象になります。
遺留分算定の基礎財産:2,000万円+6,000万円=8,000万円
遺留分計算式:8,000万円×遺留分1/4=2,000万円
・ケース(2)生前贈与あり・除外合意を適用した場合
生前にT社株式4,000万円をAからBへ贈与し、除外合意を適用します。Aが死亡した場合、下記の計算式により、500万円分がCの遺留分の対象になります。
遺留分算定の基礎財産:2,000万円
遺留分計算式:2,000万円×遺留分1/4=500万円
・ケース(3)生前贈与あり・固定合意を適用した場合
生前にT社株式4,000万円をAからBへ贈与し、固定合意を適用します。 Aが死亡した場合、下記の計算式により、1,500万円分がCの遺留分の対象になります。
遺留分算定の基礎財産:2,000万円+4,000万円=6,000万円
遺留分計算式:6,000万円×遺留分1/4=1,500万円
遺留分に関する民法特例を適用する手順【3ステップ】
遺留分に関する民法特例を適用する手順を、以下の3ステップに分けて解説します。
【ステップ1】合意書を作成する
遺留分に関する民法特例を適用するには、遺留分を有する推定相続人全員と後継者の合意が必要です。該当する人の合意をとり、合意書を作成しましょう。
【ステップ2】「遺留分に関する民法の特例に係る確認申請書」を提出する
合意した日から1ヵ月以内に必要書類を添付のうえ、「遺留分に関する民法の特例に係る確認申請書」を提出します。申請書の提出先は、経済産業省中小企業庁事業環境部財務課です。なお、確認書類に添付すべき書類は、会社経営者の場合と個人事業主の場合で異なります。
【ステップ3】家庭裁判所の許可を受ける
経済産業大臣の「確認書」の交付を受けたら、後継者は1ヵ月以内に先代経営者の住所地を管轄する家庭裁判所に「申立書」と添付必要書類を提出し、許可を得ましょう。家庭裁判所の許可を受ければ合意の効力が発生します。
参考:事業承継を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例|経済産業省 中小企業庁
スムーズな事業承継のためにも、遺留分を考慮した遺言の作成がおすすめ
遺言は、経営者の相続が発生したときに、経営者が所有している自社株式や事業用資産を後継者に取得させる有効な方法の一つです。スムーズな事業承継のためにも、経営者は遺留分を考慮した遺言を作成し、遺留分侵害額請求を回避する手立てを講じておくとよいでしょう。
遺言の方式には、普通の方式と特別な方式があり、普通の方式による遺言は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類あります。その他に特別な方式として、死亡の危急に迫った者の遺言の作成が認められています。ここでは、一般的な遺言である「自筆証書遺言」「公正証書遺言」について、それぞれの特徴を解説します。
自筆証書遺言の特徴
初めに、自筆証書遺言の作成方法とメリット、デメリットを解説します。
・自筆証書遺言の作成方法
自筆証書遺言は、遺言者が日付および氏名、財産をどのように分割するのかを手書きし、押印して作成します。なお、ワープロ等で作成した遺言は無効です。
・自筆証書遺言のメリット
自筆証書遺言は、紙と筆記具さえあればいつでも費用をかけずに作成できる点がメリットです。
・自筆証書遺言のデメリット
自筆証書遺言は専門家の目を通さないため、形式不備等により無効となるおそれがあります。また、作成した遺言書は法務局に預けることもできますが、自身で保管する場合は、遺言の紛失、隠匿、偽造などが起きないよう注意が必要です。
また、遺言者の死後、家庭裁判所へ遺言書を提出し、検認を請求しなければなりません。検認は、相続人に遺言の存在と内容を知らせ、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。遺言書検認の手続きが必要な点も、自筆証書遺言のデメリットの一つといえるでしょう。
公正証書遺言の特徴
続いて、公正証書遺言の作成方法とメリット、デメリットを解説します。
・公正証書遺言の作成方法
公正証書遺言は、公証役場に赴き、公証人と遺言者に加え証人2人以上の立会いのもと、遺言者が公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成します。公証役場は、日本公証人連合会のホームページに記載の全国公証役場所在地一覧から確認できます。
※公正証書遺言作成には証人2人の立会いが義務付けられていますが、適当な証人が見当たらない場合には、公証役場で紹介してもらえます。
参考: 公証役場一覧|日本公証人連合会
・公正証書遺言のメリット
公正証書遺言は公証人が関与するため、形式不備等により無効になるおそれがありません。また、原本は、公証役場にて保管されるため、紛失、隠匿、偽造のおそれがなく、家庭裁判所による検認手続きも不要です。
・公正証書遺言のデメリット
公正証書作成には証人2人以上とともに公証役場に行く必要があり、手数料もかかるため、証書作成までに手間がかかります。また、公正証書遺言の作成費用は財産が多くなるほど高くなるよう設定されています。
自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリットを比較すると、多少の費用と手間はかかりますが、法的に無効になるおそれが少ない公正証書遺言を選択した方が、遺言書として確実性があるといえます。
まとめ
遺留分は、事業承継における課題のひとつです。スムーズな事業承継を実現するためには、後継者以外の相続人に対してどのように対処するのかをあらかじめ決めておく必要があります。遺留分の概要を知り、後継者へ財産を生前贈与するなどして対策しましょう。
事業承継の専門家が所属するTOMAコンサルタンツグループでは、事業承継に関するサービスを提供しています。事業承継の核となるヒト・モノ・コトの3つの視点から、総合的に事業承継をサポートいたしますので、事業承継でお悩みの方はぜひご相談ください。TOMAの事業承継サービスはこちらよりご覧いただけます。
事業承継サービスの初回のご相談は無料です。無料相談をご希望の方は、最下部の無料相談・お問合せよりお気軽にお申し込みください。
事業承継セミナーのお知らせ
TOMAでは事業承継に関して定期的にセミナーを開催しております。事業承継についてお考えの方から実際に対応を実施中の方まで、どなた様でもお気軽にご参加ください。詳細はこちらよりご覧ください。









