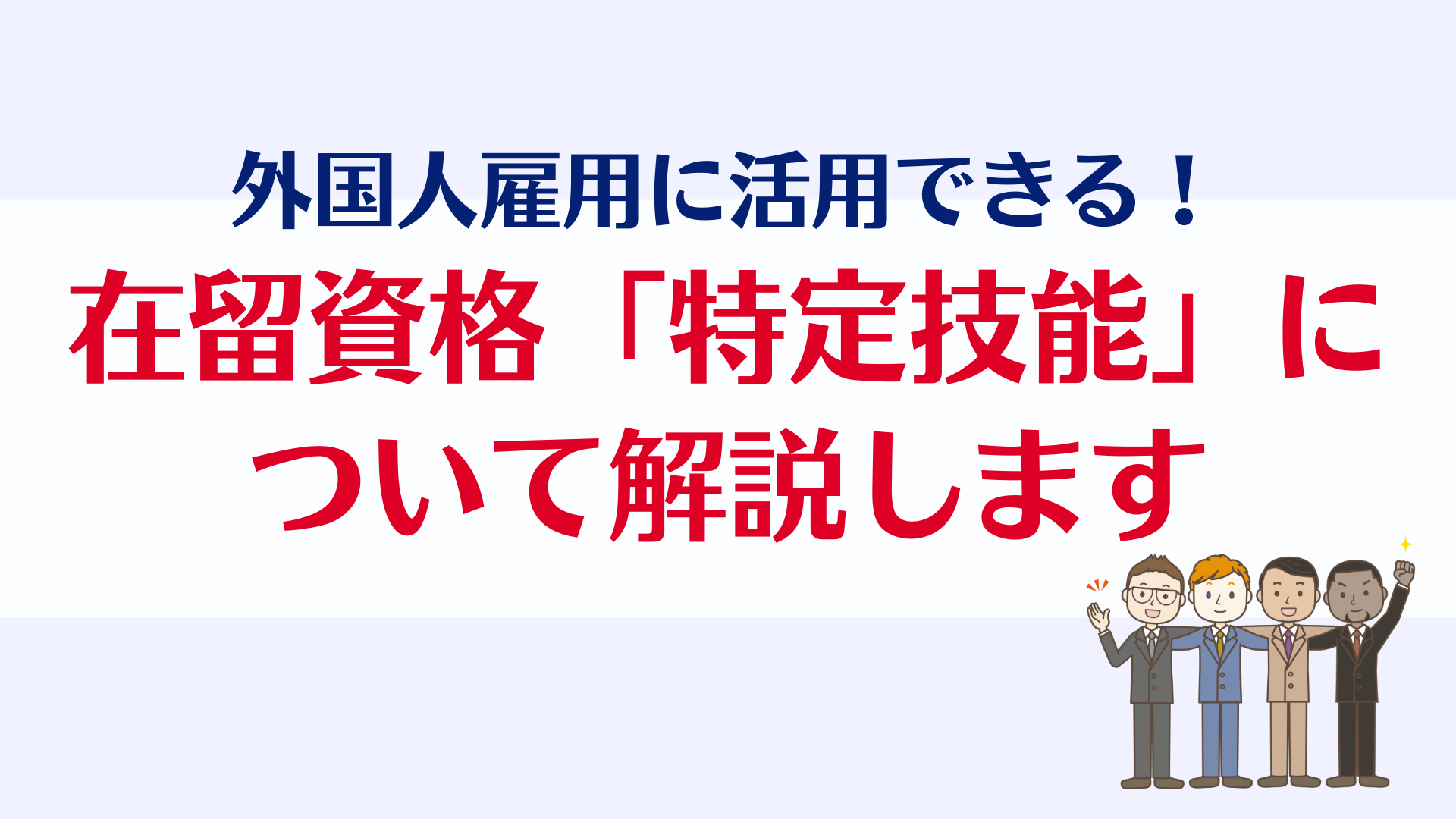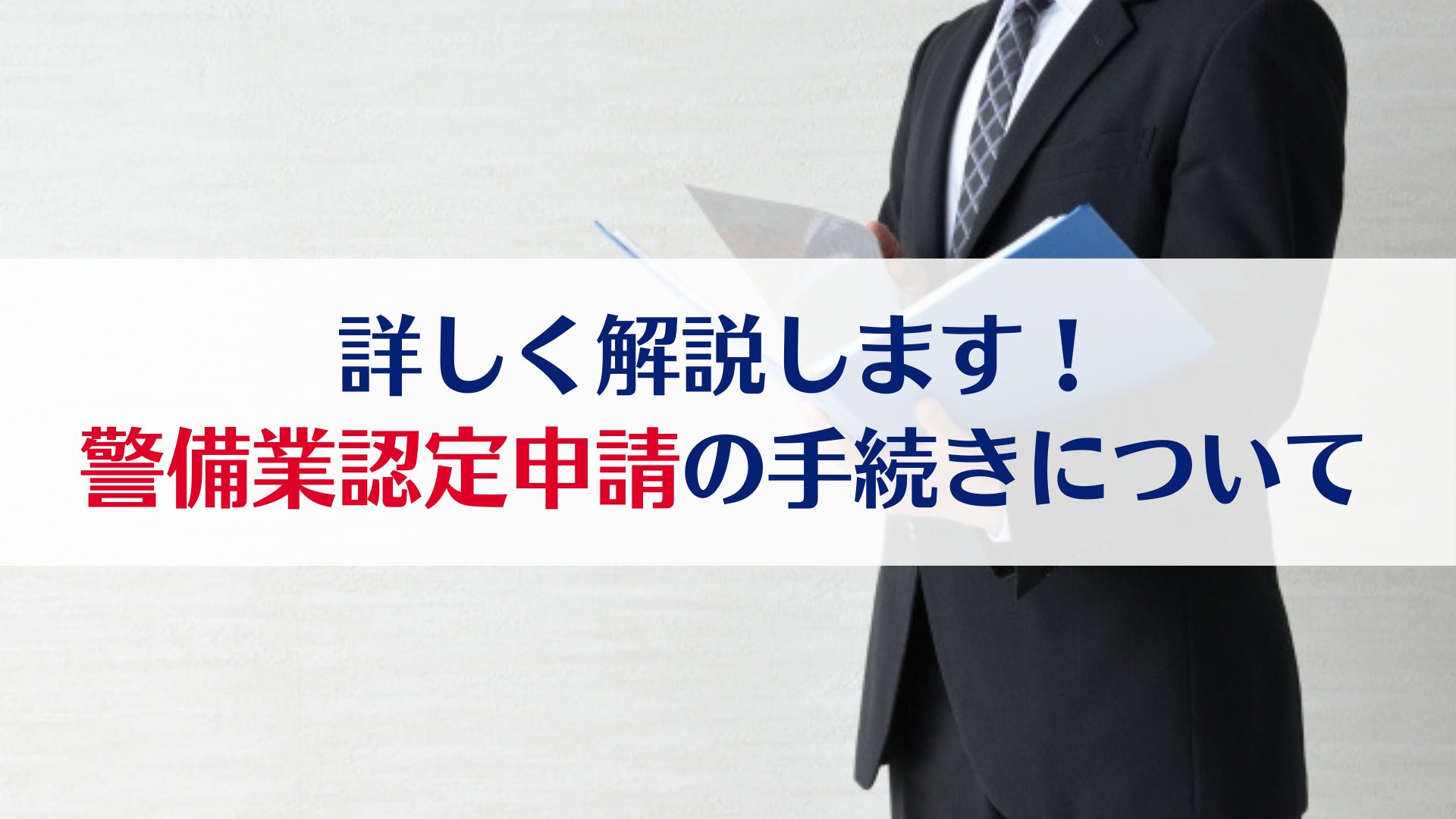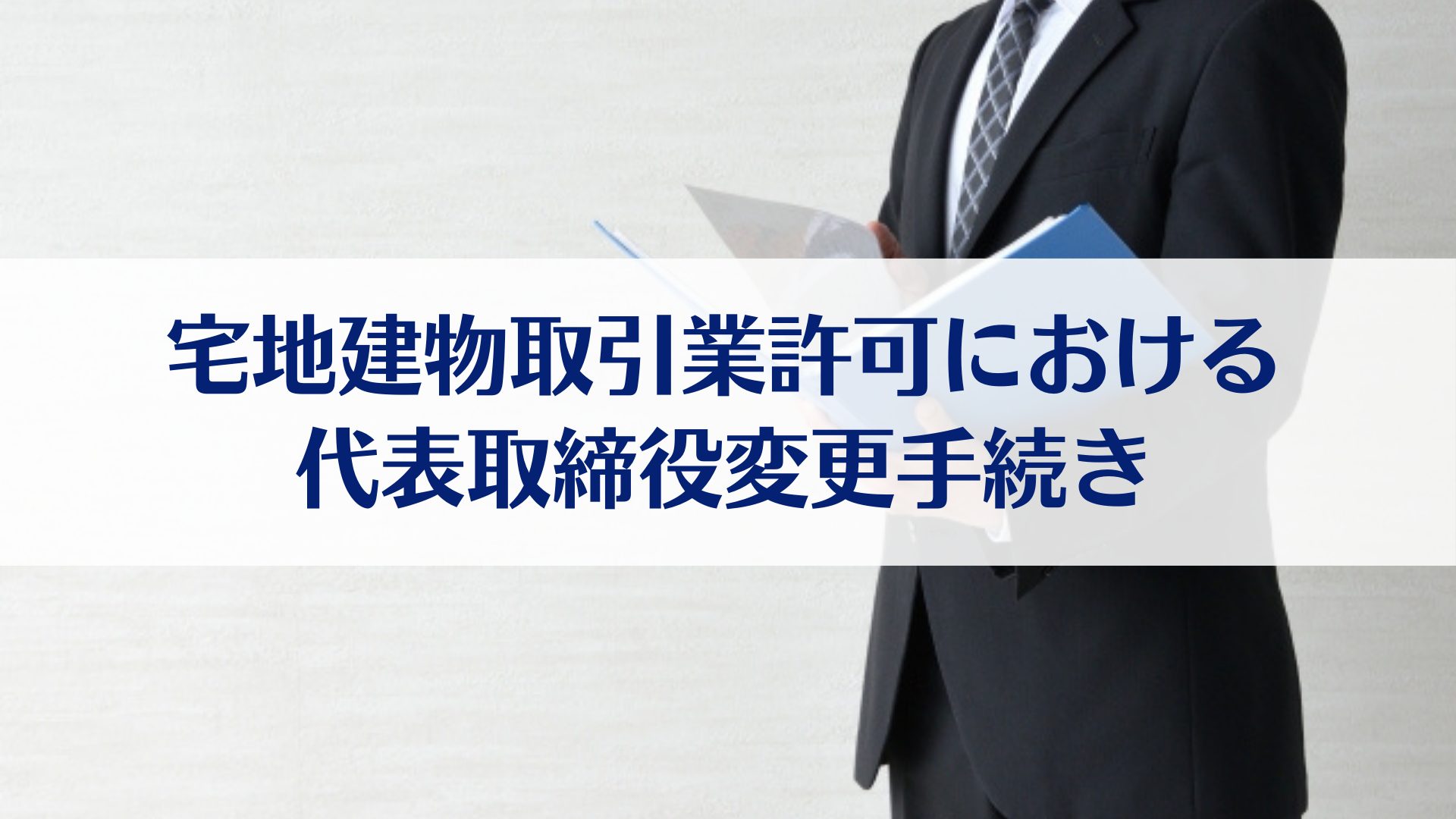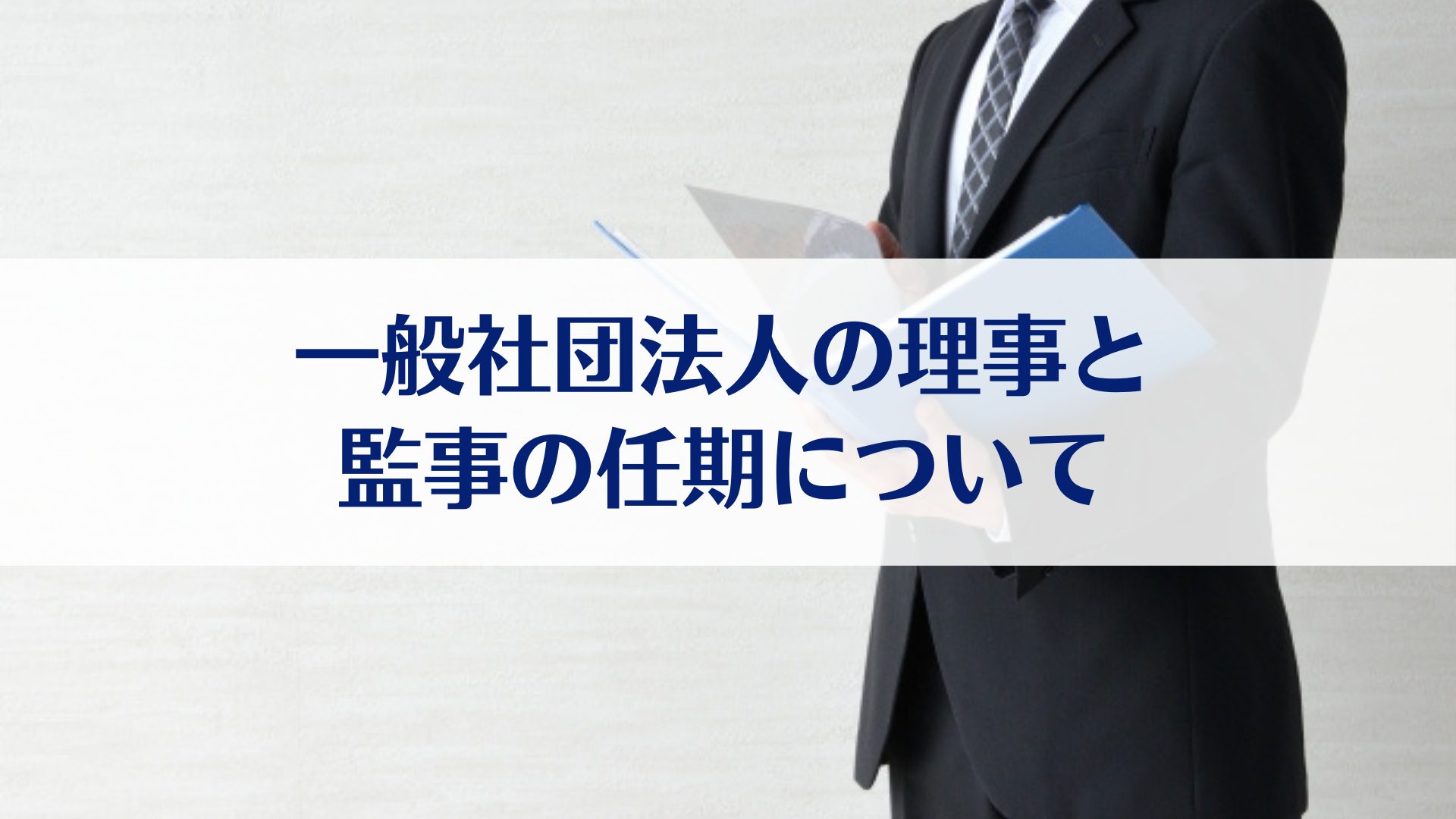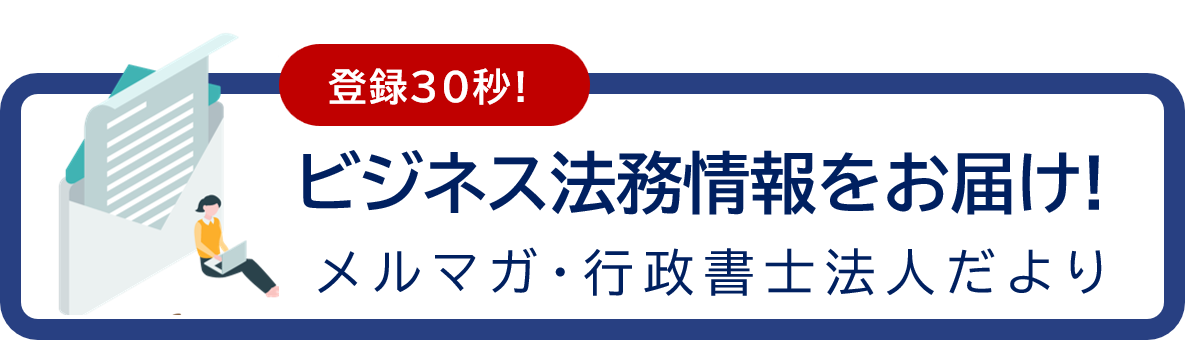人手不足という深刻な課題に対し外国人の雇用を検討されている中小企業の経営者の方も多いと思います。
そのような中、特に人手不足が深刻な産業分野で、一定の専門性や技能を有する外国人を積極的に受け入れる在留資格として2019年に「特定技能」という在留資格が新設されました。
特定技能は2025年4月現在、1号と2号に分類され、1号で16分野、2号で11分野が対象職種となっています。また、2025年4月より、届出の項目や申請のルールなどが変更されています。
今回のブログでは、在留資格「特定技能」について、2025年4月からの申請方法の変更やその特徴、メリット・デメリットについて詳しくご紹介します。
目次
在留資格「特定技能」とは
特定技能とは、人手不足が深刻な特定の産業分野で、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるために新設された在留資格です。特定技能には1号と2号の2種類があり、2号は1号よりも専門的な技能が必要となります。
「特定技能」の概要
1.対象業種
特定技能は、特に人手不足が深刻な業種に限定されています。具体的な業種は、次のとおりです。
(令和6年3月29日閣議決定により、1号は16分野、2号は11分野)。
介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業
※介護、自動車運送業、鉄道、林業及び木材産業は、特定技能1号のみで受け入れが可能。
2.技能レベル
特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つの区分があります。1号は比較的基本的な技能を持つ労働者向けで、2号はより高度な技能を持つ労働者向けです。
3.在留期間
特定技能1号の在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)です。一方、特定技能2号の在留期間は、3年、1年又は6か月で、更新により無期限滞在が可能です。
4.家族帯同
特定技能1号では原則として家族(配偶者・子)の帯同は認められていませんが、特定技能2号では家族の帯同が可能です。
5.試験制度
特定技能の資格を得るためには、業種ごとに各省庁で定められた技能試験と日本語能力試験に合格する必要があります。
6.受入れ機関のサポート
受入れ機関(外国人労働者を雇用する企業や団体)は、以下のとおり、外国人労働者が円滑に生活・就労できるようにサポートしなければなりません(特定技能1号のみ)。
・事前説明
・出入国する際の送迎
・住居確保・生活に必要な契約支援
・社会生活等の説明
・公的機関の手続等への同行
・日本語を学習する機会の提供
・相談・苦情への対応
・日本人との交流の促進
・転職支援
・定期的な面談の実施、行政機関への通報
7.登録支援機関の支援
受入れ機関に代わって、外国人労働者が円滑に就労できるように支援を行う機関で、日本での生活や労働に適応できるように様々な支援を提供します(特定技能1号のみ)。
「特定技能1号」と「特定技能2号」の違いについて
特定技能には1号と2号の2種類があり、2号は1号よりも専門的な技能が必要となります。その違いについて下記の通りまとめました。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 具体的業務 | ・建物内部の清掃作業 ・溶接作業 ・電気機器組立てなど |
・現場や工程の管理 ・業務の計画作成 ・作業者の指導・監督など |
| 対象者 | 一定の技能を有する外国人 | 熟練した技能を有する外国人 |
| 在留期間 | 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) ※在留できる期間は5年まで |
3年、1年、または6か月 ※在留期間の更新を受ければ上限なく滞在可能 |
| 家族(配偶者・子)の帯同 | 原則不可 | 可能 |
| 技能水準 | 試験等で確認 | 試験等で確認 |
| 日本語能力 | 試験等で確認 | 特に求められない |
| 業種 | 16業種 | 11業種 |
| 永住許可 | 対象外 | 永住許可の対象となる可能性あり |
| 受入れ機関または登録支援機関による支援 | 対象 | 対象外 |
外国人労働者の支援機関・登録支援機関について
特定技能の登録支援機関とは、日本において特定技能の在留資格を持つ外国人労働者が円滑に生活し、働くことができるように、企業や団体に代わって支援業務を行う機関のことです。特定技能制度では、受入れ機関(雇用主)に対して、特定技能外国人に対する支援を行う義務が課されていますが、これを専門の登録支援機関に委託することができます。
登録支援機関が提供する主な支援内容は以下のとおりです。
1.事前ガイダンスの提供
日本での生活や労働に関する基本的な情報を事前に提供します。
2.入国時の空港出迎え
外国人が日本に入国する際に空港での出迎えを行います。
3.住居の確保や契約に関する支援
住居の確保や契約手続きのサポートを行います。
4.生活オリエンテーションの実施
日本での生活に必要な情報を提供し、日常生活に関するオリエンテーションを実施します。
5.日本語学習の支援
日本語能力の向上を支援するための学習機会を提供します。
6.相談・苦情対応
労働や生活に関する相談や苦情に対応し、必要に応じて適切な助言を行います。
7.定期的な面談の実施
外国人労働者との定期的な面談を行い、状況を把握し、必要な支援を行います。
登録支援機関は、法務省に登録されており、一定の基準を満たす必要があります。これにより、外国人労働者が安心して日本で働き、生活できる環境を整えることが目的とされています。
特定技能外国人を雇用するメリットとデメリット
下記にメリット・デメリットの比較表を掲載しています。
主なメリットとしては、特定技能を持つ即戦力となる外国人人材が雇用できることで労働力不足の解消に繋がり、かつ、5年以上にわたる長期雇用が可能な点です(但し、2号に限る)。一方、デメリットとしては、手続きの煩雑さ、コスト増、(1号の場合は)在留期間の制限があることなどです。
| メリット | デメリット |
| ・特定技能は、特に人手不足が深刻な産業分野での労働力を確保するために設けられているため、同制度により即戦力となる人材を確保しやすくなります。 ・特定の技能を持つ外国人労働者を雇用することができるため、企業は即戦力となる人材を確保することで、業務の効率化や品質向上を図ることができます。 ・特定技能2号は、在留期間の更新を重ねることで、事実上の無期限滞在が可能ですので、長期の就労が期待できます。 | ・特定技能の在留資格を取得するためには、外国人労働者の技能試験や日本語能力試験の合格、申請書や必要書類を準備する必要があるため、企業にとっては手間と時間がかかります。 ・外国人労働者の受け入れには、在留資格の申請費用や渡航費用、住居の手配など、様々なコストが発生します。これらの費用は企業側が負担することが一般的です。 ・特定技能1号の在留期間は最長5年ですので、更新や特定技能2号への移行ができない場合、外国人労働者は帰国しなければなりません。これにより、長期的な人材確保が難しくなることがあります。 ・外国人を受け入れ、会社になじんでもらうために、言語、文化、風習、宗教等、日本人とは異なる配慮が必要になる場合が多々あります。 |
2025年4月からの運用の変更点について
出入国在留管理庁より、特定技能の「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が施行されることに伴い、特定技能の定期届出や随時届出、在留資格申請書類に関する制度の運用が変更になることが発表されました。
変更点に関する主なポイントを以下の通りまとめました。
①特定技能外国人受入れ手続
・提出書類が一部不要になる
・定期届出の提出頻度も従来の四半期ごとから一年に一度になる
・申請書に一部項目が追加され、市区町村への協力確認書の提出が必要となる 等
②参考様式の変更
・従前の様式が廃止され、新たな様式に変更される 等
③1号特定技能外国人支援に関する内容
・外国人支援計画の要件が追加
・定期面談について、一定のルール化でオンライン面談が可能になる 等
参考:出入国在留管理庁HP
詳しくはTOMAまでお問い合わせください。
TOMAは在留資格の申請から受入れ支援業務までワンストップでご支援します.
特定技能は、一見すると煩わしい印象を持たれるかもしれませんが、TOMAでは提携している登録支援機関がありますので、「在留資格の申請」から「受入れ支援業務」までワンストップでご提供することができます。詳しくは下記をご覧ください。
また、TOMAでは人材開発や組織開発のサービスも併せてご提供しております。外国人労働者を雇用することで生じる諸問題に対し、お客様の状況や課題・ニーズに合わせてご提案いたします。
その他、外国人労働者の税金・就業規則・給与設定のサポートなどについても、TOMAグループ内の税理士・社会保険労務士と連携してサービスをご提供できますので、安心してご相談いただけます。
少子高齢化に伴う人口減少に伴い、国内の労働力を確保することは今後ますます難しくなると予想されます。採用にお困りでしたら、外国人労働者の雇用を検討してみてはいかがでしょうか。
出典:出入国在留管理庁HP
また、TOMAではこうした情報をお届けするメルマガを定期配信しています。ご興味ある方は下記よりご登録お願いします。