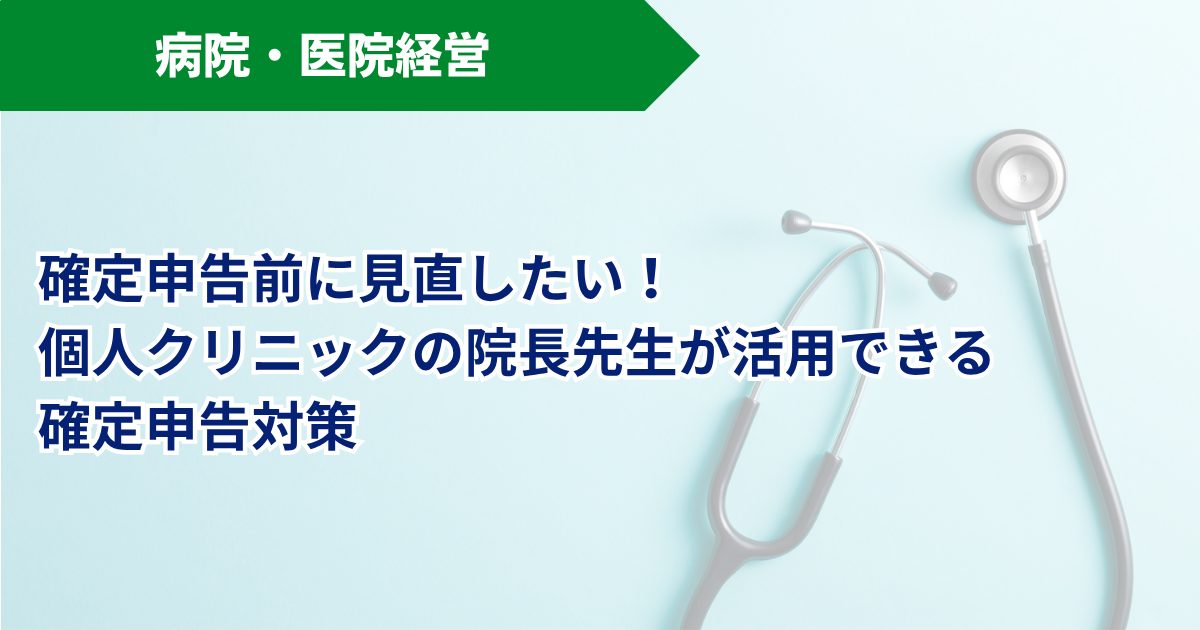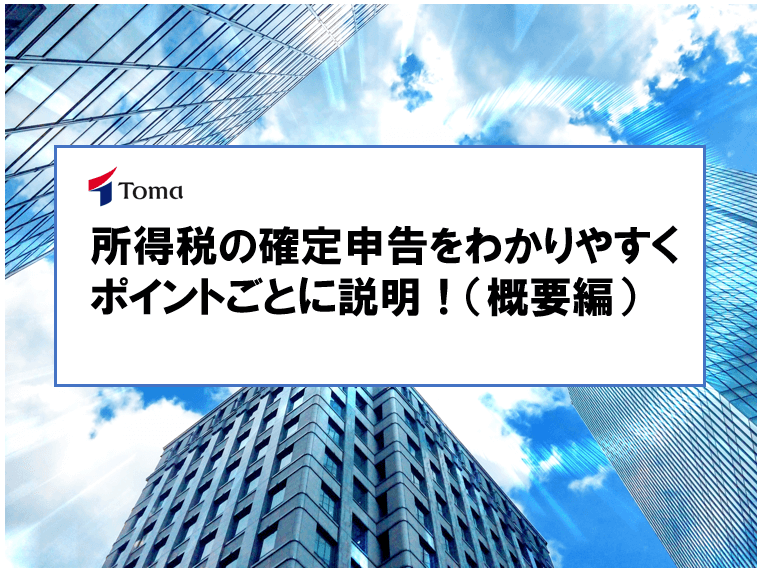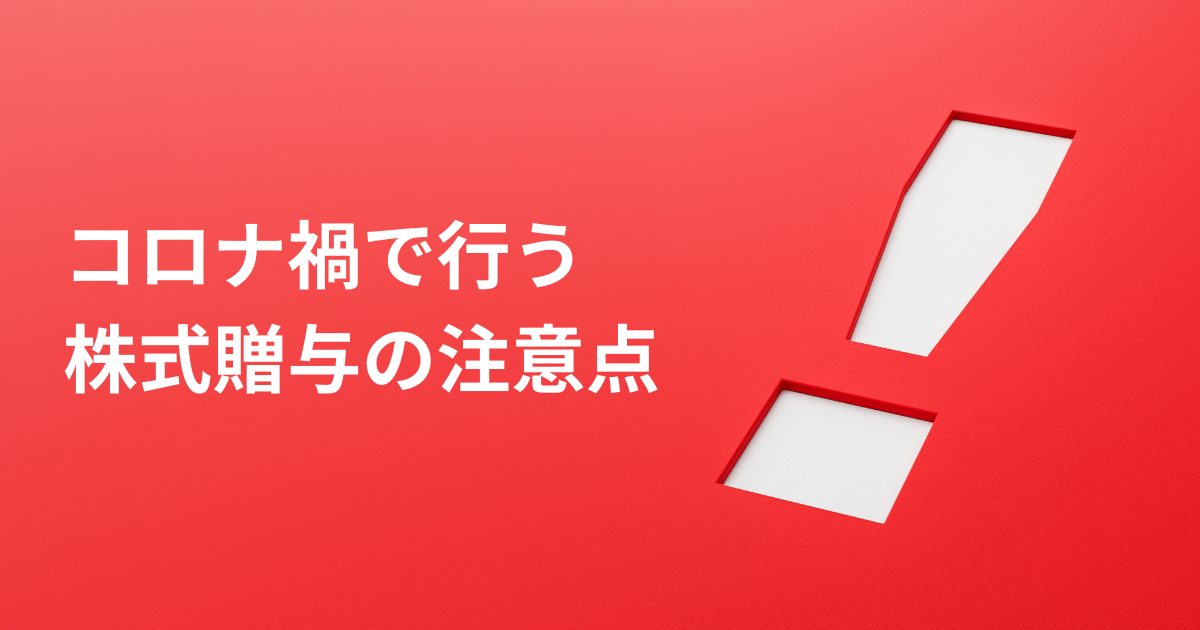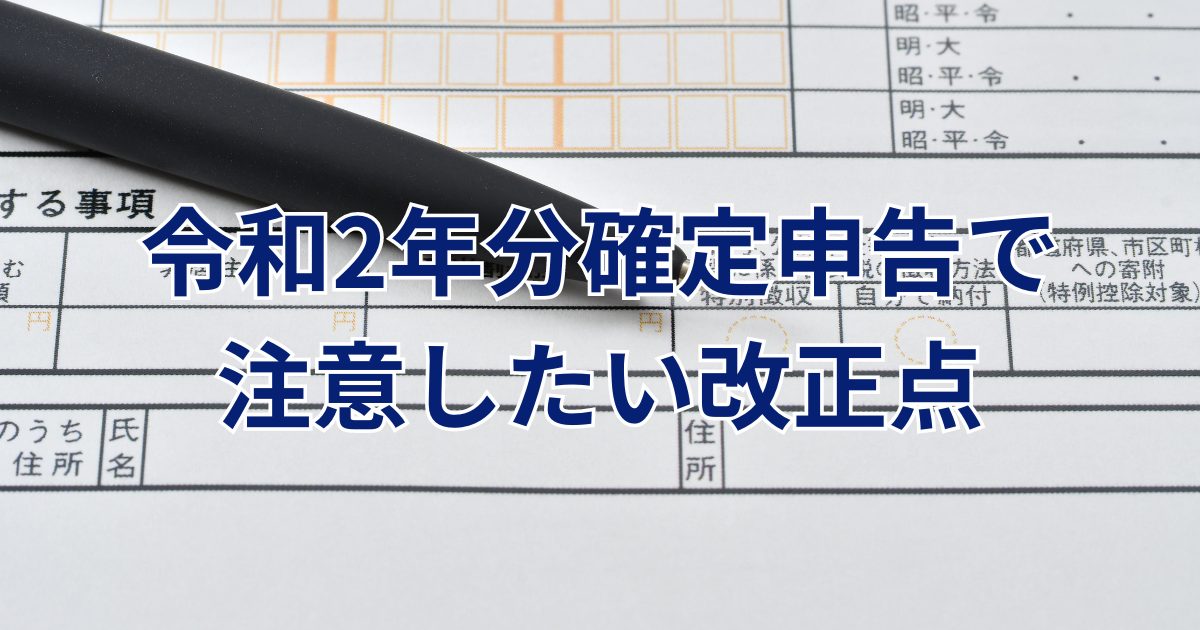確定申告の時期が近づいています。個人開業医の先生方に向けて、実務に役立つ確定申告対策を分かりやすくまとめました。年内にできる対策を確認し、安心して申告を迎えましょう。
クリニックで活用できる節税ポイント
1.賞与の支給
賞与の支給は経費として計上できます。特に業績が良い場合は、日頃頑張ってくれている従業員へ還元することができ、従業員のモチベーションアップにもつながります。
また、前年度より給与等の支給額が増加した場合には、賃上げ促進税制を適用することで、税額控除を受けられる可能性があります。ただし、親族に支払う給与や賞与は賃上げ促進税制の対象外となりますので、ご注意ください。
賃上げ促進税制については、以下のブログでも詳しく解説していますのでご覧ください。
なお、生計を一にする親族への給与や賞与は、原則として経費計上が認められませんが、一定の要件を満たすことで経費計上が認められます。
経費として計上するためには、青色申告の場合、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しておく必要があります。届出は、基本的には給与や賞与を支給する年の3月15日までに行う必要があります。
すでに届出を提出している場合でも、専従者への賞与の支給をされる際は、改めて支給金額等の届出内容をご確認ください。
2.ご自宅等を事業に使用している場合の按分経費の計上(家事関連費)
ご自宅の一部をクリニックの事務作業スペースや店舗として使用している場合、その事業利用分を経費に計上できます。
経費計上の際は、プライベート利用分と事業利用分を明確に区分し、床面積や使用時間等、合理的な基準で按分する必要があります。
例えば、自宅を店舗と併用している場合は、家賃、租税公課(固定資産税)、水道光熱費、通信費(インターネット使用料)等の事業利用分を確認しましょう。税務署から説明を求められた際に備え、按分計算の根拠や事業利用の証拠となる資料を必ず保管しておきましょう。
3.共済を活用しよう「倒産防止共済(経営セーフティ共済)」
倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、取引先企業が倒産した際に資金繰りを支援する共済制度です。
確定申告の際には、掛金全額を事業所得の経費に計上できます。また、共済契約を解約した場合は、一定の条件のもと解約手当金を受け取ることができます。
注意点として、解約手当金は事業所得として計上します。これにより、解約手当金を受け取った年は事業所得が増加し、税負担が増える場合があるため、解約のタイミングについては税理士等の専門家にご相談ください。
制度の詳細や加入要件については、独立行政法人中小企業基盤整備機構にご確認ください。
4.開業費の償却
開業費とは、事業を始めるまでにかかった準備のための費用です。クリニックの開業時に計上した開業費が、未償却のまま残っていないでしょうか。
未償却の開業費があれば、その範囲内で任意の金額を、任意のタイミングで経費に計上できます。
償却する金額は、税率や利益の状況を見て、税負担が抑えられるような所得を目安に償却しましょう。なお、赤字の年は無理に償却する必要はありません。開業費は繰延資産のため、将来利益が出る年まで残しておくことができます。
ここまではクリニックの確定申告対策を確認しました。ここからは、院長先生個人が活用できる対策を確認しましょう。
個人として使える控除を年内に確認しよう
院長先生個人が利用できる控除をピックアップしましたので、ご確認ください。
1.ふるさと納税
ふるさと納税は、都道府県や市区町村への寄附を行うことで、所得税・住民税の控除を受けられる制度です。自己負担額2,000円を除いた金額が、一定の上限まで控除対象となります。控除額は、所得税・住民税それぞれの計算式に則って計算され、下記のように控除されます。
・所得税:ふるさと納税を行った年から控除
・住民税:ふるさと納税を行った翌年度分から減額される形で控除
注意点として、所得や家族構成に応じて控除の上限額があるので、寄附額が上限を超えないよう注意しましょう。
ふるさと納税の上限額を正確に把握するには、ご自身の年間所得の見込み額を知ることが大切です。毎月の記帳をしっかり行い、年末までに所得の見込みを把握しておくことで、ふるさと納税の最適な寄附額を計算できます。
控除の上限額は、ふるさと納税のポータルサイト等でシミュレーションができます。より詳細なシミュレーションをしたい場合は、税理士等の専門家にご相談ください。
また、確定申告前に所得の見込みを確認しておくことで、他の節税対策も立てやすくなります。日々の記帳を習慣化することで、税額の予測がしやすくなり、安心して確定申告を迎えられるでしょう。ふるさと納税については以下のブログでも詳しく解説していますので、ご覧ください。
2.共済を活用しよう「小規模企業共済」
小規模企業共済は、個人事業主等が、事業の廃業や退職時に備えて積み立てる共済制度で、経営者の退職金制度のようなものです。
通常、個人事業を辞めても退職金は出ませんが、この共済制度を活用すれば、退職金代わりに共済金を受け取れます。将来に備えつつ、税制面でもメリットがある制度です。
確定申告の際には、掛金の全額が所得控除の対象となります
共済金は「一括」「分割」「一括と分割の併用」で受け取ることができるので、一括受取は退職所得、分割受取は公的年金等の雑所得となり、受取りの際にも税制面でメリットがあります。制度の詳細や加入要件については、独立行政法人中小企業基盤整備機構にご確認ください。
まとめ
確定申告は、クリニック経営者にとって重要な年中行事です。節税ポイントや各種控除制度をしっかり活用し、安心して申告を迎えましょう。ご不明な点があれば、税理士等の専門家にご相談ください。
TOMAには、ヘルスケア業に特化した税理士部門があり、心強い「共同経営者」として貴院の経営をきめ細やかにサポートします。ご不安なことがあれば、ぜひ以下の「無料相談・問合せ」よりお問い合わせください。