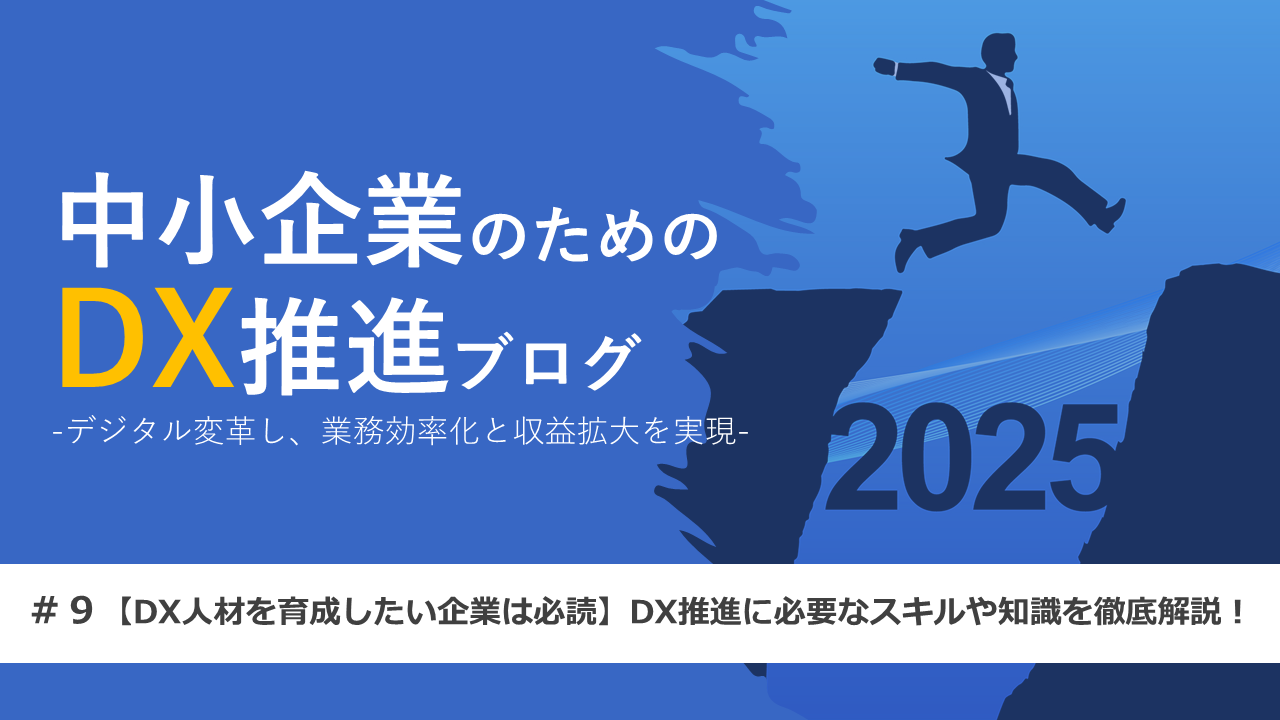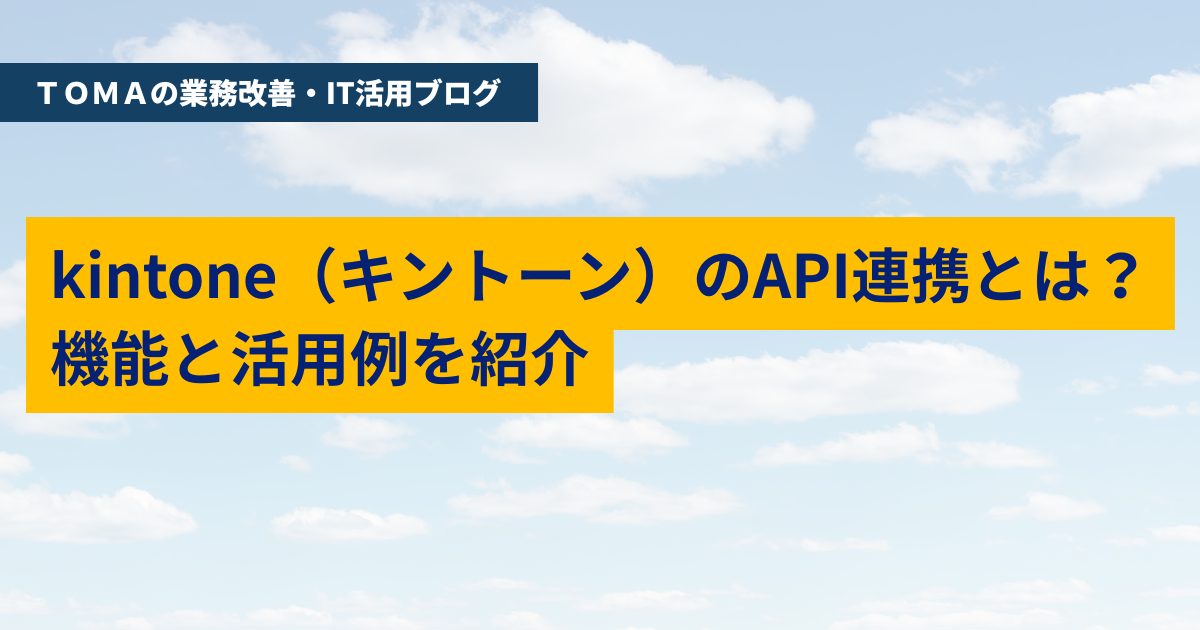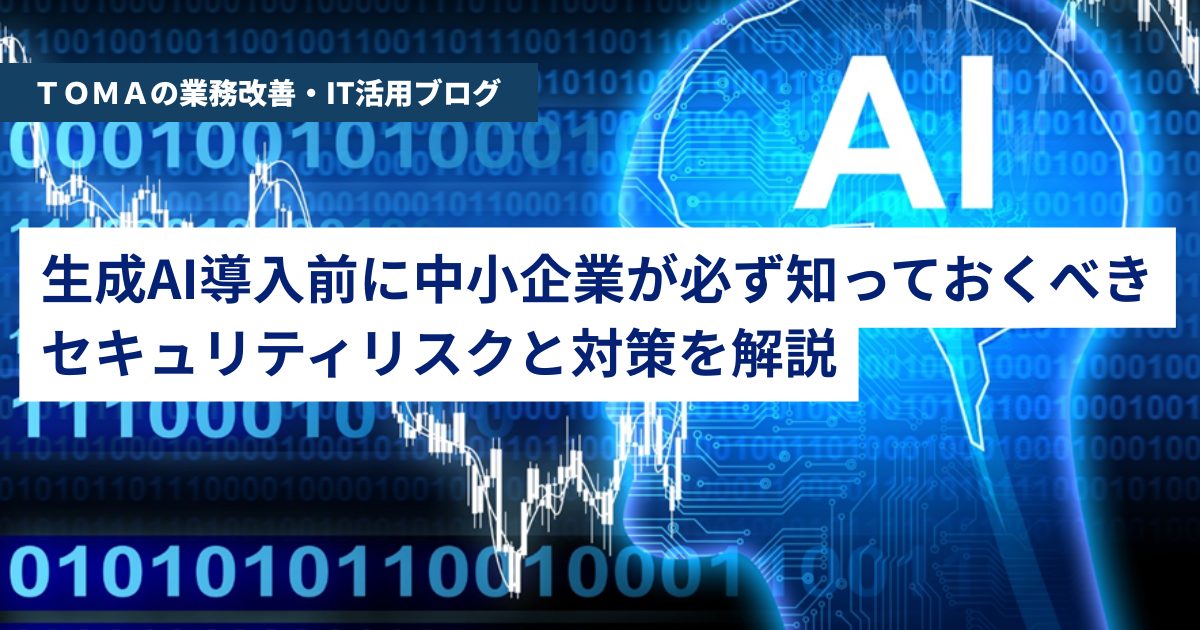お客様の業務効率化に向けて、業務改善プロジェクトを立ち上げます。業務責任者と現場の担当者、およびTOMAのコンサルタントでプロジェクトチームを組み、課題共有・対策ミーティングを実施します。
プロジェクトチームでの打ち合わせにて、現場では見えづらい業務課題をTOMAが第三者の立場から浮き彫りにし、貴社の業務内容・業務フローを客観的に診断して、改善策をご提案します。
流れとしては、はじめに業務内容をヒアリングさせていただき、業務改善後に自社で最適な運営が可能な管理体制の構築し、プロジェクトのなかで業務改善を図るとともに、改善後の「業務の標準化」を進め、業務の合理化・効率化をご支援します。
業務改善コンサルティングの目的
業務改善を行うことで未来の経営を安定化させ、売上向上につなげます
業務改善を行うことで得られる効果は、業務の標準化、業務の効率化、業務品質の向上、生産性の向上、コスト削減、労働環境の改善など多くのメリットがあげられます。業務改善は目の前の日々抱える業務の課題を解決するだけにとどまらず、ひいては企業全体の経営の安定化・売上向上にもつながります。
新型コロナウイルスが契機となり働き方が大きく変わった今、ポストコロナ時代に本当に必要な業務改善を、経験豊富なIT専門コンサルタントが、自社に最適な完全オーダーメイド型コンサルティングで伴走支援いたします。
| 業務の可視化 業務フロー図や業務マニュアルにより現在の業務を可視化し、改善課題を抽出します。 | 業務の標準化 だれが行っても毎回同じ結果がでるように業務を標準化し属人化を排除します。 | 業務の効率化 重複作業の排除やシステムの有効活用により作業時間の削減や作業分担の適正化を図ります。 |
 | ||
| 業務管理ルールの構築 標準化・効率化された業務をマニュアル化し、業務品質の向上や指導内容の統一化を図ります。 | 業務の全体効率化 部門横断的な業務に対して、全体最適となる業務プロセスに変更し、全体効率化を図ります。 | 経営の安定化・売上向上 業務改善後の先には、企業全体の経営の安定化、売上の向上を実現させます。 |
このような企業におすすめ
・事務作業やデータ入力・集計等、手入力による繰り返し作業が多く、手間ばかりかかっている・・・
・マニュアル化されていないため、担当者の技量に頼っており業務が属人化している・・・
・業務の自動化をしたいが、日々の業務に追われどこから手をつけてよいか分からない・・・
・システムを導入したが、使いこなせていない・・・
・システムを管理していた者が退職してしまい困っている・・・
・無駄が多く効率が悪いと思いながらも抜け出せていない・・・
・慢性的な人手不足だが人員確保が難しく、従業員一人当たりの業務内容が膨大だ・・・
・定型文書(企画書・報告書・議事録)が存在しない・・・
TOMAのコンサル事例
TOMAが担当させていただいた業務改善支援の事例になります。以下のリンクよりご覧ください。
・①業務課題抽出のサポート支援
・②請求書発行と入金消込の効率化支援
・③勤怠管理と給与計算の業務改善支援
業務改善コンサルティングサービスの内容
業務改善コンサルティング
業務改善コンサルティングサービスは、業務責任者、業務担当者とTOMAのコンサルタントでプロジェクトチームを組み、業務改善に取り組みます。フェーズを2つに分け施策を進めていきます。伴走型支援の総合コンサルティングサービスです。
| 第1フェーズ【業務の可視化】 |
| 推進担当者・現場担当者の方との詳細なヒアリングを行い、具体的な課題を抽出し、DX推進体制・計画をご提案いたします。 |
| 第2フェーズ【業務の効率化】 |
| 第1フェーズで明らかになった課題に対する改善を中心に実施します。改善に向けた進捗や達成度を観測しながら進めていきます。 |
料金
| 契約形態 | 価格 |
| 業務改善コンサルティング | 200,000円~ |
業務改善 パッケージソフト導入支援
貴社の業務効率化に向けて、会計・販売管理などパッケージソフトの導入をご支援します。総務、業務のそれぞれに対応したパッケージソフトで対応可能です。
| 導入支援 |
| 投資効果を見極めて最適なソフトを導入 TOMAでは、そのパッケージソフトが貴社の業務にフィットするものなのか、十分な効果を見込めるものなのかを入念に検討したうえで導入をご支援しています。「せっかく導入したのに実務にそぐわない・・・」「機能が多すぎて使いこなせない・・・」「導入前の方法のほうが効率が良かった・・・」といった無駄な投資に終わらないよう、最適なソフトをご提案します。 |
| 運用支援 |
| 効果的な運用のために徹底サポート 会計・販売管理・在庫管理ソフトは、様々な会社がその導入支援を行っていますが、「導入して操作説明をするだけ」の会社が多いのが現状です。TOMAのサービスは操作説明だけに終わらず、継続的に運用支援をしていくのが特徴。「すでにソフトを導入しているけど業務効率が上がらない・・・」という企業様もお気軽にご相談ください。経験豊富なコンサルタントが、効果的な運用方法・改善ポイントなどをアドバイスします。 |
料金
支援内容やパッケージソフトの内容によって異なります。
詳細につきましては下部の無料相談・お問い合わせよりご連絡ください。