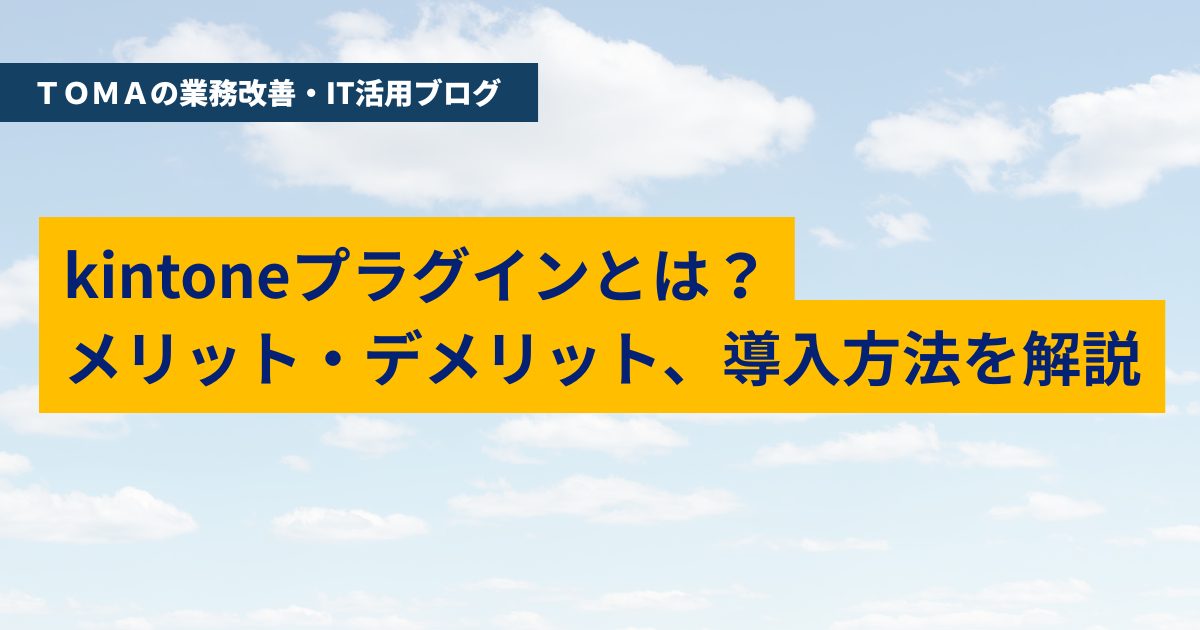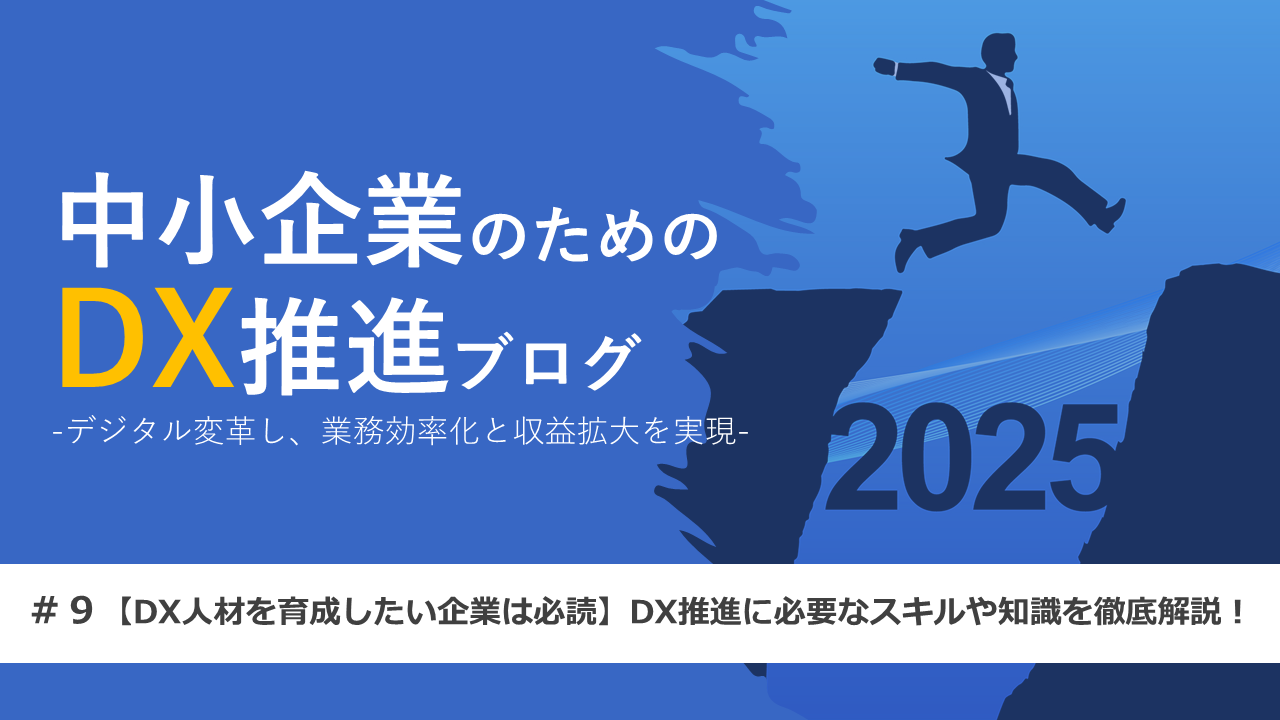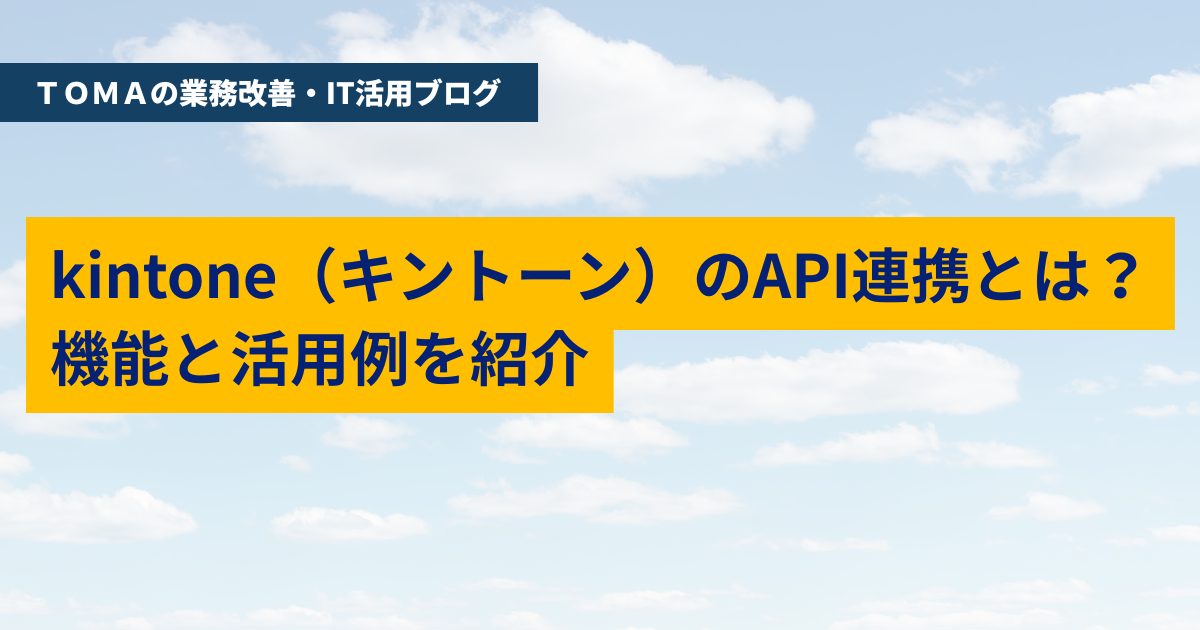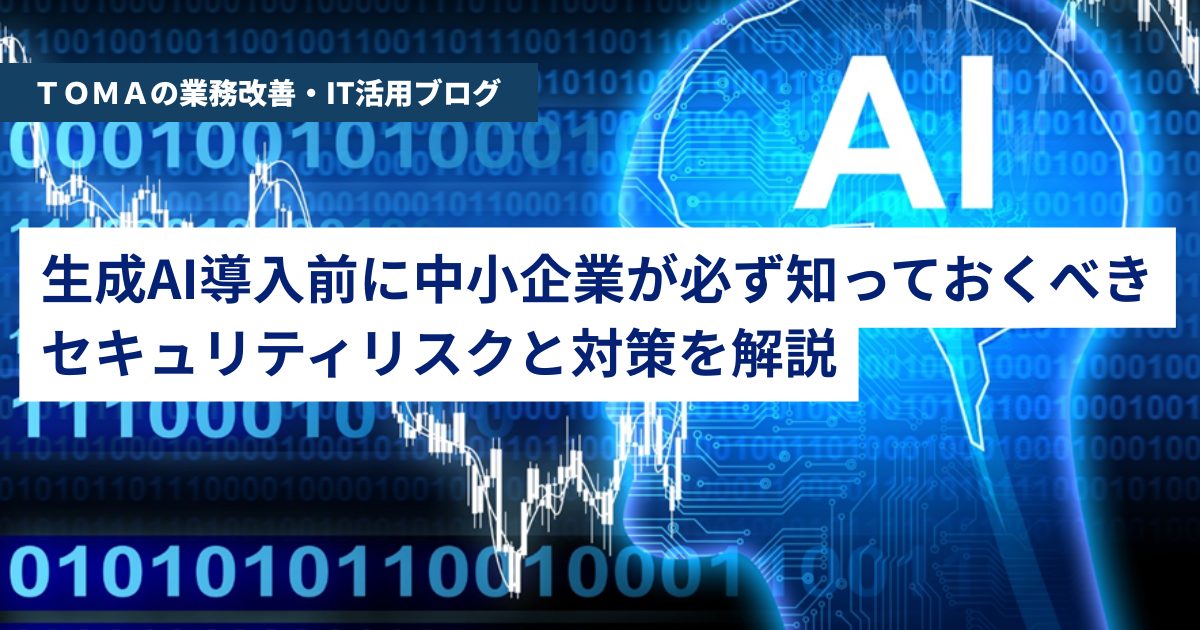kintoneユーザーのなかには、機能を拡張できるプラグインを活用したいと考えている方も多いのではないでしょうか。kintoneのプラグインは、プログラミング知識がなくても標準機能を手軽に拡張し、業務効率を向上できる便利なツールです。
本記事では、kintoneプラグインのメリット・デメリット、具体的な活用例、導入・設定方法までをわかりやすく解説します。kintoneのプラグインの導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
こちらの記事もおすすめ
・kintone(キントーン)とは?特徴やメリット・デメリット、料金について解説
・kintone(キントーン)でできること・できないことは?導入する際の注意点も解説
・kintoneでExcelのデータを取り込む方法とは?脱Excelの必要性とkintoneのメリットを解説
・kintone(キントーン)のAPI連携とは?機能と活用例を紹介
目次
kintoneのプラグインとは?

kintoneのプラグインとは、kintoneに拡張機能を追加できるパッケージソフトです。プログラミング知識がなくても、インストールするだけで業務に合わせた機能拡張が可能で、現場の運用効率や利便性の向上が期待できます。
例えば、フィールドの非表示や選択肢の動的絞り込みなど、標準機能では対応しきれない細かな制御もノーコードで実現可能です。
kintoneでは、多様な業務ニーズに応じたプラグインが豊富に用意されています。必要なものをアプリに取り込み設定するだけで、kintoneを自社のニーズに合ったツールへと進化させることができます。
kintoneのアプリとプラグイン、連携サービスの違い

「アプリ」は、kintoneの基本機能を使って作成する、データ管理や業務フローなどのベースになるものです。
「プラグイン」は、kintone内でインストールし、利用・設定できる拡張機能で、アプリの機能を拡張するものです。
また、「連携サービス」はkintoneと外部ツール(コミュニケーションツール、会計システム、Web入力フォームなど)との業務連携を実現するサービスです。APIなどを利用してkintone外部と連携します。
プラグインと連携サービスのどちらを利用してアプリをつくるかは、業務課題やニーズによって異なります。自社に適した方法を選ぶことが難しい場合は、専門家に相談しましょう。
kintoneのプラグイン、連携サービスでできること

kintoneのプラグインを導入すれば、標準機能だけでは実現できないさまざまな業務の効率化が可能です。ここでは、代表的な活用例として「帳票出力」「外部サービス連携」を紹介します。
業務帳票を簡単に出力
kintoneのプラグインを使えば、見積書や請求書、納品書などの帳票をPDFやExcel形式で出力できます。マウス操作だけで簡単に作成できるのも魅力です。
多くのプラグインでは、既存の帳票レイアウトや自社独自のフォーマットをそのまま利用できるため、長年使い慣れた書式を変更せずに済みます。
これにより、経理部門や営業部門での帳票作成・出力作業が効率化し、転記作業やレイアウト調整の手間も省けます。
外部サービス連携でリアルタイムな情報共有
TeamsやSlack、LINE WORKSなどの外部ツールと連携できるプラグインを導入すれば、kintone上の更新情報をリアルタイムで外部サービスに通知できます。
例えば、kintoneで管理している営業案件の進捗情報をSlackに自動通知したり、kintoneからTeams会議のスケジュール調整を行なったりすることも可能です。
部門間の情報共有がスムーズになるだけでなく、業務の効率化や情報の見える化という観点からも、外部サービスとの連携は重要です。
また、外部連携サービスを活用することにより次のようなことも実現可能です。
Webフォーム連携で顧客データを自動収集
kintoneとWebフォームを連携することで、Webフォームに入力された情報を自動でkintoneに登録することが可能です。
例えば、お問い合わせフォームやアンケート、申し込みフォームなどから得たデータを手作業で転記する必要がなくなるため、入力ミスや漏れを防げます。
なお、データはリアルタイムでkintoneに反映され、リード獲得から顧客管理までの流れがシームレスにつながります。限られた人員で効率的に顧客情報を管理できるため、特に中小企業などで重宝するでしょう。
kintoneのプラグインを活用するメリット

kintoneプラグインの導入は、単なる機能追加にとどまらず、業務の質やチームの生産性にも大きな変化をもたらします。ここでは、プラグインの導入によって得られる具体的なメリットを4つ紹介します。
さまざまな業務の改善に役立つ
kintoneプラグインを導入すれば、日々のデータ入力や分析作業を自動化でき、現場の作業負担を大幅に軽減することが可能です。
例えば、ルックアップを自動更新するプラグインでは、手作業で行なっていた業務を自動化できるため、転記ミスを防ぎ作業時間も削減できます。また、複雑なワークフローや承認フローの管理・最適化もプラグインで実現可能です。
これにより、業務プロセスの属人化を防ぎ、誰でも同じ手順で作業を行う環境が構築できます。
各種機能を拡張できる
標準機能だけでは実現が難しい高度な業務要件や、現場の細かなニーズに柔軟に対応できる機能の拡張性も、kintoneプラグインのメリットです。
例えば、複数条件での横断検索、複合的な条件での一覧表示、一覧表示のカスタマイズなど、業務に必要な機能をノーコードで手軽に追加できます。
また、SlackやTeams、Googleサービスなどの外部サービスと連携するプラグインを使えば、kintoneの枠を超えた情報共有や通知の自動化も可能です。
ほかにも、プラグインを活用してユーザーが直感的な操作をしやすくなるようにUI/UXを改善することで、利用者の満足度向上に役立ちます。
ノーコードでのカスタマイズができる
プログラミングの知識がなくても、ノーコードで機能の追加やカスタマイズできることがメリットです。多くのプラグインは、ドラッグ&ドロップなどの直感的な操作だけで導入・運用が可能です。そのため、専門的な知識を持たない現場の担当者でも、すぐに使いこなせます。
現場の業務を熟知した担当者が自らカスタマイズすることで、現場主導で業務アプリケーションの開発や改善が行なえます。
なお、kintoneのプラグインは定期的なアップデートにより、セキュリティ向上や新たな機能が追加されています。そのため、新たな課題や技術へも柔軟に対応できるでしょう。
コスト削減につながる
kintoneプラグインを導入すれば、必要な機能を簡単に追加できるため、外注や自社でのシステム開発に比べて大幅なコスト削減が期待できるでしょう。
複雑な工程がなく短期間で開発・運用できることで、開発にかかる時間や人件費を抑えられます。
例えば、設計から実装、テストまでを自社開発で行う場合、数百万円のコストと数ヵ月の時間がかかる可能性があります。
しかし、kintoneプラグインを導入すれば、月々数千円から利用できるものもあるので、導入も数時間で済みます。
特に予算の限られる中小企業にとっては大きなメリットです。
kintoneプラグインを活用するデメリット

kintoneプラグインは業務効率化に役立つ一方で、デメリットもあります。ここでは、3つのデメリットについて解説します。
セキュリティに関するリスクがある
kintoneプラグインのなかには、外部の開発者や企業が提供するものも多く存在します。信頼できる提供元かどうかを十分に確認せずに導入してしまうと、情報漏洩などのセキュリティリスクが発生するおそれがあります。
特に「提供元が不明確」、「セキュリティ対策が不十分」といったプラグインは、kintone内のデータが外部に送信される危険性があるため注意が必要です。
また、プラグインがkintoneのデータにアクセスする際の権限管理も重要なポイントで、必要以上の権限を与えてしまうと意図しないデータ流出のリスクが高まります。
導入前には、プラグインの提供元の利用実績などを確認し、信頼できるものを選びましょう。ユーザー評価の高いものやレビューの多いプラグイン、サイボウズ公式パートナーの提供するプラグインから検討すると安心です。
プラグイン同士の互換性の問題で、不具合が生じることがある
kintoneでは、業務の多様なニーズに応えるため、さまざまなプラグインが提供されています。
しかし、複数のkintoneプラグインを同時に導入すると、プラグイン同士の競合や干渉によって予期せぬ不具合や動作不良が発生することがあるため注意が必要です。
また、kintone本体やプラグインのバージョンアップ時に互換性が失われ、突然プラグインが動作しなくなるケースも報告されています。
トラブルを避けるためには、導入前に必ずテスト環境で十分な動作確認をしましょう。また、同じ開発元のプラグイン同士であれば不具合などの問題が少なくなります。
なお、万一のトラブル発生時に備えて、アップデート前にデータのバックアップを取っておくことも重要です。
拡張できる機能には限界がある
kintoneプラグインは便利ですが、すべての業務要件や高度なカスタマイズに対応できるわけではありません。複雑な処理や特殊な業務フロー、大規模な基幹システムとの連携など、プラグインだけでは実現が難しいケースもあります。
こうした場合は、JavaScriptによる独自カスタマイズやkintone APIを活用した外部システム連携を検討する必要があります。
また、プラグインの仕様やkintone本体の制約で思い通りの機能拡張ができない場合もあるため、導入前に要件を整理し、必要に応じて専門家に相談しましょう。
プラグインに依存しすぎると運用の柔軟性が失われたり、将来的な変更が困難になったりするケースもあります。中長期的な視点で、最適な拡張方法を検討することが重要です。
プラグインの導入方法

ここでは、プラグインの導入方法を紹介します。おおまかな導入手順は、以下のとおりです。
- プラグインをインストール
- アプリにプラグインを追加・設定
なお、kintoneのプラグインを利用するには「スタンダードコース」以上での契約が必要です。
導入方法は2種類
kintoneプラグインを導入する方法は2つあります。
1つ目は、kintone公式のプラグイン紹介ページから必要なプラグインを探してインストールする方法です。公式のプラグイン紹介ページでは、サイボウズ公式パートナーが提供するプラグインを中心に、信頼性の高いものを簡単に見つけることができます。
2つ目は、外部ベンダー等のサードパーティが提供するプラグインを利用する方法です。
どちらの場合も、提供元のWebサイトなどからプラグインファイルをダウンロードし、kintoneに手動でインストールする必要があります。プラグインファイルのインストール手順は次章で紹介しています。
プラグインのインストール手順
サードパーティが提供するプラグインのファイルは、以下の手順でインストールします。
<プラグインのインストール手順>
- kintoneの画面右上にある歯車アイコンから「kintoneシステム管理」を開く
- 「その他」から「プラグイン」を選択
- 左上の「読み込む」をクリック
- 「参照」をクリックし、ダウンロード済みのプラグインファイルを指定
- 「読み込む」をクリックしてプラグインを追加
プラグインをアプリに追加・設定する方法
インストールしたプラグインを、アプリに追加・設定します。手順は以下のとおりです。
<アプリへの追加・設定手順>
- 使用したいアプリの「設定」を開く
- 設定画面で「プラグイン」をクリック
- プラグイン画面で「追加する」をクリック
- 追加画面で追加するプラグインにチェックし、「追加」をクリック
- 必要に応じて各種オプションや動作条件を設定する
- 設定後は「保存」し、「アプリの更新」を行う
実際にアプリ上で動作することを確認します。テスト環境で十分に動作確認を行い、業務に最適な形に調整しましょう。
TOMAのkintone導入支援サービスで業務効率化を
kintoneのプラグインは、kintoneの拡張機能を簡単に追加できる便利なツールです。プラグインを活用することで、帳票出力やWebフォーム連携、外部サービスとのリアルタイムな情報共有などが可能となります。
業務改善やコスト削減、カスタマイズしやすいといったメリットがある一方で、セキュリティや互換性、拡張性の限界は十分に留意する必要があるでしょう。
複雑な業務要件や大規模なシステム連携には対応できないケースもあるため、導入時には専門的な知識や経験に基づいて慎重に検討しましょう。
そこでおすすめしたいのが、TOMAの「kintone導入支援サービス」です。
TOMAでは、長年の業務改善コンサルティングのノウハウを活かし、単なるシステム化にとどまらず、最適な業務フローの提案からシステム構築まで一貫してサポートします。kintoneの導入や活用でお悩みの方は、ぜひTOMAの「kintone導入支援サービス」をご検討ください。
その他、kintone関連サービスはこちらから
また、kintoneに関してご相談も受け付けております。以下の無料相談・お問合せよりご連絡ください。