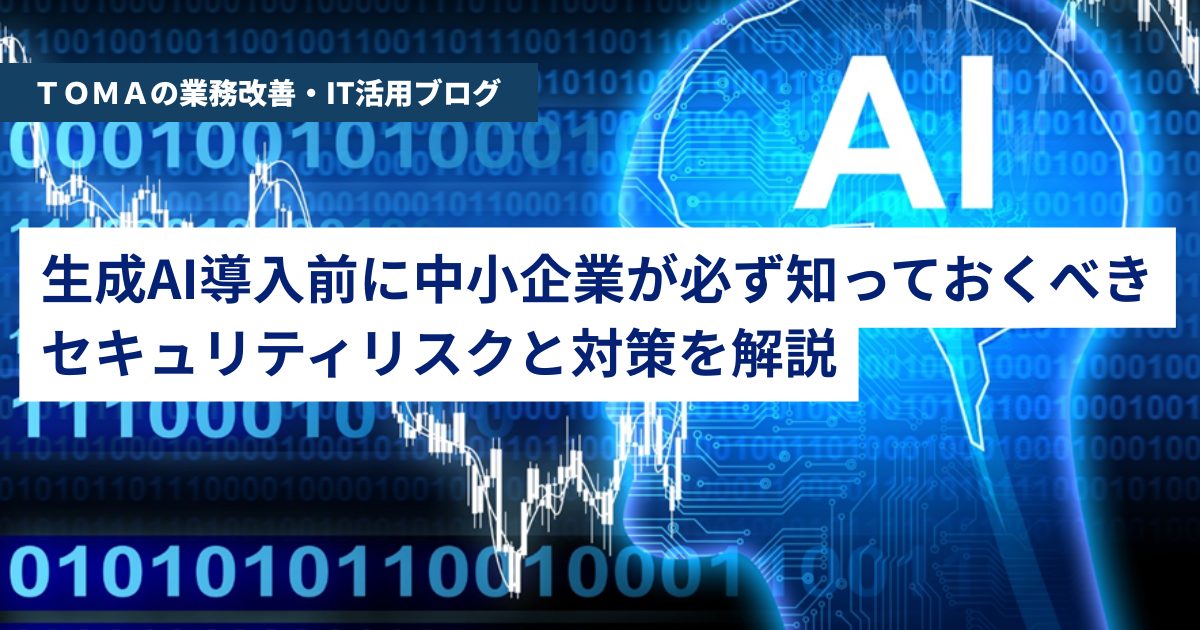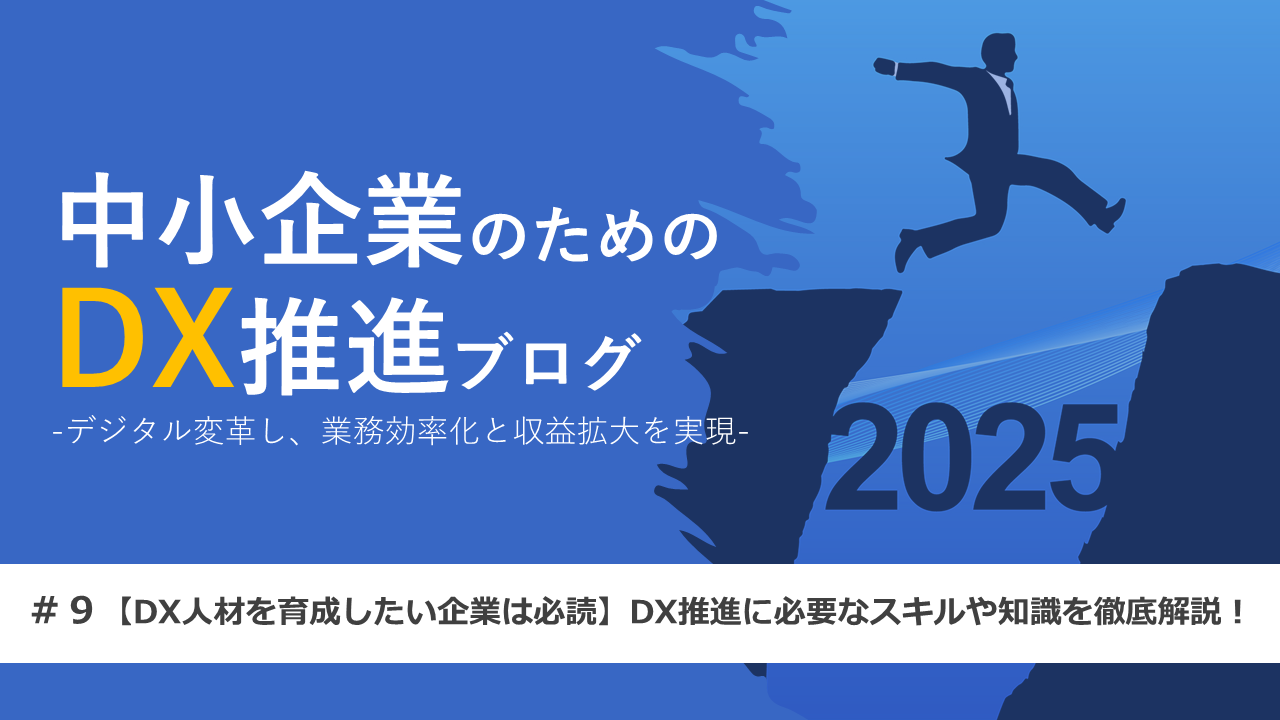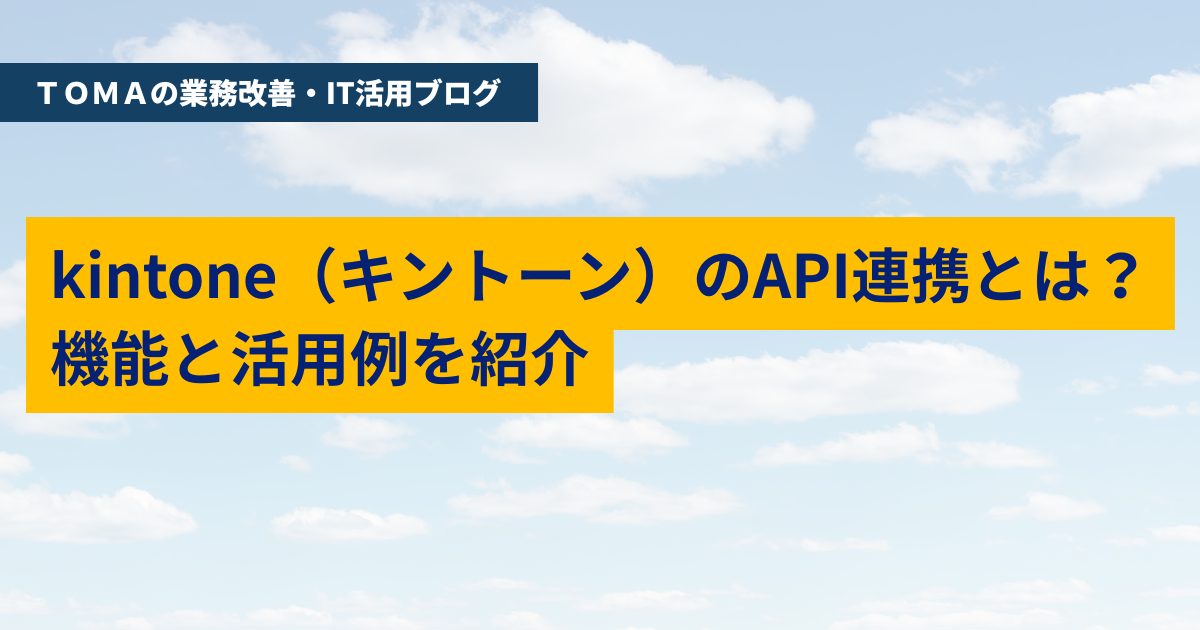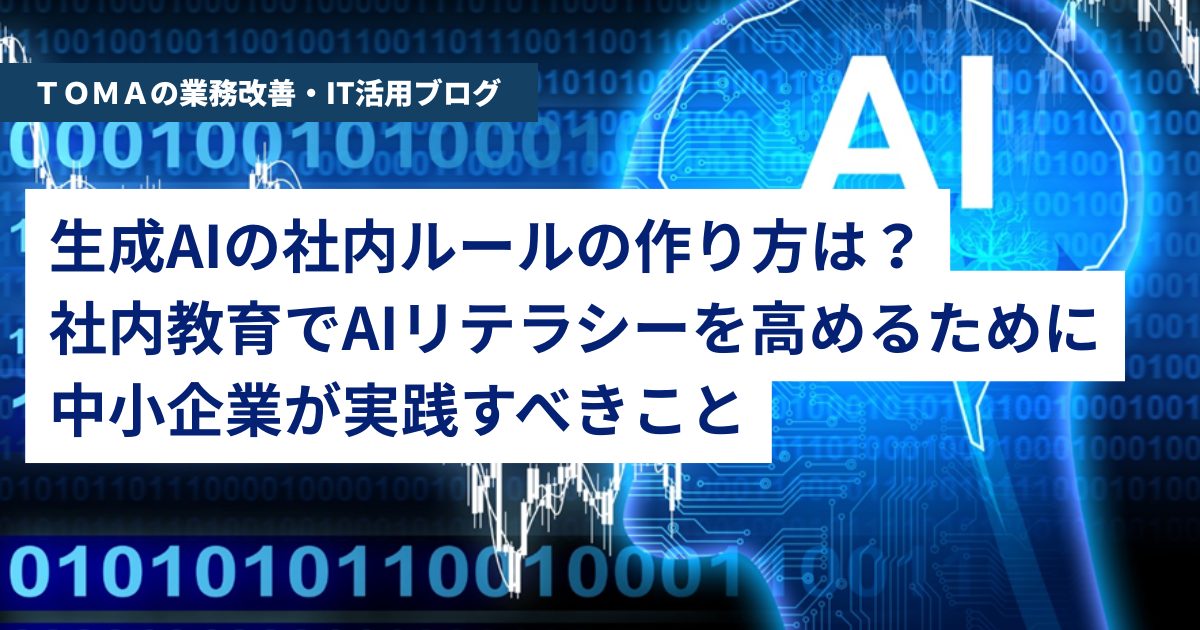AI技術の進化がビジネスを加速させる一方で、セキュリティリスクも増大していることはご存じでしょうか。
生成AIは業務効率化や新たな価値創出など大きなメリットをもたらしますが、情報漏洩や誤情報の拡散、法的リスクなどの課題も抱えているツールです。
この記事では、中小企業が生成AIを安心して活用するために理解しておくべきリスクと、導入時におけるガイドラインの必要性についてわかりやすく解説します。
目次
生成AIが抱えるセキュリティリスクとは

ChatGPTをはじめとする生成AIは、外部からの攻撃や知的財産権の侵害、悪用リスクといった複合的なセキュリティリスクを抱えています。まずは、生成AI自体が持つ代表的なリスクを紹介します。
攻撃されるリスク
生成AIは大量の情報・データをもとに学習しているため、外部からのサイバー攻撃のターゲットになりやすいといえます。
代表的な攻撃手法として挙げられるのは、悪意のある指示によってAIを誤動作させて機密情報を盗み取ることを目的とした「プロンプトインジェクション」です。
その他、AIに不正な指示を直接送り込むケースだけでなく、AIが参照する外部情報源に不正なデータを仕込む「間接プロンプトインジェクション」も存在します。
このような攻撃を防ぐには、AIに関わる情報処理の権限管理を徹底し、特にオープンなサービスの場合には入力内容とその処理に細心の注意を払わなければなりません。
盗用されるリスク
盗用のリスクは、生成AIモデル自体が盗用される場合と、生成コンテンツに関する盗用問題に分けられます。生成AIモデル自体の盗用問題は、例えば自社開発のAIモデルが盗用され、無許可で商用目的や悪意ある活動に利用される可能性があります。
一方、生成コンテンツに関する盗用問題は複雑です。AIが学習したデータセットに著作権を持つコンテンツが含まれている場合、生成物が知的財産権を侵害するリスクが高まります。このような問題は、企業のブランド価値や信頼性を損なうだけでなく、法的なトラブルにも発展しかねません。
その他、ブログ記事やマーケティングコピーなど、自社で作成し権利を持ったコンテンツが無断で生成AIに学習され、意図せず他者に盗用されるケースも考えられます。
誤用や悪用のリスク
生成AIは、意図しない誤情報や不適切なコンテンツを生成する可能性があります。
誤情報や不適切なコンテンツをそのまま利用してしまうと、企業のブランドや信用に傷がつきかねません。AIの仕組みがブラックボックス化し、開発者でさえその動作を完全に予測・説明できない場合には、誤情報の拡散リスクが高まります。
また、生成AIの悪用も社会的な問題となっています。例えば、ディープフェイク動画による情報操作・扇動、生体情報の偽造による生体認証システムのすり抜けなど、生成AIを悪用した事例が多く報告されています。
特に、説得力のあるフィッシングメールやマルウェアの自動生成など、サイバー犯罪への転用リスクも指摘されているため、注意が必要です。
企業が生成AIを社内運用する際にすべきこと

生成AIを社内で活用する際には、情報漏洩や法的リスク、誤情報の取り扱いなど多方面のリスクに十分な注意が必要です。ここでは、企業が生成AIを安全かつ効果的に運用するために押さえておくべきポイントを解説します。
情報漏洩
生成AIに企業の機密情報や個人情報を入力すると、そのデータが自社の管理下を離れ、AIサービス提供会社のサーバーに保存される可能性があります。2023年には、ChatGPTに社内の機密情報を入力したことから、情報漏洩が発生した事例が報告されています。
生成AIサービスのなかには、入力されたデータを学習や品質向上のために利用するものがあり、一度入力した情報は完全に削除できない可能性があります。そのため、入力した情報がどのように保存・利用されるのかを事前に確認しましょう。
併せて、機密性の高いデータの入力を制限するような社内ルールを策定することが重要です。さらに、従業員への教育を通じて情報管理の意識を高めることも、情報漏洩防止の観点から欠かせません。
法的な問題(知的財産権やプライバシーの権利など)
生成AIは「無から有を生み出すもの」ではなく、既存の膨大なデータを学習して新たなコンテンツを生成するツールです。そのため、学習データや生成物が著作権・商標権などの知的財産権を侵害するリスクがあります。
例えば、著作権で保護された文章や画像を無断で学習させたり、それをもとに生成されたコンテンツを商用利用したりした場合、著作権者から法的措置を受けることになりかねません。
また、AIが個人情報を含むデータを学習した場合、プライバシー権の侵害となるおそれもあるため、個人情報保護法やGDPRなどの法規制にも注意が必要です。AI導入時には、利用規約や契約書の確認、法務部門との連携を強化するなど、リスクを最小限に抑える取り組みが欠かせません。
さらに、自社で開発したAIモデルが第三者に盗用されるリスクも考慮して、契約や技術的な対策による権利保護を徹底することが求められます。
ハルシネーション(誤情報)
生成AIは、学習データに基づいて回答やコンテンツを生成しますが、その内容が必ずしも正確であるとは限りません。AIがもっともらしく誤った情報を生成する現象の「ハルシネーション」には注意が必要です。
誤った生成結果をそのまま業務に利用した場合、顧客への誤った案内や経営判断の誤りなど、企業活動に深刻な影響を及ぼすリスクがあります。
例えば、AIが生成したレポートや分析結果を鵜呑みにして意思決定を行うと、重大な損失や信用失墜につながるでしょう。
このようなリスクを回避するためには、生成AIの出力内容を必ず人間が確認・検証する体制を整える必要があります。また、生成AIのプロンプトに「根拠を明示させる」「不明な場合は明確に伝える」といった文言を含むことも有効です。
生成AIの利便性を業務で活かすために、不正確性への警戒と適切な運用ルールの整備を徹底しましょう。
社内情報に対するセキュリティ対策
生成AIを安全に社内で運用するためには、情報管理体制やセキュリティ対策の強化が不可欠です。
まず、機密情報や個人情報は入力しないことを明文化したガイドラインを作成し、全従業員に周知徹底する必要があります。さらに、AIサービスの利用範囲や用途を明確に定め、業務ごとにアクセス権限を制限することも重要です。
情報漏洩や不正利用を防ぐため、AIサービスの選定時にはセキュリティ監査やデータ保護機能を確認します。必要に応じて、暗号化やアクセスログの管理など技術的な対策も講じましょう。
また、違反時の対応や罰則についてもルール化し、組織全体で統一した運用を心がけることが求められます。
AIリテラシーの向上
生成AIを効果的かつ安全に活用するうえでは、従業員一人ひとりのAIリテラシー向上が必要です。AIの仕組みやリスク、適切な使い方を理解していないと、誤用や情報漏洩などのトラブルにつながりかねません。
定期的な研修やマニュアルの整備、社内勉強会の開催を通じて、AI活用に関する知識と意識を高める取り組みを実施しましょう。さらに、AIの利用状況を定期的に評価し、問題点や改善点を洗い出すことで、継続的なリスク管理と業務効率化の両立が可能になります。
AI技術の進化に合わせて教育内容も随時アップデートし、全従業員が安心してAIを使える環境を整備することが大切です。
企業が生成AIを導入する際はガイドラインが不可欠
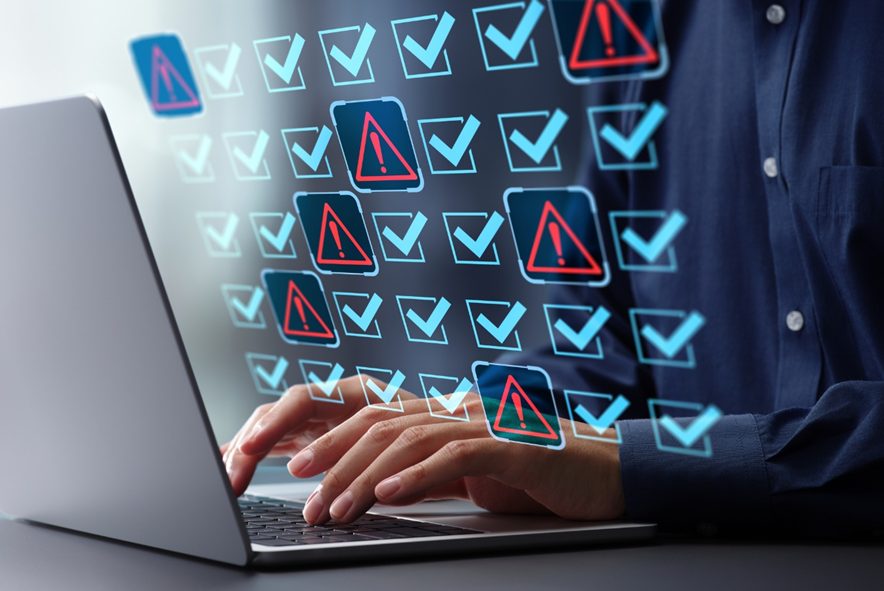
生成AIを安全に利用するためには、組織全体で遵守すべきガイドラインの策定が欠かせません。ここでは、セキュリティリスクを最小化しつつ効果を最大化するガイドライン策定のポイントについて解説します。
生成AIガイドラインに含めるべき基本要素
ガイドラインの基本要素として、利用可能なAIツールの明確なリスト、プロンプト入力可能な情報の定義を明記しましょう。
さらに、利用申請の手続きや著作権確認義務などの生成物の利用ルール、研修計画などについても記載します。誤作動時の対応フローや責任体制、セキュリティインシデントへの対応手順も記載が必要です。
特に重要なのは、データ入力時の機密情報保護措置、虚偽出力の可能性への注意喚起、著作物に対する盗用リスクの周知徹底です。
自社の事例だけではなく、他社の成功・失敗事例を参考にすることで、実践的な内容を構成できます。ガイドライン策定時には法務部門との連携が不可欠です。加えて、専門家の助言を求めることを推奨します。
自社業務における生成AI用途・影響範囲を確認
ガイドラインを作成する際には、まず自社のどの業務で生成AIを活用するのか、その用途について具体的に整理することが大切です。例えば、営業部門での提案書作成や企画部門での市場分析の補助など、部門ごとにAIの活用方法を明確化します。
次に、AI導入によって影響がおよぶ業務やシステムを事前に洗い出し、顧客データの取り扱いや既存システムとの連携におけるリスクも評価しましょう。例えば、製造業であれば設計データの漏えいリスク、サービス業であれば顧客対応時の誤情報伝達リスクなど、業界や事業の特性に合わせて検討することが重要です。
このような分析を通じて、どの従業員を対象に研修や教育を実施するか、アクセス権限をどのように設定するかといった運用面の方針も明確になります。用途や影響範囲を可視化し、部門間で情報を共有することで、ガイドラインの実効性を高められます。
ガイドラインは定期的な見直しと更新が必要
生成AIの技術は日々進化しており、それにともなって新たなリスクや課題が発生しています。したがって、ガイドラインも一度作って終わりではなく、定期的に見直しと改定を行うことが不可欠です。
例えば、AI技術の進展によって新しい機能やサービスが登場した場合や、法規制が変更された場合には、速やかにガイドラインへ反映させる必要があります。
また、実際の運用で発生したトラブルや従業員からのフィードバックをもとに、内容を柔軟に修正することも大切です。ガイドラインの更新は単なる文書の改訂が目的ではなく、全従業員がその内容を理解し、日々の業務で適切に生成AIを活用できるようにすることが本質です。
定期的な研修や勉強会を通じて理解度を高め、ガイドラインが形骸化しないよう運用していくことが求められます。
まとめ
生成AIの導入は、中小企業の競争力強化や業務効率化に大きな可能性をもたらします。しかしその一方で、セキュリティリスクや法的課題、誤情報の拡散など、多くの注意点が存在することも事実です。
したがって、生成AIの安全な活用のためには、ガイドラインの策定と定期的な見直し、社内リテラシーの向上、情報管理体制の強化が欠かせません。全社的な意識と体制を整えることによって、リスクを最小限に抑えつつ生成AIのメリットを最大限に活かせるでしょう。
TOMAでは、AI活用の環境づくりを専門家が支援する「AI導入支援サービス」を提供しています。こちらのサービスでは、生成AIの活用をともに考え、作り上げていくことが可能です。
従業員教育から導入・運用まで段階的に支援するため、業務全体を鑑みて効果的な導入・活用案を提案できる強みがあります。導入・活用支援だけでなく、運用ガイドラインの策定支援も対応します。
AI関連の有資格者による根拠・裏付けがあり、IT部門の専門家が在籍していますので、安心してお任せください。「AI活用の進め方がわからない」「社内のAIリテラシーを向上させたい」とお悩みの場合には、ぜひ一度ご相談ください。
ご相談は以下の無料相談・お問合せよりご連絡ください。