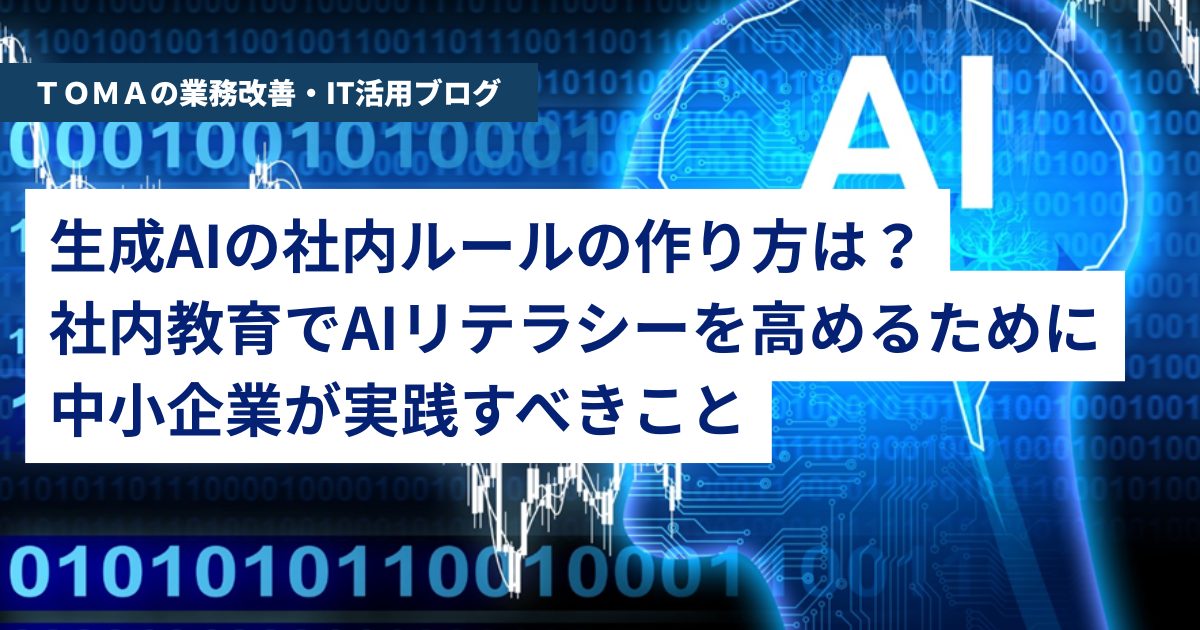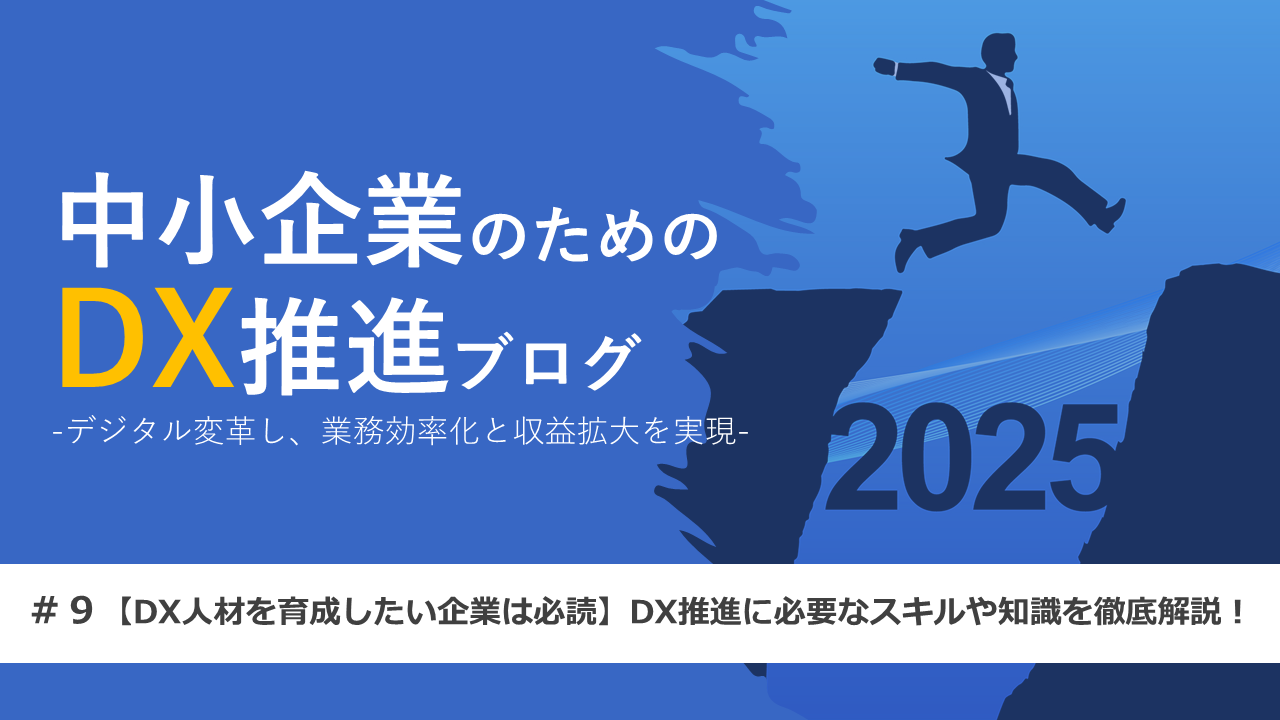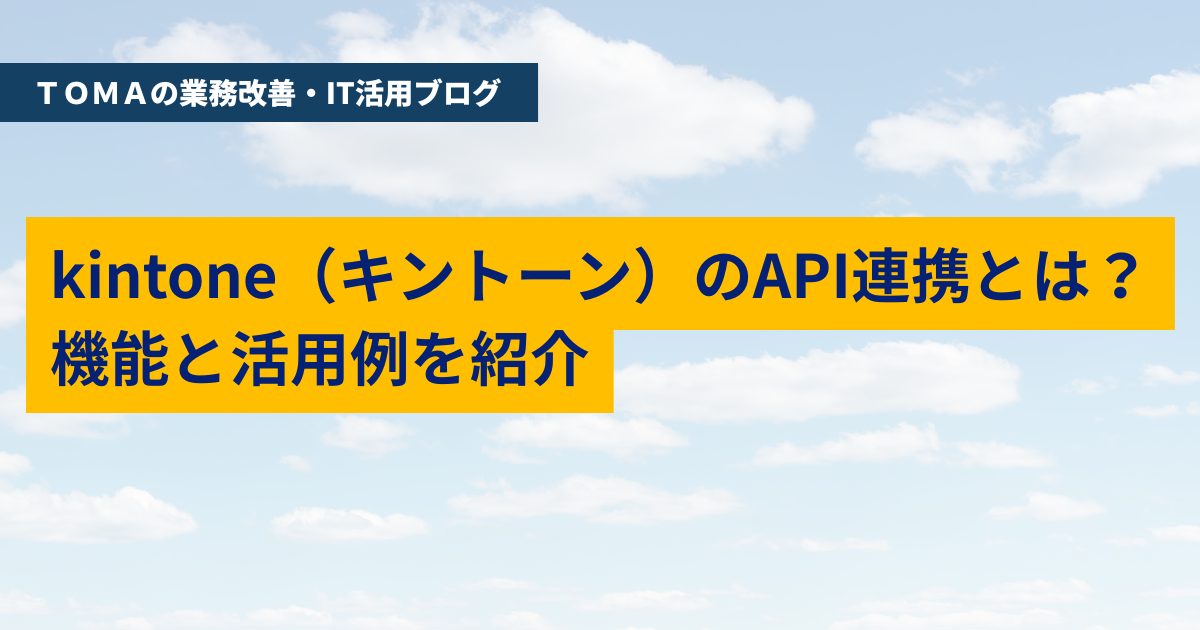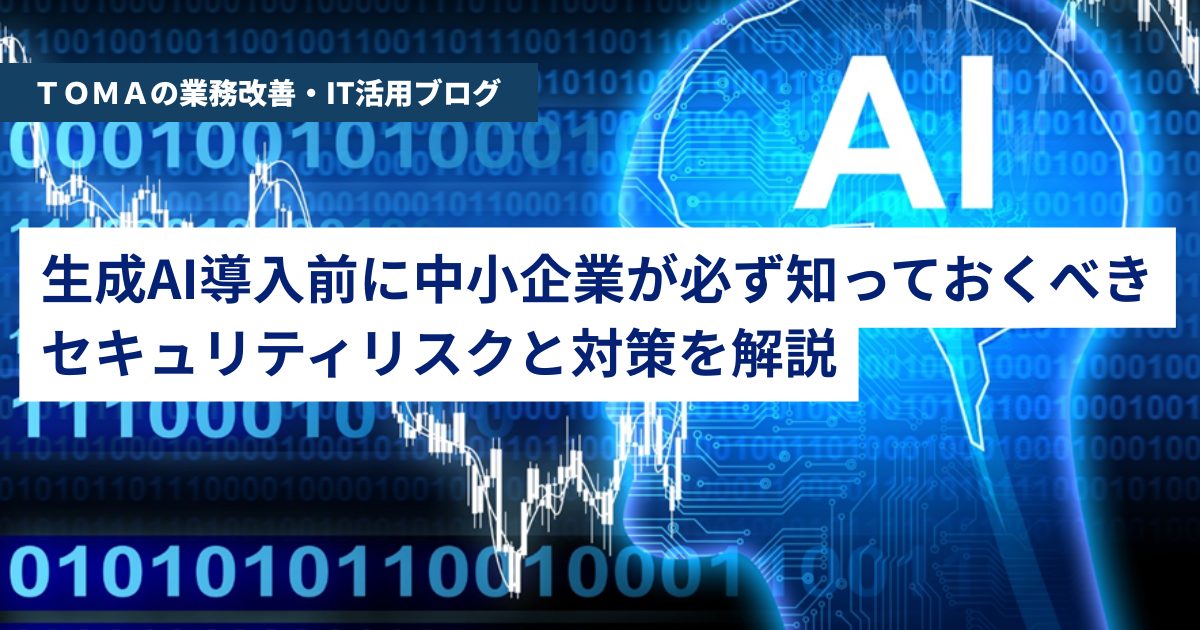生成AIの活用は、あらゆる企業にとって競争力を高める重要な手段になっています。しかし、安直な生成AIの活用は、情報漏えいや著作権侵害などのトラブルを招きかねません。
安全かつ効果的に生成AIを活用するためには、明確な社内ルールを整備し、従業員一人ひとりが正しいAIリテラシーを身に付ける必要があります。
この記事では、生成AIを安心して活用するために、中小企業が実践できる社内ルールの作り方を紹介します。社内教育に有効な手段や社内研修の進め方などについても解説しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
生成AIに関する社内教育が必要な理由

生成AIは急速に普及しており、大企業のみならず中小企業も対応が迫られています。生成AIがもたらす恩恵を最大限に享受するためにも、社内教育の必要性について認識しておくとよいでしょう。
ここでは、生成AIに関する社内教育が必要とされている理由を紹介します。
ビジネスシーンにAIが浸透しつつあるため
生成AIの導入には業務効率化やコスト削減などのメリットがあるため、ビジネスにおいては大きな注目の的です。メール作成や市場動向のリサーチなど、従来は人が担っていた業務を生成AIが自動的に行えるようになります。
総務省の発表「令和5年 通信利用動向調査報告書(企業編)」によると、2023年時点でIoTやAIなどのシステムを導入している企業は全体の16.9%でした。導入予定がある企業も11.3%で、ビジネスシーンにAIが普及しつつあることがわかります。
特に金融・保険業や情報通信業などは、ほかの産業に比べてAIなどを導入している割合が高くなっています。
企業全体で生成AIへの認識を深め、時代の流れから取り残されないようにすることが急務となりつつあります。
AI技術の向上が競争力強化につながるため
従業員が生成AIを使いこなせるようになれば、データ分析や情報収集など、幅広い領域でそのメリットを享受できます。
生成AIは人間とは異なり、その日のコンディションなどに作業量が左右されることはありません。ヒューマンエラーなどもなく、安定してタスクを正確にこなしてくれます。
また、簡単なタスクは生成AIに任せられるようになるため、従業員はコア業務に多くのリソースを割くことが可能です。組織全体のデジタルリテラシーが生成AIの導入によって底上げされ、企業としての競争力が強化されます。
特に中小企業では、まだまだAIの導入が進んでいない状況です。いち早く最新技術を取り入れて競合他社に差を付ければ、有利なポジションを確立できる可能性があります。
コンプライアンス学習によるリスクヘッジのため
生成AIは完璧なツールではなく、使い方を間違えると企業に大きな損失をもたらすおそれがあります。知識のない従業員が不用意に生成AIを使うと、情報漏えいや著作権侵害といったトラブルに発展するおそれもあるでしょう。
また、生成AIが提供する情報には誤りが含まれている場合があります。AIが誤った情報に基づいてもっともらしく説明する現象は「ハルシネーション」と呼ばれ、AI活用における課題の一つとされています。
生成AIが出力した情報を鵜吞みにしてそのまま利用すると、企業の信頼性低下にもつながりかねません。コンプライアンスの面でリスクヘッジをするためにも、生成AIに関する社内教育は重要です。
生成AIの社内ルールの作り方

生成AIの社内ルールを作る際は、まずルールを作る目的を明確にする必要があります。生成AI活用のルールが明文化されれば、従業員はルールの範囲内で安心して生成AIを活用することが出来るでしょう。
生成AIの社内ルールに優先的に盛り込むべき内容としては、個人情報や機密情報を入力しない、出力された情報を鵜呑みにしないなどの注意事項が挙げられます。情報漏えいや不正確な情報の発信といった事態を防ぐためにも、生成AIのリスクについて従業員に理解させておきましょう。
また、生成AIが出力したコンテンツの著作権にも注意が必要です。人間の作品を無断で模倣している可能性があるため、特に商用利用する場合には注意が必要な旨をルールに盛り込みます。
ルールの対象とする生成AIや、生成AIの利用を禁止する業務領域なども明文化しておきましょう。その他、生成AIが原因でトラブルが起きたときの対応手順を定めておけば、被害の拡大を抑えやすくなります。
策定した生成AIの社内ルールを周知し、従業員にしっかりと守らせることが大切です。
生成AIの社内教育に有効な3つの手段

生成AIに関する社内教育を実施する際には、社内講師や外部講師、eラーニングなどを活用する方法が考えられます。ここからは、生成AIに関する具体的な社内教育の方法について3つ取り上げ、それぞれの方法の特徴やメリット・デメリットについて解説します。
社内講師の活用
社内で講師を育成し、AI研修を内製化する方法です。研修を内製化すれば、コストを抑えて継続的な学習環境を実現できます。
また、実務に精通している社内人材が研修を担当すれば、実務に即した実践的な形での指導を行えます。ただし、社内に専門知識を備えた人材がいない場合には、十分な教育を行うことが難しくなるので注意が必要です。
生成AIに関して深い知識を持つ人材がいない場合、研修の内製化はリスクが高いため、外部の専門家にアドバイスをもらうことが賢明です。
外部講師の活用
外部の研修サービスを利用し、生成AIのエキスパートに指導してもらう方法もあります。研修サービスを利用すれば最新技術を学べるうえに、ニーズに応じた幅広いプログラムを提供してもらえます。
内製化に比べてコストはかかりますが、生成AIの導入で業務効率化や競争力強化を図りたい場合にはおすすめの方法です。
なお、AI研修の外部リソースには多くの選択肢があるため、選び方には配慮する必要があります。
まず確認すべき点が、提供しているカリキュラムの充実度です。AI初心者が多い場合には基礎重視の内容、実務に活用したい場合にはハンズオン形式の実践的な内容など、目的に合ったカリキュラムを用意できるサービスを選ぶとよいでしょう。
また、講師の専門性の高さも研修の質を左右する要因です。生成AIは日進月歩の世界であり、最新の知識や技術に精通した専門家であれば信頼できます。そのため、実績豊富で多くの事例を交えながら講義できる講師に依頼することをおすすめします。
研修後のサポート体制も、比較検討すべきポイントの一つです。フォローアップがしっかりしていれば、研修で学んだ知識を定着しやすくなります。
さらに、研修と併せてツールの導入支援も行ってくれるサービスなら、生成AIに関して包括的にサポートしてくれるはずです。
テキスト・eラーニングの活用
テキストやeラーニングを活用すれば、従業員が場所や時間を選ばずに学習できます。日々進化する生成AIの技術を有効活用するためには、継続的な学習が不可欠です。ただし、テキストやeラーニングだけで生成AIの実践的なスキルを身に付けることは難しいでしょう。
専門家の研修で実践的なスキルを学び、eラーニングプラットフォームのオンデマンド学習などで知識を深める方法がおすすめです。外部の研修サービスとeラーニングなどを併用しながら、AIスキルを磨き続けることが大切です。
生成AIスキルに関する社内教育の進め方

社内教育で生成AIのスキルを効率的に育成するためには、適切な手順でプログラムを組むことが重要です。ここからは、生成AIスキルを培うための社内教育の進め方を、3つのステップに分けて紹介します。
1.目標の設定
まずは、社内教育によって達成したい目標を設定します。具体的には「生成AIの機能を理解する」「実務で生成AIを活用するスキルを習得する」といった目標が考えられます。
目標設定と同時に研修の効果を測定できるよう、定量的な評価基準を導入しておくとよいでしょう。
例えば、研修の前後で受講者にテストを実施して、理解度を確かめる評価方法が挙げられます。また、業務で生成AIを活用した事例を報告してもらえば、AI導入の具体的な成果を確認できるでしょう。
2.勉強会の開催
次に、生成AIについての知識を深めるための勉強会を開催し、生成AIの基礎知識やリスク管理などを学んでもらいます。
基礎知識に関して学ぶべき内容は、生成AIの仕組みや種類などです。ChatGPTやGeminiなど、生成AIごとの特徴や得意なジャンルなども押さえておくとよいでしょう。
勉強会では、具体的な事例を交えながら、生成AIの市場動向や情報漏えいのリスクなどを講義・ディスカッションします。受講者同士のコミュニケーションを通じて、生成AIへの理解をより深めてもらえるはずです。
3.実践的なスキルの習得
基本的な内容を学んだら、最後に実践的なスキルを習得します。ハンズオン演習で実際に生成AIを使いながら、実務で活用する方法を学びましょう。
研修の最終段階では、部門ごとにケーススタディを取り入れて、生成AIを実際に動かすのが効果的です。マーケティング部門なら最適なコンテンツ生成、営業部門なら顧客対応の自動化など、各部門で実践的な学習内容を設定します。
自社の業務フローをもとに、どのようなタスクでAIを活用できるのかイメージしながら研修を進めるとよいでしょう。
生成AIの社内教育の効果測定と継続的な改善のポイント

生成AIの導入で業務効率化などのメリットを得るためには、社内教育の効果をこまめに測定し、その結果に基づいてアプローチを改善していく姿勢が欠かせません。
ここからは、生成AIの社内教育による効果を測定する方法と、継続的に改善していくためのポイントを紹介します。
定期的な理解度テストの実施
定期的に理解度テストを実施すれば、社内教育でどれほど成果が上がっているのかを可視化できます。社内教育の前後などで理解度テストを行い、結果によって改善ポイントを見極めます。
生成AI導入の効果を測定するうえで、定量的な評価指標の採用も有効です。AI導入の前後で、業務時間内における処理件数の増加率やタスク完了までの時間の短縮率などを測定し、比較してみるとよいでしょう。
その他、マーケティング部門でAIを導入したあとのコンバージョン率の変化などを確認する方法もおすすめです。
社内での業務適用事例の共有
生成AIを業務で活用した事例を社内で共有すれば、生成AIの有用性が広く認知され、従業員に受け入れられやすくなります。事例を共有するためにも「社内教育を受けたあとは業務への適用事例の報告を義務とする」といった仕組みを設けるとよいでしょう。
共有した事例に対して各部門でフィードバックを行い、より効率的に業務を遂行できるような体制を整えると効果的です。生成AIの有用性を実務に即した形で確認すれば、研修実施後におけるモチベーションの低下も防ぎやすくなります。
アンケートによる勉強会への満足度調査
生成AIに関する勉強会を開催したあとは、参加者にアンケートを実施するとよいでしょう。参加者の満足度などから勉強会の問題点を把握し、次回の開催時までに内容を改善して臨みます。
同時に、生成AIの急速な進化に追いつくために、勉強会のたびに最新の機能やモデルに関する知識を共有することも大切です。
初めての生成AIはTOMAのAI導入支援がおすすめ
初めて生成AIを導入する際は、社内ルールの策定などに多大な労力がかかります。生成AI活用でのトラブルを防ぐためにも、AI導入支援サービスの利用がおすすめです。
TOMAでは、専門家によるAI導入支援サービスを提供しています。生成AIに関するガイドライン策定のサポートなども行っており、情報漏えいなどのリスク管理にも役立つでしょう。
TOMAのAI導入支援サービスでは、ヒアリングを通して現状を分析し、具体的な運用ルールやプロセスを作成します。ガイドラインの策定後も、従業員向けにトレーニングを実施して社内運用の定着をしっかりとサポートします。
ガイドライン策定だけでなく、GPTs(カスタマイズChatGPT)の導入支援やツール連携支援により、業務効率化をサポートすることが可能です。生成AIに関するリソースが不足している場合には、TOMAのAI導入支援サービスをぜひご活用ください。
まとめ
生成AIは便利な反面、誤情報の出力や著作権の問題といったリスクも抱えているツールです。生成AIを業務に活用する際には、明確な社内ルールを策定したうえで、研修サービスなどを利用して従業員教育を徹底することが大切です。
TOMAにはAIに関する有資格者による根拠・裏づけがあり、IT部門の専門家が在籍しているため、安心してお任せください。TOMAの生成AIサービスにつきましては以下よりご確認できます。
相談は以下、無料相談・お問合せよりお知らせください。