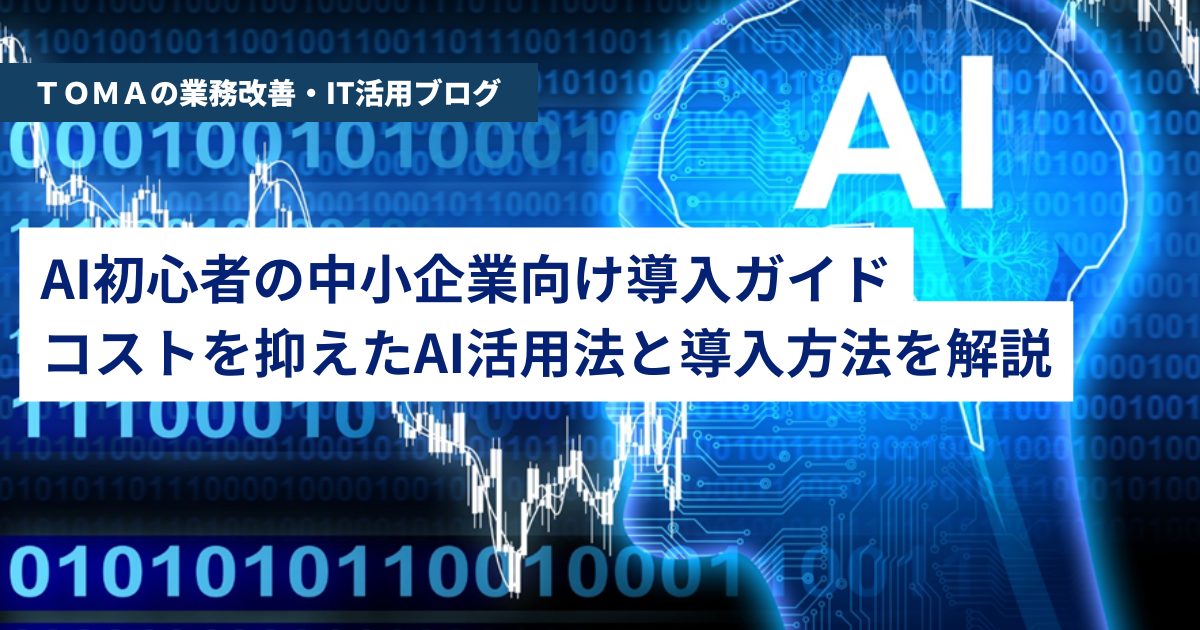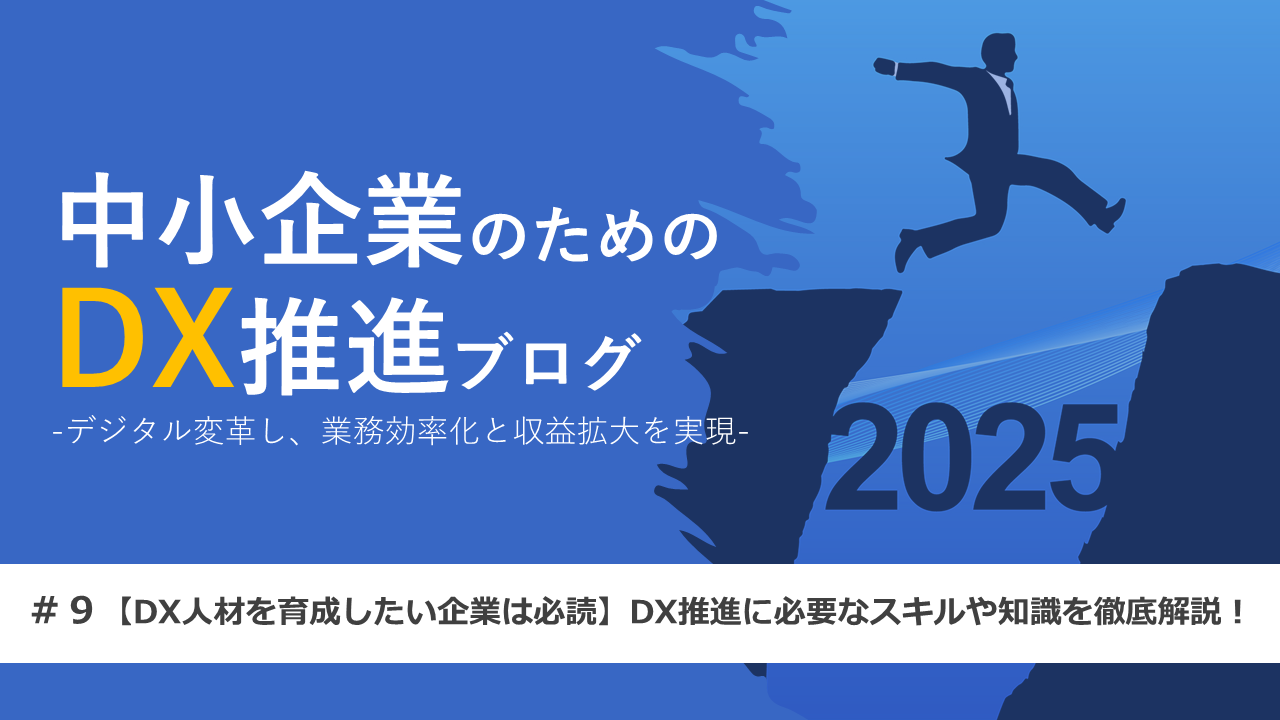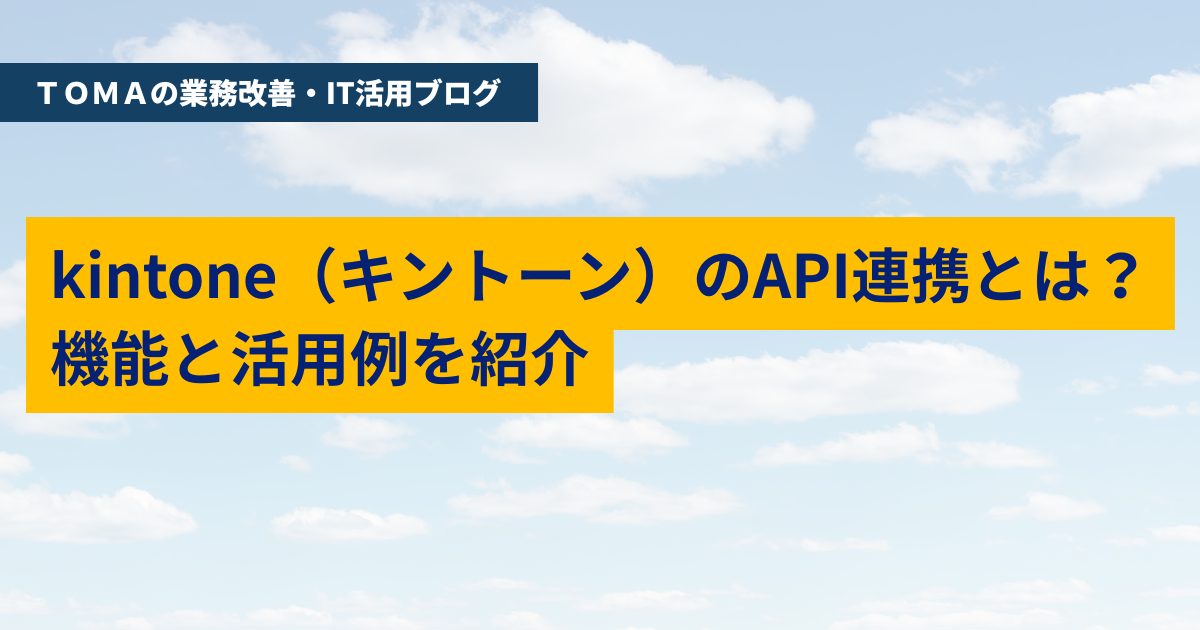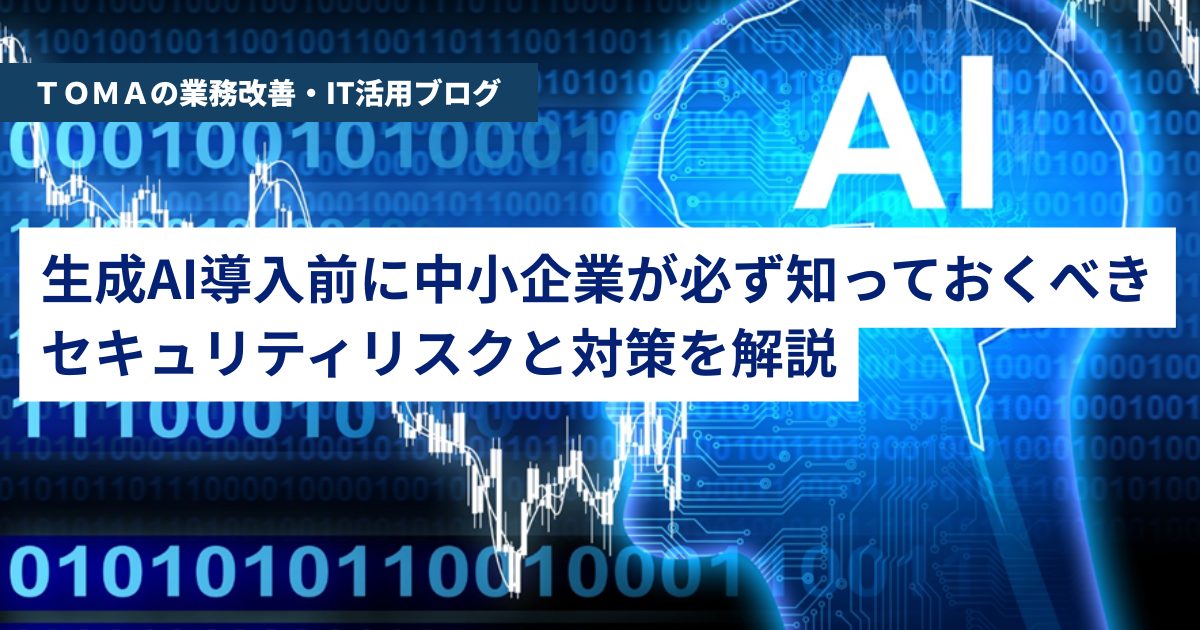生成AIを業務に取り入れたいと思いつつ、「費用がかかりそう」「専門知識がない」といった理由で導入をためらっている方も多いのではないでしょうか。慢性的な人手不足に悩まされる中小企業では、業務の効率化などに貢献する生成AIを積極的に活用することが重要になります。
この記事では、AI初心者の中小企業でも無理なく生成AIを導入できる手順を紹介します。生成AIを導入するメリットや任せられるタスクなどについても解説しているので、何から始めて良いのかわからないという方はぜひ参考にしてください。
目次
なぜ中小企業ほど生成AIの活用が必要なのか

中小企業のAI導入が進まない背景には、技術的なハードルの高さやリソース不足、経営者の認識不足などが考えられます。しかし、人材不足が慢性的な問題となっている中小企業こそ、生成AIの活用が求められている状況です。
生成AIを導入すれば業務効率が向上し、限られたリソースをコア業務に多く割り当てられるようになります。事業のさらなる発展を目指すためにも、中小企業こそ生成AIを活用することをおすすめします。
ここからは、中小企業にこそ生成AIが必要な理由について、さらに掘り下げて解説します。
慢性的な人手不足
中小企業は慢性的な人手不足に悩まされており、このことが企業の成長における足枷となっています。
人手不足を進行させる要素の一つとして挙げられるのが、コロナ禍からの需要回復です。中小企業庁の「2024年版中小企業白書」では、コロナ禍からの需要回復にともない人手不足が深刻な問題となりつつあることが示されています。
さらに、東京商工会議所が2024年に実施した「中小企業の人手不足、賃金・最低賃金に関する調査」においても、65.6%もの中小企業が「人手不足」と回答しています。
少子高齢化の影響による労働力人口の減少も、この状況を悪化させています。企業の成長に必要な労働力を確保するという意味で、中小企業こそ生成AIを活用すべきといえるでしょう。
生産性の向上
生成AIを導入すると生産性が向上し、中小企業は成長がしやすくなります。
生成AIは、業務の自動化やデータの活用によって効率化を実現してくれるツールです。そのため、適切に導入すれば少人数のチームでも効率的に成果を上げられます。
例えば、生成AIを活用したチャットボットによって、顧客対応を24時間体制で自動化できます。また、AIによるデータ分析を活用して、効果的なマーケティング戦略を考案することも可能です。
競争が激化するデジタル社会においては、AIを活用できるかどうかが中小企業の生存戦略における要となるでしょう。
知識の補完
人手不足によって、業務に必要な知識・スキルのある人材の採用は難しくなっています。そこで考えられるのが、従業員の知識・スキル不足をAIでカバーするという手段です。
例えば、Excelの関数やプログラミングなどの専門知識が要求される業務に対して、生成AIを活用できます。
また、従来であれば外国語の知識や経験が必要だった翻訳業務も、生成AIに任せれば簡単に実行が可能です。これによって、海外の企業や顧客との取引も効率的に行えるようになるでしょう。
AIが人間の知識を補完すれば、従業員の経験に左右されずに業務の質を一定水準に保つことが可能です。AIの正しい活用により、人材不足を補いながら業務効率を高められる可能性があります。
生成AIとは?特化型AIと汎用型AIの違い

AIは大きく「特化型」と「汎用型」の2種類に分けられます。生成AIの導入を検討する前に、それぞれの特徴や違いを理解しておくとよいでしょう。
ここからは、特化型AIと汎用型AIの特徴について解説します。
特化型AIとは
特化型AIとは、特定領域のタスクに特化したAIのことです。限定された範囲で高度な処理を行えるため、自動運転や医療診断などの形ですでに実用化されています。その他、画像認識や音声認識、天候予測などのAIシステムがあります。
特定の領域で豊富な専門的知識を有し、問題解決のサポートをする「エキスパートシステム」も特化型AIの一種です。
特化型AIは特定の範囲では高い処理精度を誇る一方、ほかのタスクには応用できないことが難点です。現時点で実用化されているすべてのAIは、この特化型AIに該当します。
汎用型AIとは
汎用型AIとは、処理できるタスクが特化型のように限定されず、幅広い役割をこなせるAIのことです。
人間のように多様な知識領域に対して適応できる点が特徴で、タスクを取り組むにあたって事前に対象分野の大規模なデータ学習を必要としません。自律的に状況を分析し、課題解決に向けて柔軟に対応できます。
汎用型AIはいまだに実現されておらず、多くの組織が研究開発を進めている状況です。現在使われている生成AIでは、身体性をともなう情報収集などの、人間であれば容易に遂行できるタスクにも対応できないため、汎用型AIとはいえません。
汎用型AIが実現すれば、さらにその先の段階であるASI(人工超知能)が誕生する可能性があります。ASIは自律性を持つだけでなく、これまで人間ができなかったことも可能にする存在です。人類に与える影響などを考慮しながら、注意深くASIの研究が進められています。
中小企業が生成AIを導入するメリット

生成AIの導入によって、企業は業務フローの改善や顧客満足度の向上といったメリットを得られます。ここからは、中小企業が生成AIの導入で得られるメリットを紹介します。
人手不足の解消
生成AIは、データ分析やタスクの自動化で業務効率の向上に貢献してくれるツールです。
中小企業が生成AIを導入すれば生産性が向上し、従来よりも効率的に業務をこなせるようになります。具体的な活用方法には、チャットボットによる自動の顧客対応や業務プロセスの効率化などが挙げられます。
また、人間の場合は一人ひとりの経験やスキル、知識などによって、担当できる業務が変わります。体調が悪化して、普段どおりの能力を発揮できなくなる場合もあるでしょう。
一方、生成AIは人間とは異なり、業務の質にばらつきが生じることがありません。一貫して効率的に業務を遂行できるため、スケジュールも立てやすくなります。
慢性的な人手不足に悩んでいる場合、生成AIの導入によって解決できる可能性が高いでしょう。
顧客満足度の向上
生成AIは膨大なデータを分析したり、その結果から将来的な動向を予測したりする能力に長けています。そのため、生成AIを業務に取り入れれば、ビッグデータの分析を通して顧客ニーズを正確に把握しやすくなります。
市場の動向や顧客ニーズを考慮した戦略を立案すれば、顧客満足度の向上が図れることもメリットの一つです。市場のニーズから求められている製品やサービスを導き出し、適切な事業戦略を練れば、ブランド価値を高めることにもつながります。
AIチャットボットによるスムーズな顧客対応など、直接的に顧客満足度の向上に貢献してくれる側面もあります。また、製造業においてAIによる検品システムを導入し、不良品の販売を防ぐことも顧客満足度の維持につながるでしょう。
コストの削減
生成AIを導入して業務の自動化を進めれば、従来は人手に頼っていた単純作業をAIに任せられるようになります。従業員の労働時間を短縮できるため、残業手当などの出費が発生しにくくなります。
その結果として、人件費などのコストを大幅に削減することが可能です。浮いた資金を新規事業などに投資すれば、企業を効率的に成長させられます。
また、生成AIのデータ分析で企業の財務状況などを正確に把握すれば、社会的な信用度が高まって金融機関からの資金調達も容易になります。コストの削減と資金調達の改善で、生成AIは事業拡大にも大きく貢献してくれるでしょう。
競争力の向上
生成AIは大量データの分析能力に優れており、膨大なデータを短時間で処理することによって企業に有益な情報を提示してくれます。
例えば、顧客セグメンテーションに生成AIを活用すれば、購買データなどから効率的に顧客のカテゴライズが可能です。細かくパーソナライズされたデータをもとに、訴求力の高いマーケティング活動が可能になるでしょう。生成AIの活用で、経営戦略やマーケティングの方向性を明確に定めやすくなります。
また、生成AIの導入が新しいビジネスモデルの開発につながる場合もあります。AIの高度なデータ分析能力や予測能力が、売上の向上、ひいては市場における競争力の向上につながるでしょう。
ヒューマンエラーの防止
生成AIは人間と違って気分のムラなどがなく、データ入力をはじめとするタスクを正確にこなせます。生成AIの導入で業務の正確性が高まり、ミスに対するリカバリーなどの余計な手間が省けるでしょう。
また、画像認識機能などにより異常を検知し、人間のミスを発見するうえでも生成AIは役に立ちます。
例えば、金融機関の取引データを生成AIにチェックさせた場合、不正取引などを迅速に感知して、自社や顧客の資産を守れるでしょう。医療や車の運転など、人為的なミスが致命的な結果を招きかねないシーンでも、AIの正確性に大きな期待が寄せられています。
中小企業ができる生成AIの活用法

生成AIには得手不得手があるため、任せられるタスクの種類を把握しておくことが重要です。ここからは、中小企業の効果的なAIの活用法を紹介します。
アイデア出し(ブレインストーミング)
生成AIは、優れたアイデアを出すための「壁打ち相手」になります。新商品のコンセプトやマーケティング施策、新しいサービスのキャッチコピーなどについて、自分だけでは思いつかないような多様な視点からの提案を行ってくれます。
従来なら複数人で集まって行うべきアイデア出しの作業を、好きなときに一人で始められる点は大きな利点といえるでしょう。企画に行き詰まった際などに生成AIを活用してブレインストーミングを行えば、業務の質とスピードを向上させられます。
テキスト・メール作成
文書作成は生成AIが得意とするタスクの一つです。生成AIの導入で会議での議事録やビジネスメールの作成などを自動化でき、業務効率を高められます。また、膨大なテキストデータの内容を要約することも得意です。
生成AIはインターネット上に存在する膨大なデータを学習しており、多言語間での翻訳も容易にこなせます。生成AIによるテキスト作成を活用する際は、目的や制約条件、出力すべき情報などを明確に指示すると成果物の精度を高められます。
データ入力・事務作業
従来は人間が行っていたデータ入力作業も、生成AIに任せれば効率的に進められます。AIの文字認識技術(OCR)を活用すれば、手書き書類のデジタル化なども可能です。
AI-OCRは従来のOCRに比べて文字認識の精度が格段に高くなっており、手書きの文字も高い精度で読み取れます。郵便物や銀行窓口の書類など、手書きの帳票もスムーズにデジタル化でき、業務の効率化に貢献してくれるでしょう。
会計処理でも、請求書などのデータを自動的に入力してくれるため、ヒューマンエラーを防いで正確に作業できます。その他、経費精算やスケジュール管理、契約書類のチェックといった、さまざまなバックオフィス業務の自動化・効率化が可能です。
生成AIの導入で、あらゆる企業に共通するバックオフィス業務を効率的にこなせるようになるでしょう。
情報収集
生成AIを使えば、インターネット上の膨大な量の情報から必要なデータを効率的に集めてもらえます。最新のWebサイトから情報を取得したり、リサーチした情報をわかりやすくまとめたりすることも可能です。その他、特定のWebサイトを示して、その内容を要約してもらうといった使い方もできます。
また「Deep Research(ディープリサーチ)」という機能では、ユーザーの質問意図を深く理解し、関連がある数十から数百の情報を参照して詳細なリポートを提供してくれます。
効率的なリサーチ・分析にも、生成AIは不可欠なツールとなりつつある状況です。
画像・デザイン作成
生成AIの活用によって、大雑把なイメージから画像やデザインを作成することも可能です。
人に任せる場合との大きな違いとしては、複数のデザインを低コストで作成できることが挙げられます。ニーズに沿った画像やデザインを生成AIに複数作成してもらい、そのなかからイメージに合ったものを採用できます。
従来は外部の企業へ委託していたようなデザイン業務も、生成AIの導入で内製化できる可能性があるでしょう。
顧客管理・マーケティング
生成AIを導入すれば、顧客データの管理・分析も効率的に行えるようになります。例えば、生成AIの分析能力を活用した顧客セグメンテーションによって、ターゲットに応じて適切なマーケティング戦略を展開可能です。
また、顧客対応の自動化や商品のレコメンド、市場動向の分析などにも生成AIを活用できます。適切な顧客管理とマーケティングが事業の成長に役立つうえに、顧客満足度の向上にも貢献してくれるでしょう。
採用・人事管理
採用の場面では、生成AIに履歴書などのデータ分析を任せることで、応募者の適性を効率的に評価できます。また、過去の採用成功者のデータを分析すれば、適切な人材を選定しやすくなるでしょう。
AIチャットボットなどを利用して採用面接を一部自動化し、選考過程を効率化できます。その他、職務適性診断や従業員エンゲージメント分析、離職予測などにも生成AIを活用できます。
生成AIの導入によって、優秀な人材を選定と適切な管理が可能になります。
中小企業が低コストで生成AIを導入する方法

潤沢な予算がある大企業が早々にAIを導入する一方で、中小企業のAI導入はあまり進んでいません。業務効率化を実現したい中小企業は、低コストでAIを導入する方法を押さえておくことが大切です。
ここでは、中小企業がなるべくコストを抑えて生成AIを導入する際の流れを紹介します。
1.自社の課題を洗い出す
最初に、生成AIの導入により解決すべき自社の課題を明確にすることが必要です。業務課題を明確にすれば、どのような形でAIを活用できるのかをイメージしやすくなります。
課題の具体例としては、「顧客の問い合わせに対応できていない」「生産プロセスの無駄が多い」といったことが考えられます。不適切な在庫管理によって、在庫切れや在庫過多が生じているケースもあるでしょう。
課題を抽出する際には、経営目標を明確にしたうえで現場へのヒアリングなどを行います。また、業務プロセスを見える化し、業務を細かくカテゴライズすることも重要です。
これにより、システム化されているプロセスとそうでないプロセスを区別できます。経営者と現場担当者の両方の視点で、自社が抱えている課題を洗い出しましょう。
2.課題となっている業務をリストアップする
次に、1のステップで把握した課題をリストアップし、生成AIの導入で解決できるかどうかを検討します。例えば、問い合わせに対応しきれていない場合、AIチャットボットの導入で状況が改善する可能性があります。
顧客からの問い合わせ内容を生成AIで分析し、用意したテンプレートを使って返信することも可能です。課題解決に取り組む際は、具体的な目標も設定してAI導入による成果を管理できるようにしておきましょう。
3.無料で始められるAIを探す
生成AIには多くの種類があり、その利用料はサービスごとに異なります。実際に使ってみなければ自社に合っているかがわからないため、まずは無料のサービスやトライアルから始められるサービスを利用するのがおすすめです。
無料で利用できる生成AIの代表例としては「ChatGPT」や「Gemini」などが挙げられます。また、画像生成AIの「Stable Diffusion」も無料で利用可能です。いずれもプランをアップグレードすれば、より高機能なAIを使えるようになります。
4.スモールスタートで段階的に導入する
生成AIは業務効率化やコスト削減に役立つ便利なツールですが、リスクがないわけではありません。例えば、AIの学習機能によって、入力した情報が外部に漏れるおそれがあります。
また、AIを活用して何らかのトラブルが起こった場合、責任の所在が不明確になることもデメリットの一つです。
AI活用で想定されるリスクやトラブルを事前に把握し、業務範囲を限定して段階的に導入するのが賢明といえます。
初めてのAI導入なら導入支援を受けるのがおすすめ
多くの中小企業は、AIの導入に高いハードルを感じています。スムーズにAIを導入して業務効率化を実現するためにも、AI導入支援サービスの利用がおすすめです。専門家の視点から状況を分析し、AI導入に関して最適な提案をしてくれるでしょう。
TOMAでは、初心者向けのAI研修やガイドラインの策定、ツールの導入などをトータルサポートしています。TOMAのAI導入プロジェクトは、以下のステップで進められます。
- AIリテラシー向上支援
- ガイドライン策定支援
- ツール導入支援
- 継続的な運用・改善支援
最初にAI導入・活用研修を行い、AIを実務に活かすために必要な知識や使い方を習得します。ChatGPTなどを使いながら学ぶハンズオン形式で、研修内容はニーズに合わせてカスタマイズが可能です。
次に、ヒアリングや現状分析を通して、ガイドラインの策定をサポートします。さらに、AIによるツール連携や業務プロセス自動化の支援を行い、継続的な運用・改善のサポートを提供します。
「社内にAIを使いこなせる人材がいない」「AI運用のリスク管理が不安」「AI活用に向けたデータの整理方法がわからない」など、AIの導入で悩んでいる場合にはぜひご相談ください。
まとめ
人手不足の解消や顧客満足度の向上などに役立つ生成AIは、中小企業こそ活用すべきツールです。生成AIを導入する際には、課題の洗い出しやリストアップ、段階的な導入といったステップを踏むことが大切です。必要に応じてAI導入支援サービスを利用しながら、事業をさらに発展させる足がかりにするとよいでしょう。
TOMAのAI導入支援サービスは、AIに関する有資格者による根拠・裏づけがあります。IT部門の専門家も在籍しているため、安心してお任せください。
ご相談は以下、無料相談・お問合せよりご連絡ください。