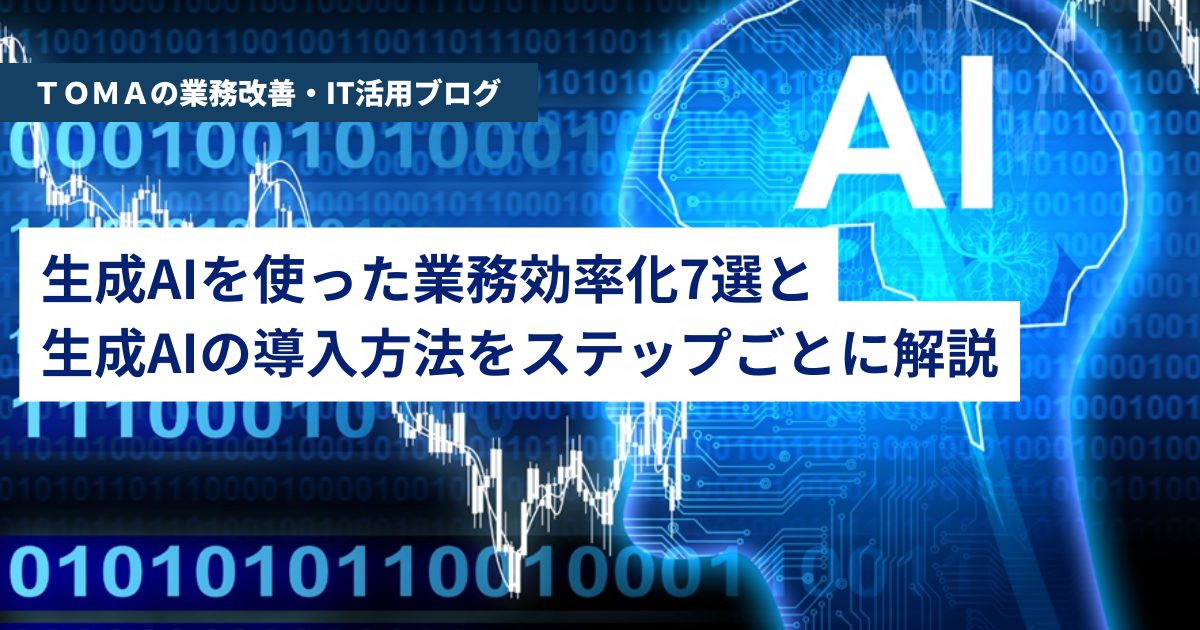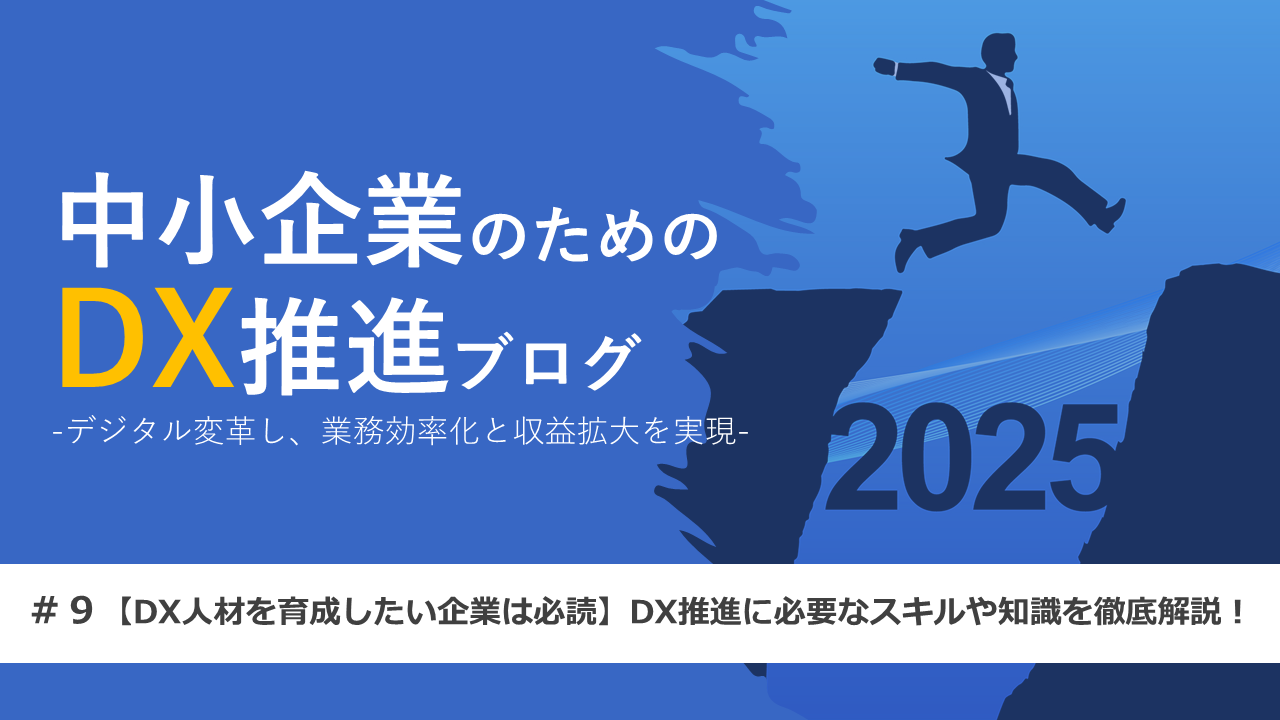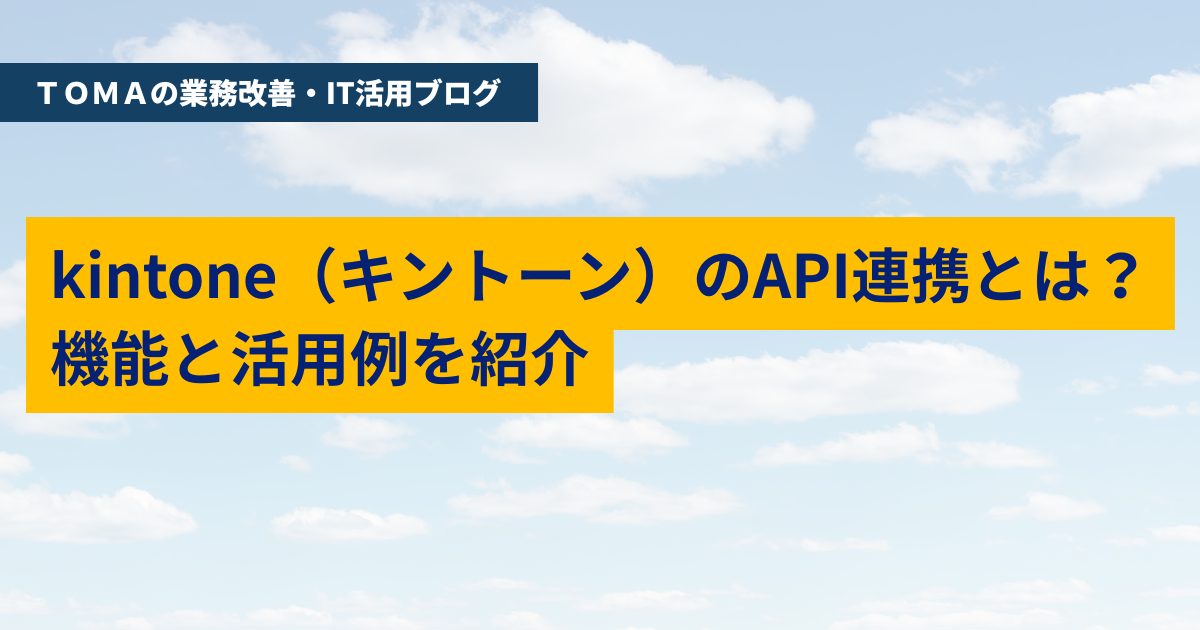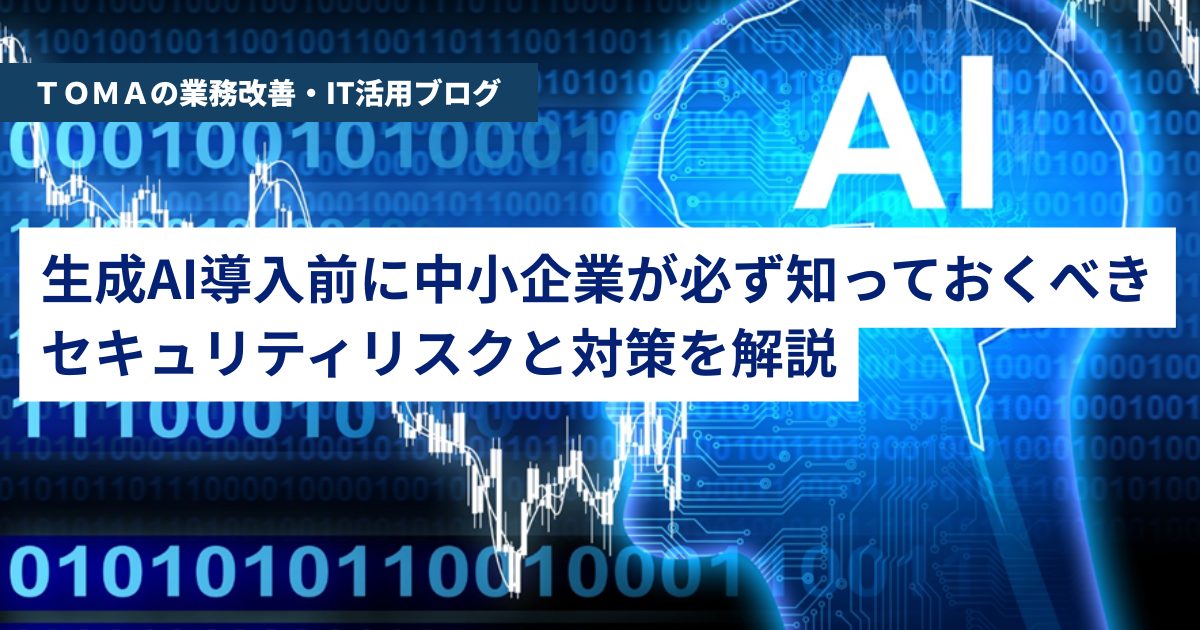生成AIの活用は、業務の効率化だけでなく企業が直面するさまざまな課題の解決にも有効です。
とはいえ、生成AIの導入を検討している企業担当者のなかには、どう活用すれば業務効率化につながるのか、どの生成AIを導入すればいいのかがわからないでいる方も多いでしょう。
本記事では、生成AIを使った業務効率化の例やおすすめの生成AI、導入方法などを解説します。生成AIの業務活用や導入のイメージをつかむために、ぜひご覧ください。
目次
生成AIによる業務効率化が重要といわれている理由

生成AIによる業務効率化が重要視されている理由には、生成AIが社会のさまざまな課題に対応し得る可能性を秘めていることが挙げられます。
まずは、現代社会においてどのような課題があるのかを解説します。代表的なものを取り上げているので、一つずつ見てきましょう。
多くの企業で人材不足が深刻化
人材不足は、現代の日本企業が直面する重大な課題の一つです。生成AIによる業務効率化は、この状況を打開する有効な手段と考えられています。
厚生労働省の資料をもとに、ここ数十年の日本企業を取り巻く環境を見ると、1970年代前半、1980年代後半から1990年代前半、そして2010年代以降という3期間で人手不足が顕著になっています。
特に2010年代以降は、人手不足を感じる企業の割合が過去の2期間よりも増し、その期間も長期にわたっていることが明らかになりました。
参照:厚生労働省「令和6年版労働経済の分析―人手不足への対応―〔概要〕」
こうした背景から、不足する人材の穴埋めを行う現実的な解決策として、生成AIを活用した定型業務の自動化が注目されています。生成AIによる業務の効率化は、業務の継続性や生産性の維持も期待できます。
少子高齢化による生産年齢人口の減少
日本企業の人材不足の要因として挙げられるのは、少子高齢化による生産年齢人口(生産活動の中心となる15~64歳の人口)の減少です。
日本国内の総人口は2008年に1億2,808万人を記録して以降、減少傾向にあります。それにともなって生産年齢人口も減少し続けており、今後もこの傾向が続くことが予測されています。
生産年齢人口とは異なり、労働力人口(15歳以上の人口のうち、就業者と完全失業者の総数)は過去10年間でほぼ横ばいとなっている状態です。
これには、女性や65歳以上の高齢者の労働力人口が増加していることが影響しています。しかし、長期的に見れば少子高齢化の影響で労働力人口も減少し、人手不足が深刻化することが想定されます。
参照:国土交通省「国土交通白書2024第1章人口減少と国土交通行政第1節本格化する少子高齢化・人口減少における課題」
このような状況下で、生成AIを活用した業務の効率化は、労働力不足を補う有効な手段となるでしょう。
残業問題の改善
厚生労働省の「毎月勤労統計調査令和6年5月分結果速報」によれば、全産業の平均所定外労働時間数は9.9時間となっています。一方、民間のアンケート調査では、2024年4~6月の平均残業時間は21.0時間という結果でした。
参照:
厚生労働省「毎月勤労統計調査令和6年5月分結果速報」
転職サービスdoda「平均残業時間の実態調査残業が少ない・多い仕事は?」
調査方法や対象によって差はありますが、いずれも依然として残業が常態化している現状が浮き彫りになっています。近年は働き方改革の推進や労働基準法の改正などにより、残業時間は減少傾向にありますが、その分業務の効率性が求められるようになっています。
したがって、生成AIの活用で定型業務やデータ処理を自動化するなどして、労働時間の短縮やワークライフバランスの向上を図ることが喫緊の課題となっています。
競争優位性の確保
生成AI市場は急速に成長しており、ビジネスにおける生成AIの活用は一般的になりつつあります。今後は、生成AIをいかに効果的に活用しているかで他社との差別化を図り、企業の競争優位性を高めるようになると考えられています。
従来、膨大な時間と労力を要していたデータ処理やレポート作成などの業務も、生成AIの活用で迅速かつ正確に処理できるようになりました。さらに活用の場を広げれば、業務プロセス全体の改善や、経営判断・意思決定の速度アップにもつながります。
業務の効率化や企業成長の加速が期待できる生成AIの活用は、企業経営において不可欠な要素となるでしょう。
生成AIで行える業務の効率化7選

生成AIの活用で実現できる、代表的な7つの業務効率化の方法をご紹介します。
1.定型業務の自動化
定型業務の自動化は生成AIが得意とする分野であり、業務効率化の第一歩としてさまざまな企業で実践されています。契約書や議事録、報告書など、ビジネスシーンで頻繁に発生する定型的な文書の作成は、生成AIの活用で大幅な時間短縮が可能です。
例えば、必要事項を入力するだけで、生成AIが過去の事例やテンプレートを参考にしながら自動的に文章を生成します。あとは、人の手による最終確認や微修正を加えるのみで書類の完成です。
生成AIによる定型業務の自動化は、担当者の負担が軽減されるだけでなく、ミスの防止や品質の向上も期待できます。
2.チャットボットによる顧客対応の効率化
生成AI搭載のチャットボットを活用すれば、カスタマーサポート業務におけるオペレーターの負担が大きく軽減されます。
AIチャットボットは顧客からの問い合わせに対して、事前に学習した過去の事例などの情報をもとに、自動で一次回答を行います。必要に応じて、根拠となる情報を提示することも可能です。
AIチャットボットの活用により、問い合わせ対応の迅速化やオペレーターのリソース最適化、24時間体制でのサポートなどができるようになります。
3.生成AIによるデータ分析
従来のデータ分析方法と比較すると、生成AIは大量のデータを高速かつ効率的に処理することが可能です。
データを読み込ませてプロンプト(生成AIに対する命令文)で指示するだけで、AIが自動的に分析を進めていき、担当者が手作業で行うよりも短い時間で結果を提示してくれます。
人件費の削減や作業時間の短縮が期待できるだけでなく、データの可視化やレポート作成も自動化できるため、経営層への情報提供がスムーズになる点も大きな特徴です。生成AIによるデータ分析は、市場動向の把握や業務改善の迅速化に効果を発揮します。
4.生成AIによる名刺や資料のデジタル化
名刺や紙の資料を効率的にデジタル化するためには、高精度なOCR(手書きの文字や画像データを抽出し、デジタルデータに変換する仕組み)技術が不可欠です。生成AIとOCRを組み合わせることで、スキャンした名刺や資料の情報をより正確にデータとして抽出できるようになります。
さらに、オペレーターによる確認や補正と組み合わせれば、完璧に近い精度でのデジタル化が可能です。名刺や資料をデジタル化することで情報の一元管理や検索がしやすくなり、社内の情報共有や顧客管理も効率化されます。
また、デジタル化されたデータはCRM(顧客関係管理システム)やSFA(営業支援システム)などとも連携しやすく、業務の自動化や効率化に大きく影響します。
5.生成AIを活用した在庫管理
在庫管理業務で生成AIを導入すると、需要予測の精度向上と在庫数の最適化が実現できます。
従来の在庫管理システムでは、過去の販売データやユーザーの行動データなどをもとに需要予測を行っていました。
一方、生成AIを活用すると、従来のシステムで使用していた要素に加え、天候やイベント、SNSの投稿内容、経済指標など、多様なデータを組み合わせて分析できるようになります。
生成AIの活用で需要予測が精密になれば、過剰在庫を抱えたり、欠品したりするリスクを低減させることも可能です。これらの効果により、業務の効率化だけでなく、コストの削減や顧客満足度の向上も期待できるでしょう。
6.音声認識による議事録や文字起こし
生成AIの音声認識技術を活用すれば、会議やインタビューなどの音声データを自動的にテキスト化できます。さらに、要点を抽出して議事録を作成することも可能です。複数話者の識別や専門用語の認識に対応できるものもあり、幅広いシーンで活用できます。
生成AIによる議事録作成の効率化が進むと、担当者の負担は大きく軽減されます。また、テキスト化されたデータは共有や検索がしやすいため、社内の情報管理の効率化にもつながります。
7.言語処理によるメールの作成
生成AIを活用すれば、社内外のコミュニケーションで適切な文面や表現を考える時間を大幅に削減できます。既存の文書の要約や翻訳、トーン変更なども瞬時に行えるため、グローバルコミュニケーションも効率化することが可能です。
生成AIに言語処理を任せることで、担当者の業務負担が大きく軽減されるだけでなく、迅速かつ正確な情報発信ができるようになります。生成AIは、業務の効率化だけでなく、企業のグローバル展開や多様化にも対応できる強力なツールといえます。
業務効率化のために導入したいおすすめ生成AI

導入をおすすめしたい生成AIについて、用途別にご紹介します。活用する生成AIを検討する際の参考としてください。
資料作成やデータ分析などの業務をサポートできる生成AI
初めて生成AIを業務に活用する場合は、以下にご紹介するものから使い始めることをおすすめします。どの生成AIも広く知られており、さまざまな業務を高水準でサポートしてくれるものばかりです。
ChatGPT
ChatGPTはOpenAI社が開発した対話型AIで、複数の指示を含む応用的なプロンプトにも柔軟に対応できる点が特徴です。テキスト情報だけでなく、画像や音声なども入力データとして処理できるマルチモーダルに対応しています。
プロンプトの工夫次第でより高度なタスクにも対応できるため、業務の自動化や効率化だけでなく、幅広い業務シーンでの活用が期待できます。
Claude
Claudeは、OpenAI社の元エンジニアたちが設立したAnthropic社によって開発された対話型AIです。特にプログラミングコードの生成・解説、文章作成能力に優れており、AIを活用するユーザーから高い評価を得ています。
人間らしい自然な文章生成が可能であり、専門的な内容にも対応できるため、複雑な技術文書の作成や報告書、契約書などのビジネス文書の作成に適しています。
Gemini
GeminiはGoogle社が開発した生成AIで、テキスト・画像・音声といったさまざまな種類のデータを同時に扱えるマルチモーダルに対応しています。識別が困難な知識やパターンを膨大なデータのなかからでも発見できる、高い推論能力を有している点が特徴です。
また、複数のファイルをアップロードしてデータ分析できるため、複雑なデータ分析やレポート作成、市場動向の可視化など、高度な業務支援が期待できます。データドリブンな意思決定を目指す企業にとって、非常に有用なツールです。
NotebookLM
NotebookLMはGoogle社が提供する生成AIで、ユーザーがアップロードした資料をもとに回答します。ユーザー指定の情報源から回答するため、「ハルシネーション(AIが事実と異なる内容を生成する現象)」が起こりにくい点が特徴です。
GoogleドキュメントやGoogleスライドを直接読み込めるため、既存の業務資料を活用しながら、シームレスに情報検索や要約、質疑応答を行えます。社内ナレッジの整理や、資料をもとにした正確な情報提供が必要な場面で特に効果を発揮します。
画像の作成業務をサポートできる生成AI
画像生成に優れた生成AIを活用すれば、営業資料やWebサイトで使用するイメージ画像の作成を効率化できます。画像生成の分野は近年急速に進化し、「Stable Diffusion」や「Adobe Firefly」のように、画像生成に特化したAIサービスも存在します。
前述のChatGPTやGeminiなどの多機能な生成AIでも、テキスト入力から画像を生成することは可能です。一方で、画像生成に特化したAIサービスでは、詳細な条件の指定をしてより高精度な画像を生成できる、と考えるとよいでしょう。
ただし、画像生成の際には、生成された画像の著作権や利用規約に注意する必要があります。商用利用の可否や二次利用の可否など、各サービスの規約を事前に確認し、適切に運用することが求められます。
音声データの生成で業務をサポートできる生成AI
テキストの読み上げが行える音声データの生成AIは、コールセンター業務やナビゲーションシステムなど、さまざまなシーンで活用が進んでいます。ここでは、代表的な2つの生成AIについて見ていきましょう。
VALL-E
VALL-Eは、Microsoft社が開発した音声合成AIモデルです。既存の音声圧縮技術や膨大なデータセットを活用すれば、短時間の音声サンプルからでも対象者の声を忠実に再現できます。
VALL-Eでは、わずか3秒程度の音声データをもとに、対象者の声質や話し方に極めて近い発話の生成が可能です。さらに、感情表現や眠たげな声調など、細かなニュアンスの調整も可能で、ナレーションやアナウンス、コールセンターの音声案内など、幅広い用途での活用が期待されています。
Amazon Polly
Amazon PollyはAmazon社が提供する音声合成サービスで、音声アシスタントのAlexaにも技術が活用されています。深層学習テクノロジーを活用して高品質な音声を生成しており、日本語を含む世界各国の言語に対応している点が強みです。
Amazon Pollyは、テキストを入力するだけで自然な抑揚や発音の音声データを生成できます。そのため、ナレーションや案内放送、eラーニング教材の音声化など、多様な業務シーンで利用されています。
複数の生成AIを使える「統合型プラットフォーム」も登場
ChatGPTやGeminiなど多様な生成AIを個別に契約・運用するのは、コストや管理の手間を考えるとあまり効率的ではありません。こうした課題を解決するため、複数の生成AIを1つのプラットフォーム上で利用できるサービスがあります。
1つのサービスを契約するだけで、文章生成や画像生成、データ分析など、業務内容に合った生成AIを選択して利用できるものが統合型プラットフォームです。例えば、企業で統合型プラットフォームのサービスを1つ契約し、部署ごとに異なる生成AIを活用する、ということが可能になります。
統合型プラットフォームを利用するメリットは、契約や管理を一元化できる点です。統合型プラットフォームを利用すれば、AIの導入や運用に関する負担を軽減しつつ、業務の効率化や生産性の向上を図れます。
【業務効率化の実現】自社で生成AIを導入するためのステップ

生成AIの導入は、段階的に進めることで失敗のリスクを減らし、業務効率化の効果を最大化できます。ここでは、企業が生成AIを導入するための7つのステップについて解説します。
STEP1.プロジェクトの責任者を決める
最初に、導入目的の設定や投資対効果を意識した意思決定、関係者間の調整などを担うプロジェクトの責任者「AI推進リーダー」を定めましょう。責任者が明確になるとプロジェクトの方向性が定まり、部門横断的な連携もスムーズに進みます。
特に中小企業では、経営層と現場の橋渡し役となる人材の存在が、導入の成否を左右します。
STEP2.課題となっている業務をリストアップ
生成AIの導入効果を最大化するためには、現状の業務プロセスを可視化し、AIで解決すべき課題を具体的に洗い出すことが不可欠です。業務フロー図の作成や、時間・労力がかかる作業のリストアップに取り組みましょう。
「どの業務を効率化したいか」「従業員のどの負担を軽減したいか」といった観点から、課題を特定します。この段階では幅広く候補を挙げ、次に優先順位を付けるというプロセスにすることで、そのあとのAI選定や効果測定の精度向上につながります。
STEP3.生成AIを導入することで目指すべき目標を決める
続いては、生成AIの導入で実現させたい、具体的かつ定量可能なKPI(重要業績評価指標)を設定します。
例えば、「提案資料の作成時間を30%短縮する」「問い合わせ対応件数を月100件増加させる」などと数値目標を定めることで、効果の可視化や関係者との意思疎通が容易になります。
目標が曖昧だと、導入後の効果検証が困難となり、プロジェクトの継続性にも影響をおよぼしかねません。KPIは業務プロセスに沿って設計し、技術面とビジネス面の両方から評価することが推奨されます。
STEP4.導入する生成AIを決める
課題と目標が明確になったら、自社に合った生成AIツールを選定します。このとき、業務で利用するクラウドサービスやパッケージソフトとのデータ連携、セキュリティ要件なども踏まえて判断することが重要です。
機能・精度・使いやすさ・サポート体制・コストなどを総合的に比較し、課題と目的に合った最適なツールを選定しましょう。自社の要件に合ったツールが見つからなかった場合は、自社開発や外部委託によるシステム構築も検討する必要があります。
STEP5.生成AIの導入・設定を行う
導入・設定段階では、データの準備や既存システムとの連携、従業員向けの教育・研修、運用ルールの策定などを行います。データの質や量が生成AIの性能に直結するため、事前のデータ整備も欠かせません。
また、システム連携のためのAPI(プログラムやアプリケーションなどをつなぐ技術)設計や、AI利用時のガイドライン策定も進めます。導入初期は小規模な範囲から始め、効果を確認しながら段階的に拡大することで、リスクやコストを抑えられます。
STEP6.生成AIの試験運用を行う
全社展開の前に、一部の部署や業務プロセスで試験運用を実施し、効果や課題を検証します。試験運用では、設定したKPIに基づく効果測定や、ユーザーからのフィードバック収集を行い、本格導入前に改善点を洗い出しましょう。
この段階で見つかった課題への対策を講じることで、全社展開でのトラブルを未然に防げます。試験運用の実施は、社内のAI活用に対する信頼性を高めるうえでも重要です。
STEP7.導入後の効果測定、社内への浸透
本格導入後は、事前に設定したKPIの達成状況の定点観測や、アンケートによる満足度調査、生成AIの品質評価などを継続的に実施します。成功事例を社内で積極的に共有し、横展開を図ることで、組織全体のAI活用レベルを高められます。
生成AIを社内に浸透させ、持続的な業務効率化を実現させるためには、効果測定と改善のサイクルを回し続けることが欠かせません。
TOMAのAI活用サービスの事例紹介
TOMAの「AI導入支援サービス」は、AI活用の環境づくりを専門家が支援するサービスで、教育から導入・運用までを段階的に支援します。ここでは、サービスの概要を簡潔にご紹介します。
AI導入・活用研修
AI導入・活用研修は、自分でChatGPTを使用しながら学ぶハンズオン形式です。AIの基礎や仕組み、どのような業務に活用できるのかといった基本的な内容を学んでから、実際にプロンプトを設計していきます。
研修では、AIを活用した業務効率化の具体的な活用方法や、自社業務への応用方法も学べます。受講者は、研修を通じてAIの可能性を理解し、現場での実践的な活用スキルを身に付けることが可能です。
ChatGPT運用ガイドライン策定支援
生成AIの活用が進む一方で、情報漏洩やコンプライアンス違反といったリスクへの対応も重要です。TOMAのAI導入支援サービスでは、ChatGPTなどの生成AIを、社内で安全かつ効果的に運用するためのガイドライン策定も支援します。
ガイドライン策定を通じて、生成AI活用のメリットを最大限に活かしつつ、リスクを最小化する体制の構築が可能です。また、ガイドライン策定後の社員向けトレーニングもサポートします。
生成AI活用導入支援
TOMAでは、カスタマイズChatGPT(GPTs)による業務効率化を支援します。
既存システムとのAPI連携、データ管理、コミュニケーションツールとの連携を通じて、社内環境に最適なカスタマイズを実現します。これにより、ChatGPTのポテンシャルを最大限に引き出します。
まとめ
生成AIの活用は、業務効率化だけでなく、企業が直面するさまざまな課題の解決にも役立ちます。そのため、段階的な導入計画と現場の声を反映した運用が不可欠です。
効果的なAI活用を検討されている場合は、TOMAのAI導入支援サービスをご検討ください。このサービスでは、生成AIの活用を企業の方とともに考え、作り上げていく伴走型の支援を提供します。
また、業務全体を見据えた最適な提案ができることも強みです。AIに関する専門家が在籍しているため、根拠に基づいた安心のサポートが可能です。AI導入による業務革新をお考えの際は、ぜひTOMAにご相談ください。
また、生成AIの導入に関してご相談も受け付けております。以下の無料相談・お問合せよりご連絡ください。