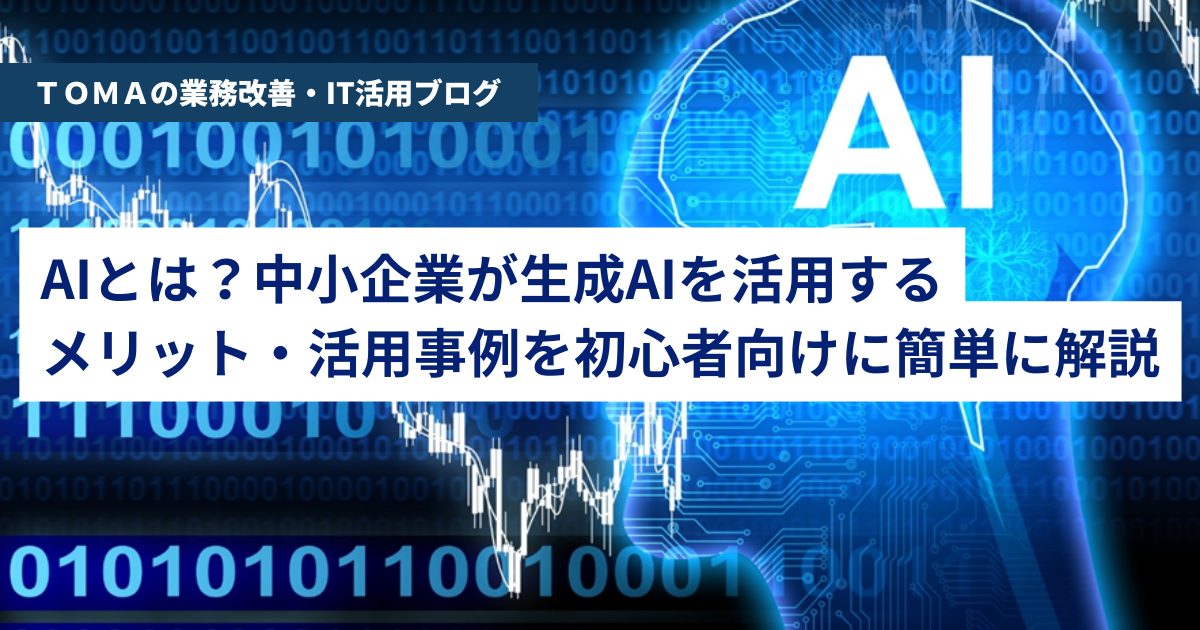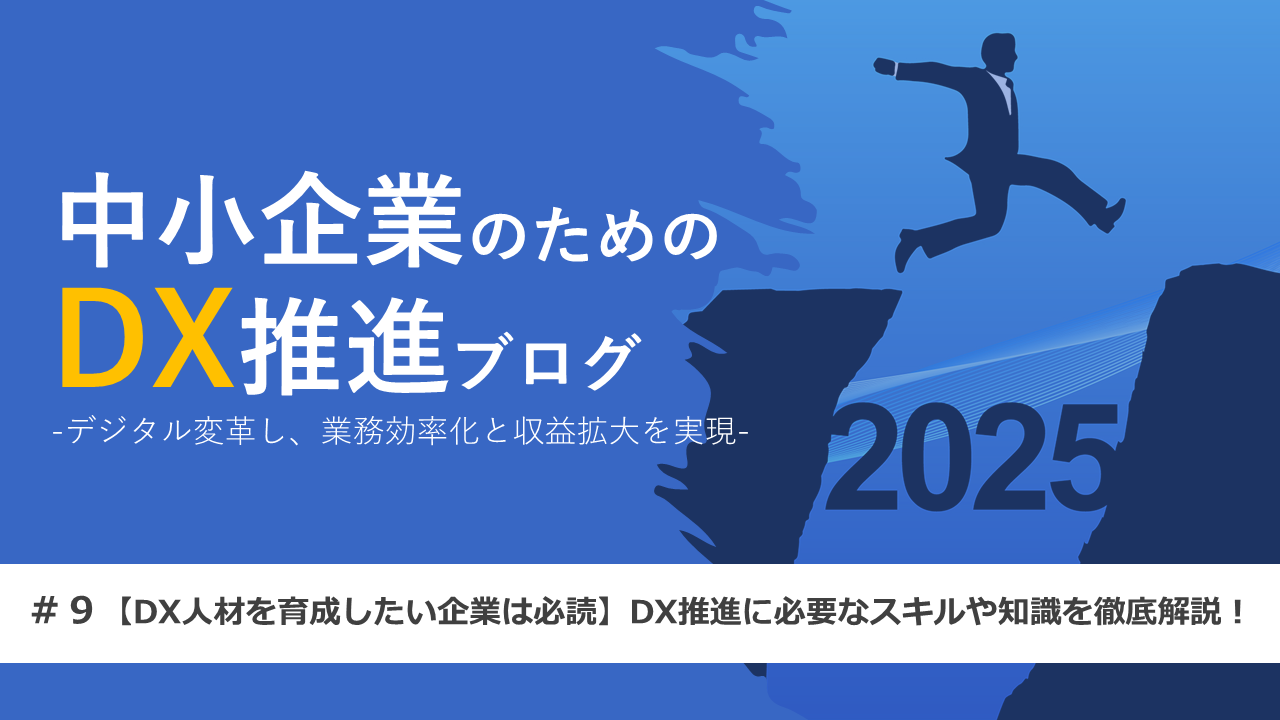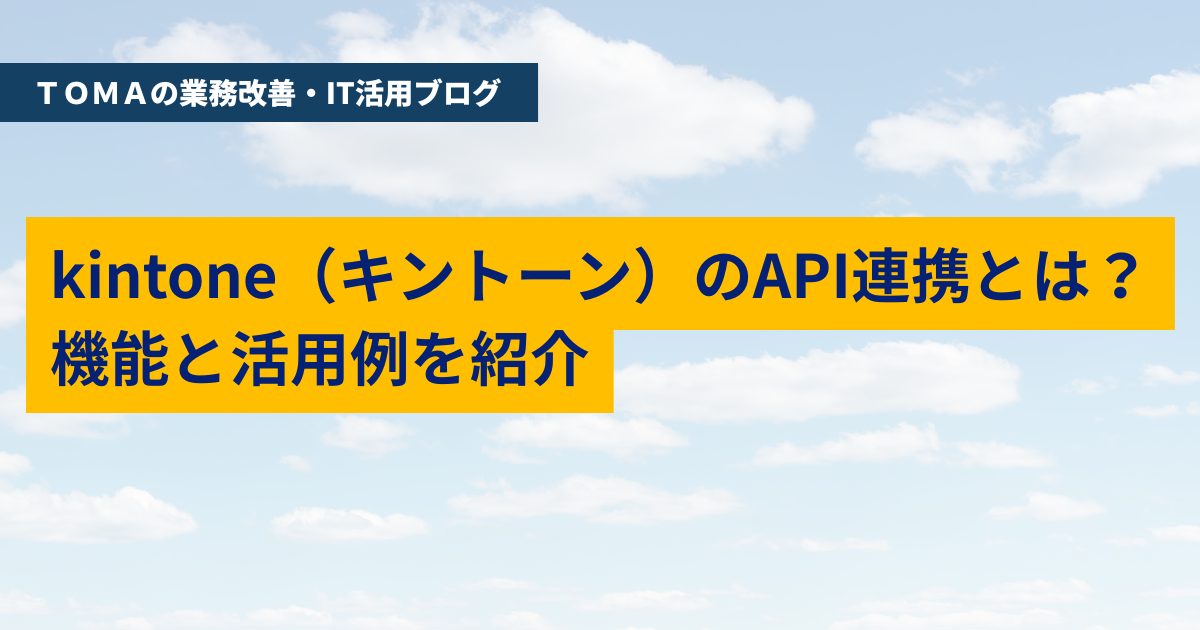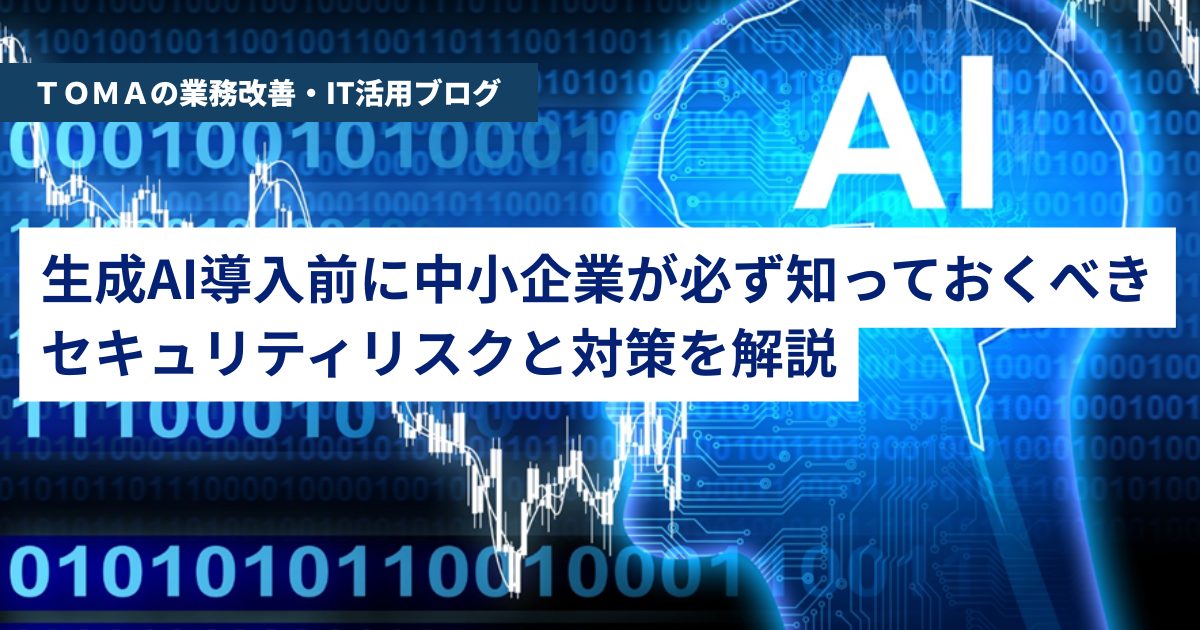ChatGPTやGeminiといった生成AIの登場以降、私たちの生活は大きく変化しつつあります。ビジネスにおいても、大企業を中心に生成AIの活用が進んでおり、中小企業にとっても生成AIの活用は欠かせないものになるでしょう。
企業がAIを導入し、その機能を十分に活用するには、まずAIについて理解することが重要です。
本記事では、AIの概要や生成AIとの違い、生成AIでできること、中小企業が生成AIを導入するメリットなどをご紹介します。生成AIを業務に導入する際の注意点も解説するので、導入をご検討中の方はぜひご覧ください。
目次
AIとは?簡単に解説

新聞やニュースなどで、AI(人工知能)に関する話題をよく耳にするようになりました。しかし、具体的にどのようなものなのかと聞かれると、うまく答えられない方も多いのではないでしょうか。ここでは、機械学習やディープラーニングといったAIに関する基本的な用語の意味や、AIと生成AIの違いを簡単に解説します。
機械学習とは?
AIと機械学習は同じものと思われることもありますが、根本は異なります。
AIは人間の知的な振る舞いを模倣し、コンピュータに実行させる技術全般を指す際に使われる言葉である一方、機械学習はAIを構成する主要な技術の一つです。具体的には、大量のデータからコンピュータが自動的にパターンや規則性を学習し、それに基づいて予測や判断を行ないます。
例えば、迷惑メールを振り分けるためのフィルタリングには機械学習が利用されています。従来のフィルタリングは、事前に設定したルールに従って迷惑メールを抽出していました。しかし、機械学習によるフィルタリングでは、運用中に得た情報から学習して判断するため、より抽出精度が高くなります。
このほか、過去の株価データをもとに、株価の上がり下がりを予測する際にも機械学習が利用されています。こちらも、精度は学習データが増えるほど高くなる点が特徴です。
ディープラーニングとは?
ディープラーニング(深層学習)とは機械学習の一分野で、画像認識や音声認識、自然言語処理など、より複雑なパターン認識や高度な判断を可能とする手法です。特に、情報を分析する際の条件を自ら見つけ出してくれるため、近年大きな注目を集めています。
ディープラーニングでは、人間の脳神経系に似た「ニューラルネットワーク」という分析構造が多く採用されています。入力層・隠れ層(中間層・分析を行う層)・出力層の3つが神経のように細かく結び付いており、隠れ層を増やせば、より複雑な判断が可能です。
AIと生成AIの違い
AIと生成AIはどのような違いがあるのでしょうか。
先述したように、AIは人間の知的な振る舞いを模倣し、コンピュータに実行させる技術全般を指すときに使われる言葉です。したがって、概念的な側面が強いといえるでしょう。対する生成AIは、AIの一種です。既存のデータから学習して、文章や画像、音声など「独自の新しいコンテンツの生成」に特化しています。
生成AIについて、ここ数年で誕生したものだと思う方もいるかもしれませんが、実際は1960年代には研究がスタートしていました。以前の生成AIは精度に問題がありましたが、近年は学習できるデータ量が増大し、ディープラーニングが発展したことで、実用的な精度に到達しています。
AIは大きく分けると特化型・汎用型の2種類
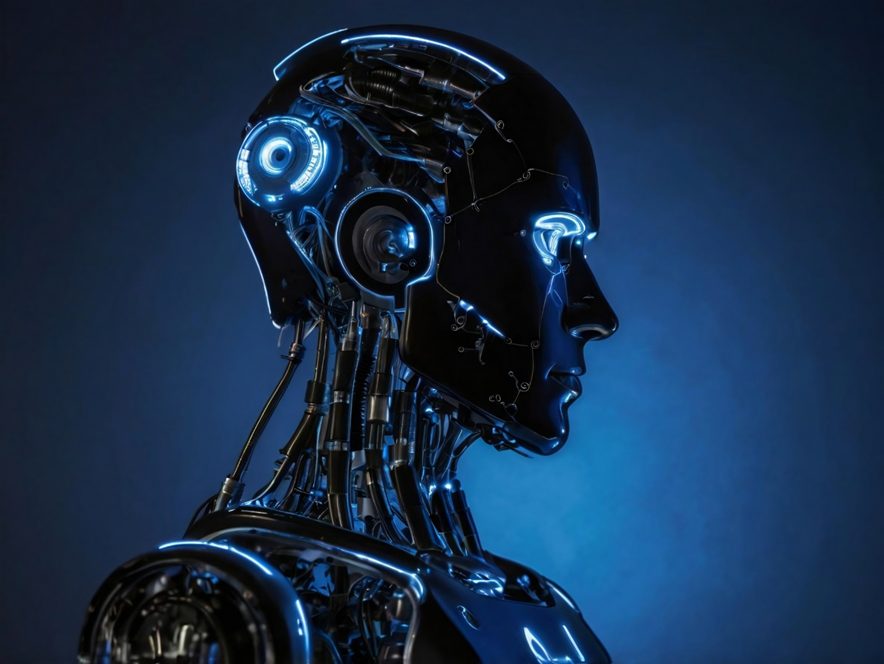
AIは、機能や自意識の有無によって大きく「特化型AI(弱いAI)」と「汎用型AI(強いAI)」の2種類に分けられます。現在実用化されているChatGPTやGemini、Claudeといった生成AIツールは、特化型AIの一種です。
一見すると万能そうなこれらの生成AIも、膨大なデータをもとに決められたルールに従って回答しているに過ぎません。そのため、特化型AIは自意識の有無という観点からは「弱いAI」と表現されることがあります。
一方の汎用型AIとは、人間の知性を完全模倣し、人間に似た知的行動が行なえるシステムのことです。SF作品に出てくるロボットのように限りなく人間に近く、場合によっては人間以上の思考能力をもつAIです。
そのため、弱いAIとも呼ばれる特化型AIに対して、汎用型AIは「強いAI」と表現されることがあります。
しかし、汎用型AIは2025年現在は実現のめどが立っていません。
生成AIでできることは?

生成AIは、私たちの働き方や創作活動などに大きな可能性をもたらす存在です。具体的にどのようなことができるのか、代表的な活用例を以下の4つのカテゴリに分けて解説します。
・文章理解・作成
・データの分析
・チャットボットによる応答
・画像作成
文章理解・作成
生成AIは人間が書いた文章の意味を理解して、その文章を要約したり質問に答えたりします。また、新しいブログ記事やメール、レポート、ユーザーからの回答など、さまざまな種類の文章を、指示に基づいて自動作成することも可能です。
ただし、生成AIは、人間が書いた文章を人間と同じように理解したうえで文章を作っているわけではありません。生成AIは言葉の意味を数値として読み取り、関連性が高い単語を組み合わせて文章を作り出しています。
そのため、定型的な処理は得意とするものの、まったく新しいことやイレギュラーなことへの対応には適していません。
データの分析
生成AIは、大量のデータから傾向やパターンを分析でき、データから何が読み取れるのかを人間が理解できるようにサポートします。
例えば、社内の日報データを分析すると、上司が効果的なフィードバックを行なえるようになります。また、顧客アンケートの自由記述部分の分析にも生成AIを使えば、大幅な省力化ができるだけでなく、分析結果を分類する基準の標準化も実現が可能です。
データが膨大になりがちなWebサイトのアクセスログ分析にも、生成AIは活用できます。分析にかかる業務負担が軽減されるほか、問題点をすぐ検出してくれる点もメリットです。このように、生成AIによるデータ分析は、人間の意思決定を支援してくれます。
チャットボットによる応答
生成AIチャットボットは、自然言語処理によって人間の言葉を理解し、適切な返答を行ないます。ユーザーからの問い合わせに対して自然な会話で対応したり、情報提供を行なったりするため、カスタマーサポートを自動化することが可能です。
24時間対応できる、同時に複数のユーザーに対応できるといったメリットがあります。また、社内ヘルプデスクの効率化にも利用されています。蓄積されたデータを読み込ませることで、生成AIが実務に沿って適切な回答をしたり、新たなデータ活用方法を提案してくれたりします。
画像作成
生成AIは、プロンプトと呼ばれるテキストの指示に基づいて、オリジナル画像を生成することも可能です。提案書に使うイメージ画像の作成や、製品カタログ用画像の編集、競合製品の広告画像の分析などに活用できます。
生成AIを活用したサービスの特徴

近年、多くの企業が生成AIを活用したサービスを提供しています。ここでは、テキスト生成に対応している代表的なサービスをピックアップして、それぞれの特徴を解説します。
ChatGPT(OpenAI)
ChatGPTはOpenAI社が開発した生成AIで、自然な対話形式でユーザーの質問に答えたり、文章を作成したりするサービスです。
「GPT」という大規模言語モデル(LLM)を利用しており、汎用性が高く、情報収集やアイデア出し、文章校正、プログラミング支援など幅広い用途に使われています。なお、大規模言語モデルとは、テキストの理解と生成に特化したAIモデルのことです。
ChatGPTのビジネスプランでは、セキュリティも向上しています。特に最上位プランの「ChatGPT Enterprise」では、入力したデータがAIのトレーニングに使用されないため、情報漏洩リスクを軽減できるでしょう。
加えて、データを転送・保存する際には暗号化される設計も採用されています。
Claude(Anthropic)
ClaudeはAnthropic社が開発した生成AIです。ほかの生成AIサービスと比べてより人間らしい自然な文章を作成できる特徴があります。
プログラムのコーディング能力の高さも、Claudeの特徴です。コードが動かないときには原因や解決策を丁寧に教えてくれるため、コーディング初心者でもわかりやすいでしょう。
Claudeはユーザーデータの取り扱いに関する安全性が高く、ユーザーデータをAIのトレーニングに利用するのは、ユーザーの同意があった場合だけとしています。具体的には、ユーザーが出力された結果に対して、「いいね」「よくないね」をクリックしたときだけ利用される仕組みです。
Gemini(Google)
GeminiはGoogle社が開発したマルチモーダルAIです。マルチモーダルAIとは、テキストだけでなく、画像や音声、動画など、さまざまな種類の情報を統合的に処理・生成できるAIを指します。
例えば、ユーザーが動画とテキストを使って質問をした場合、動画とテキストを総合的に理解したうえで回答をしてくれます。
Geminiは、GmailやGoogleスプレッドシートなど、Google社が展開しているサービス内で直接使用可能です。自社でGoogleドキュメントなどを利用している企業にとって、Geminiの導入ハードルは低く感じられるでしょう。
生成AIの統合型プラットフォームも登場傾向にある
近年は多くの生成AIが登場しているため、どれを使えばいいのか判断できずにいたり、用途別に複数の生成AIを契約したりしている方もいるでしょう。
こうしたユーザー向けに、複数の生成AIを1つのサービス内で利用できる「統合型プラットフォーム」も登場しています。
統合型プラットフォームを利用すれば、複数の生成AIと契約しなくても、自分の用途に合った生成AIをスムーズに切り替えて使えるようになります。
業務で生成AIを利用する場合は、プロンプト管理やログ監査などが必要です。しかし、統合型プラットフォームにはこれらの機能も備えられているため、企業が生成AIを導入するハードルが下がるでしょう。
中小企業が業務に生成AIを導入するメリット

大企業よりもリソースが限られている中小企業だからこそ、生成AIを導入するメリットがあります。ここでは、中小企業が生成AIを導入することによって期待できる、5つの効果について解説します。
・業務効率化
・コスト削減
・チャットボットを活用した顧客満足度向上
・企業競争力の向上
業務効率化
文書や資料の作成は多くの企業で行なわれる基本的な業務ですが、リソース不足によりそこまで手が回らないケースもあるでしょう。
しかし、定型的な事務作業が得意な生成AIにメール作成や議事録要約、資料作成などを任せれば、労力と時間を短縮できます。
また、情報収集やアイデア出しなども生成AIは得意です。これらの業務にも生成AIを活用すれば、従業員はより重要度の高い業務に集中できるようになるでしょう。
コスト削減
人の手で行なっていた作業を生成AIで自動化・効率化できれば、コスト削減につながります。これまで特定の社員が行なっていた業務を生成AIに任せれば、当該社員の業務負荷は軽減されます。
さらに、新入社員への教育・研修に生成AIを導入することで、従来の集合研修や個別指導にかかっていたコストの削減も可能です。
チャットボットを活用した顧客満足度向上
生成AIは顧客満足度の向上にも役立ちます。例えば、飲食店で予約や問い合わせの対応を電話で行なっていると、電話がつながらなかったり、電話できる時間が限られていたりすることで、顧客満足度が下がりがちです。
しかし、AIチャットボットであれば24時間365日で顧客対応が可能です。つながりにくくなることもないため、顧客へのスムーズな対応が可能になります。
また、顧客の過去の注文履歴などに基づいて、パーソナライズされたメニューを提供できるところも、顧客満足度向上につながるでしょう。
企業競争力の向上
生成AIはデータ分析能力に優れているため、膨大なデータを分析し、企業として何をすべきなのかを判断する材料を提示してくれます。
具体的には、売上や需要の予測精度の向上、リアルタイムに近い早さでの市場動向の分析、複数の要因を加味した精密なリスク評価などが可能です。
このように活用することで、経営戦略やマーケティングの施策実施スピードの向上が期待できます。
【部門別】中小企業の業務サポートで生成AIが活用できる具体例

生成AIは中小企業のさまざまな部門で、業務の効率化や品質向上に貢献できます。ここでは、生成AIの具体的な活用例を部門別に紹介します。
人事・経理部門でのAI活用
人事・経理部門では、次のような用途に生成AIを活用することで、手作業によるミスを減らし、業務時間を短縮できます。
・求人原稿の作成
・社員からの定型的な問い合わせへの自動応答
・経費精算データの入力補助やチェック
・ExcelマクロやPythonなどを使ったデータ集計
求人原稿を手作業で制作する場合、掲載先ごとのルールに沿った内容にしなければなりませんが、すべてのルールの把握は困難です。しかし、生成AIはすべてのルールを学習してくれるため、効率的に作成できます。作業の属人化を防げる点もメリットです。
このほか、経費精算データの入力補助でのAI活用には、紙データをスキャンしてテキストを自動抽出することや、仕訳候補の提案などが考えられます。
営業部門でのAI活用
営業部門では、以下のような用途でAIを活用できます。
・顧客へのメールの文案作成
・営業日報や会議議事録の自動要約
・市場動向の分析に基づいた営業戦略の提案
・プレゼンテーション資料の構成案作成
AIをCRM(顧客管理システム)と連携させると、顧客のデータに基づいてパーソナライズされたメールの文案を作成してくれたり、次に取るべき行動を提案してくれたりします。
また、ChatGPTのようにスマートフォンでも使える生成AIサービスを利用すれば、外出先でも手軽に業務報告書の下書き作成などが可能です。
マーケティング部門でのAI活用
マーケティング部門では、生成AIを次のような用途で活用できます。
・SNS投稿のアイデア出し
・自社コンテンツの作成
・広告コピーの作成
・アンケート結果の分析とレポート作成
SNS投稿や自社コンテンツの作成に生成AIを使うと、業務の効率化につながります。ただし、過度に依存すると企業としての特色が失われるケースがあるため、最終的な編集は人の手で行うことが大切です。
また、従来のアンケート分析は属人的な部分があり、分析者によって結果が異なる場合がありました。しかし、生成AIを使えば、一貫した基準による分析が可能です。加えて、アンケート結果を視覚的にわかりやすいレポートにして、出力することもできます。
IT部門でのAI活用
IT部門では、以下のような用途が考えられます。特に、開発サイクルの短縮や運用保守業務の負担軽減につながるでしょう。
・プログラムコードの自動生成
・既存コードのバグチェックや修正提案
・技術文書の作成支援
・システム障害の予防保守や発生時の修正提案
システム保守については、将来的にAIを活用して完全自動化される可能性があります。
生成AIを業務に導入する際の注意点

生成AIは私たちにさまざまなメリットをもたらしますが、導入する際にはいくつかの注意点を理解して対策しておかなければなりません。ここでは、特に重要な3つのポイントを解説します。
セキュリティのリスク
機密情報や個人情報を生成AIに入力すると、AIサービスの提供企業のサーバーにデータが送信・保存されます。そのデータは、ほかの人への回答に使用されたり、提供企業内で不正行為が行なわれた場合に漏洩したりすることがあります。
したがって、自社が情報を管理できなくなるリスクを認識したうえで、入力する情報を慎重に判断しなければなりません。また、生成AIそのものがサイバー攻撃の対象になる可能性もあるため、利用するサービスのセキュリティ対策を確認しておくことが重要です。
責任の所在
生成AIは誤った情報を生成したり、著作権を侵害するようなコンテンツを作成したりすることがあります。
したがって、業務に導入する場合には、それらをそのまま使用してしまったときに、誰が責任を負うのかを、事前に明確にしておかなければなりません。AIサービスの提供企業のなかには、権利侵害で訴えられた場合に法的責任を負うと表明しているところもあり、対策の一つになるでしょう。
しかし、企業側も生成AIの出力はあくまで参考とし、最終的な判断は人間が行うという意識をもつことが大切です。そのためには、生成AIを安全に利用するためのルールを社内で定めておく必要があるでしょう。
人材教育が必要
生成AIを効果的・安全に活用するには、従業員のAIリテラシー向上が欠かせません。AIの基本的な仕組みやAIにできること・できないこと、潜在的なリスク、適切なプロンプトの作成方法などに関する研修を実施し、社内での利用ルールを周知徹底する必要があります。
まとめ
AIとは、人間の知的な振る舞いを模倣し、コンピュータに実行させる技術全般を指す言葉です。私たちが利用しているChatGPTやGeminiなどはAIの一種である生成AIに該当し、学習した内容に基づいて独自のコンテンツを生成できる特徴があります。
中小企業が生成AIを導入すると、業務効率化やコスト削減、顧客満足度の向上といったメリットがあります。しかし一方で、生成AIにはセキュリティリスクや責任の所在といった注意すべき点も存在するため、これらへの対策も欠かせません。
業務への生成AIの導入を検討しているのであれば、TOMAのAI導入支援サービスをご検討ください。TOMAのAI導入支援サービスでは、生成AIをどのように役立てていくかを、企業の方とともに考えて作り上げていきます。
TOMAにはAIに関する専門家が在籍しており、企業の業務全体を分析したうえで、最適なプランを提示することが可能です。
また、ご相談も受け付けております。お気軽に以下無料相談・お問合せよりご連絡ください。