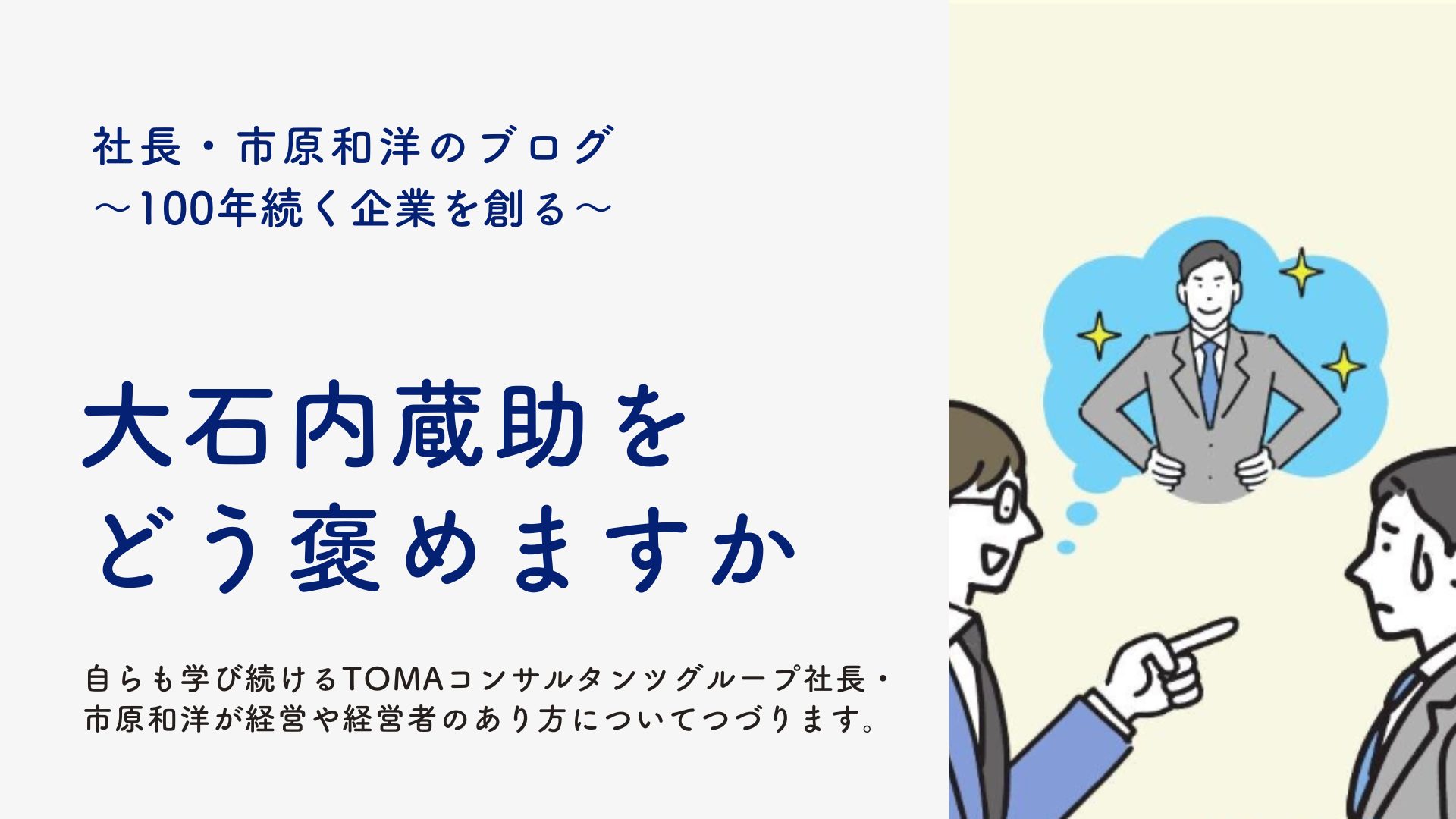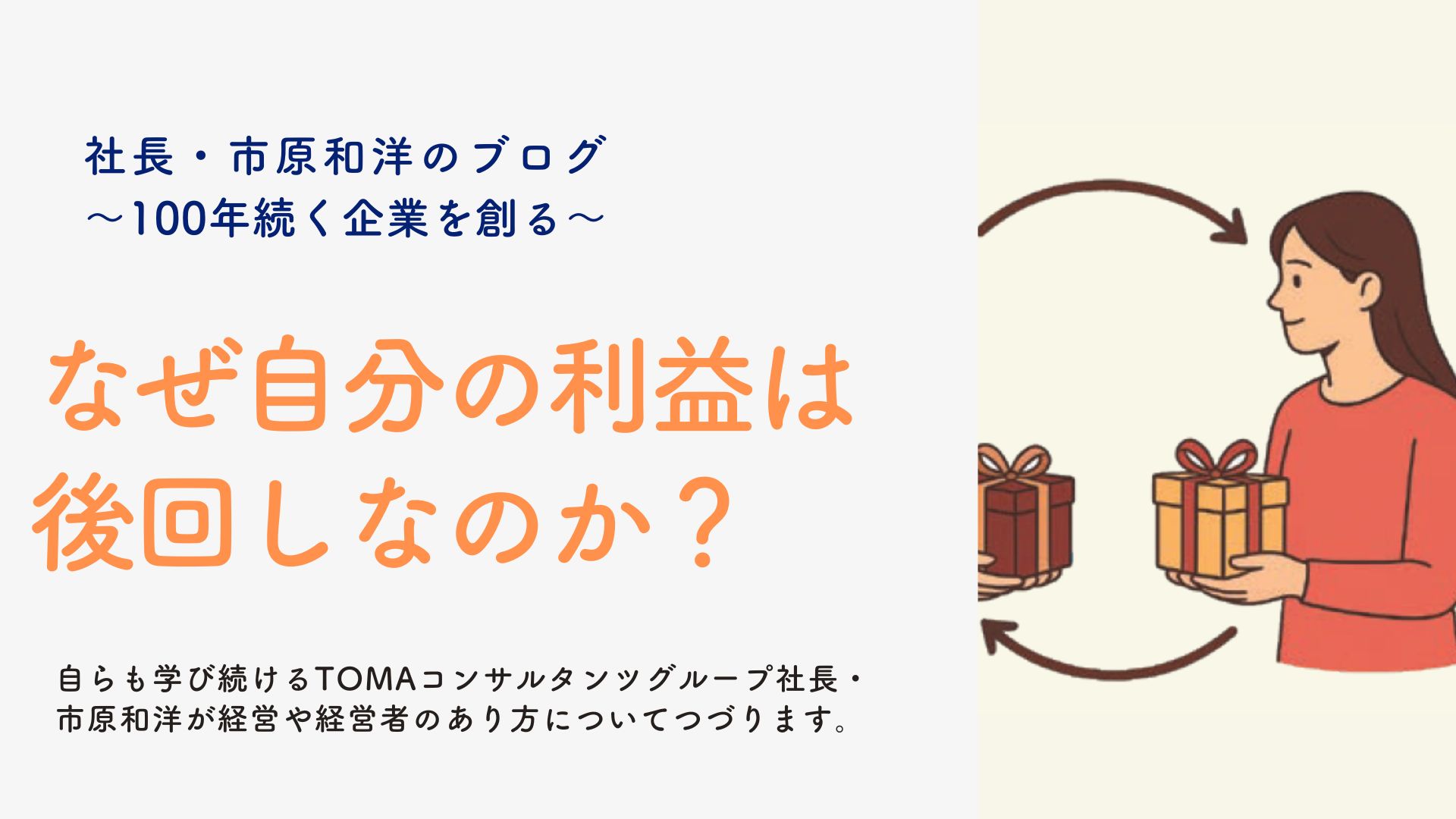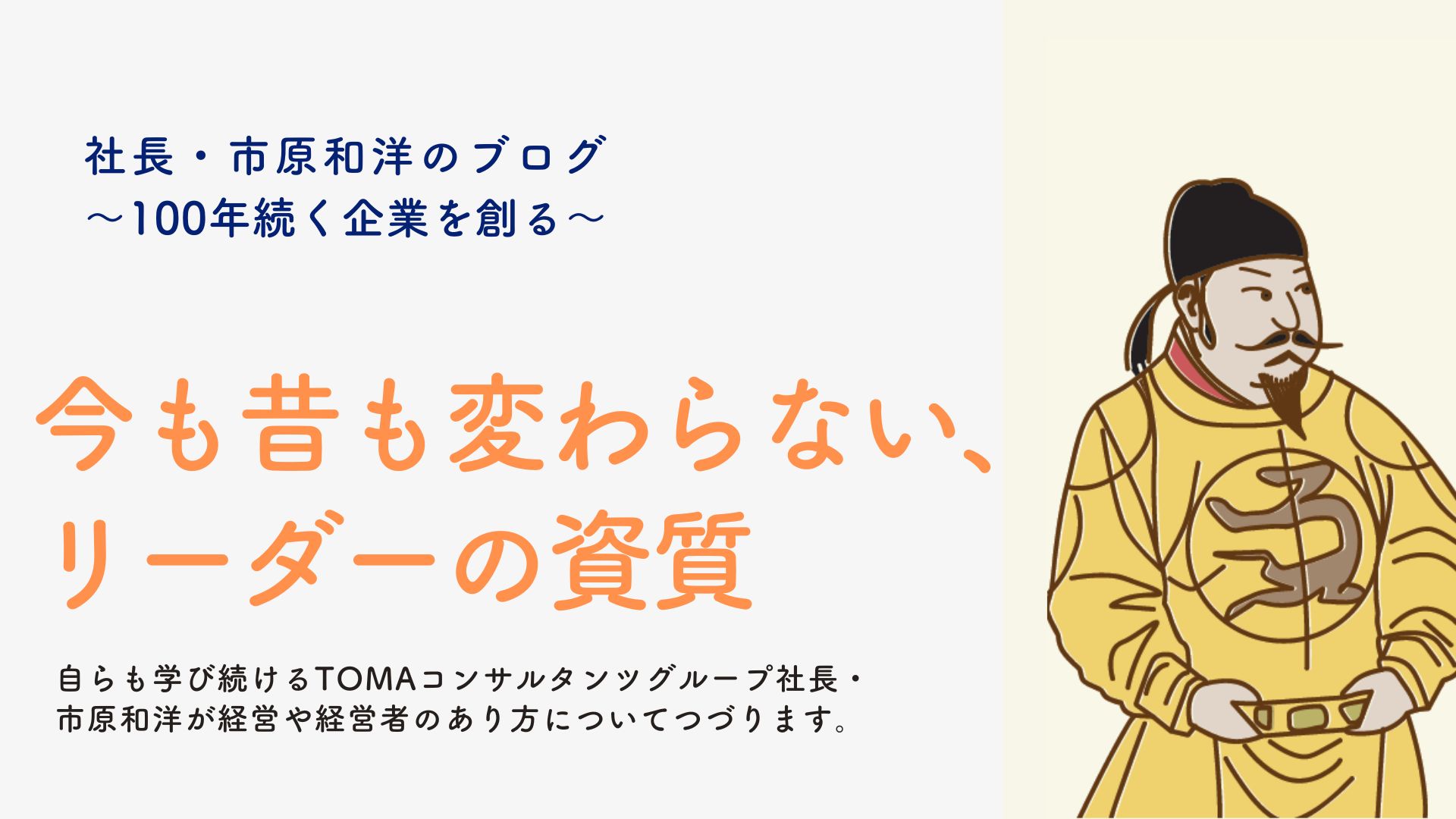芥川龍之介の短編小説『或日の大石内蔵助』を読んでみました。討ち入りを果たした後、細川家の屋敷で裁きを待つ大石内蔵助の心情を、芥川龍之介独自の視点で描いた作品です。ここで語られる内蔵助は、芥川龍之介が当時の社会を風刺したものであり比喩ではあるものの、読む人に新しい視点と気付きをもたらしてくれると思います。
大石内蔵助の気持ち
多くの人にとって大石内蔵助は、主君への忠義を貫いた忠臣蔵のヒーローだと思います。私は討ち入り後の内蔵助の心情まで想像したことはありませんでしたが、この小説を読む前であれば、恐らく自分の美徳に従い目的を果たした満足感や達成感のようなものを想像したことでしょう。
しかし当の内蔵助の心情は少し異なります。ある日、仇討ちを果たした満足感に浸っていた内蔵助は、自分に対する賞賛の声に、何とも言えず憂鬱でいたたまれない気持ちになるのです。
最初の違和感は、討ち入り後、江戸中で仇討ちの真似事が流行しているという話を聞いたことでした。米屋の亭主が職人に殴られ、米屋の丁稚が仇討ちと称して職人を襲い大怪我をさせてしまったという話です。乱暴な行いにも関わらず、町では丁稚の方が素晴らしいと賞賛されていることを聞くと、内蔵助は自分のした事の影響に少しの驚きを感じます。
次に細川家の者たちが内蔵助の忠義を褒め称えますが、内蔵助は恥ずかしいと謙遜します。実は赤穂藩には多くの浪士がいたものの、同盟から抜けて討ち入りに加わらなかった者も沢山いたからです。その中には身分が高い者も、内蔵助の親族の者もいました。
内蔵助は同盟から抜けた者たちの気持ちを理解し、憎いとまでは思っていませんが、話が盛り上がると、武士の風上にも置けない人畜生であると批判する声が起こります。内蔵助は思います。「何故我々を忠義の士とするためには、彼等を人畜生としなければならないのであろう」と。
さらに内蔵助が自由気ままに遊んでいたのは世間を欺くためであったと賞賛されると、ますます憂鬱で後ろめたい気持ちになっていきます。実は世間を欺くためではなく、時には復讐を忘れてただ楽しんでいたこともあったからです。そして内蔵助は、自分への誤解に対する反感の気持ち、誤解されたまま世間の勝手な賞賛の声が後代に伝えられていくだろうことを思い、ため息をつくのです。
相手の立場に立って考える
人は誰でも、自分の存在を認めてもらいたいし褒められたいものだと思います。しかし実際の人の気持ちはそう単純なものではないかもしれません。皆さんも、身近な人を良かれと思って褒めたもののそれほど喜ばれなかった、思わぬ反応が返ってきたということがあるのではないでしょうか。
よく「相手の立場に立って考える」ことが重要であると言われます。お客様の立場、部下の立場、ビジネスに限らず様々な場面で相手の立場に立って考えることは確かに重要です。
しかし、私たちは本当に相手の立場に立って考えられているでしょうか。相手の立場というシチュエーションを想像し考える際には、相手には心があるという前提を忘れてはいけません。相手には心があるから様々なことを思い、考えるのです。
人を褒める時も同様です。相手には心があるという前提を忘れるから、勝手な大石内蔵助像を想像し、的外れな賞賛の声を送ってしまうのではないでしょうか。
自分が褒められた時のことを思い返してみれば、欲しいのは、行動や結果に対する賞賛の言葉だけでなく「自分の気持ちを理解してくれる」とか「普段から気にかけてくれる」と感じられることだと気づくと思います。
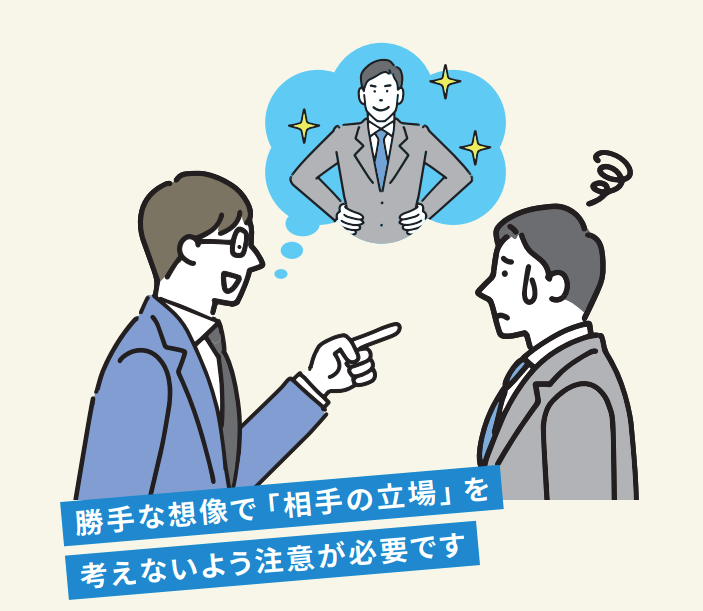
文学に殆ど触れたことの無い私がこの小説を読んだのは全くの気まぐれですが、小説からも新たな気づきが得られることを知りました。
芥川龍之介に興味を持った方には、『桃太郎』もお薦めです。なぜ桃太郎が鬼ヶ島の征伐を思い立ったのかや、鬼の立場から見た桃太郎の行動など、何かしら新しい気付きをもたらしてくれると思います。
TOMAコンサルタンツグループ株式会社
代表取締役社長
市原 和洋
代表メッセージはこちら
<チェックポイント>
□人は褒めれば喜ぶとは限らない
□相手には心があるという前提のもとに相手の立場に立って考える
□行動や結果への賞賛だけでなく「気持ちを理解してくれる」「普段から気にかけてくれる」と感じられることも大切である