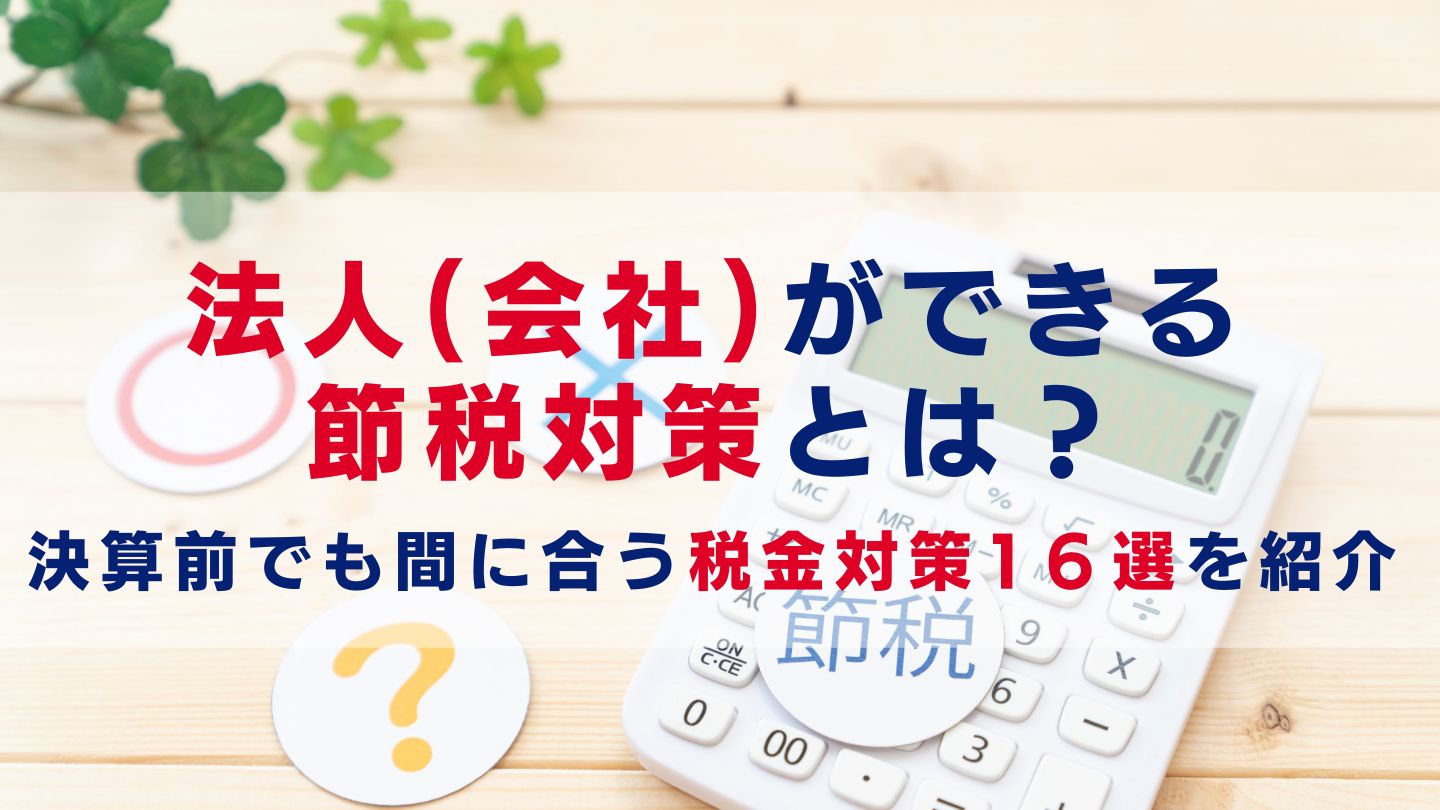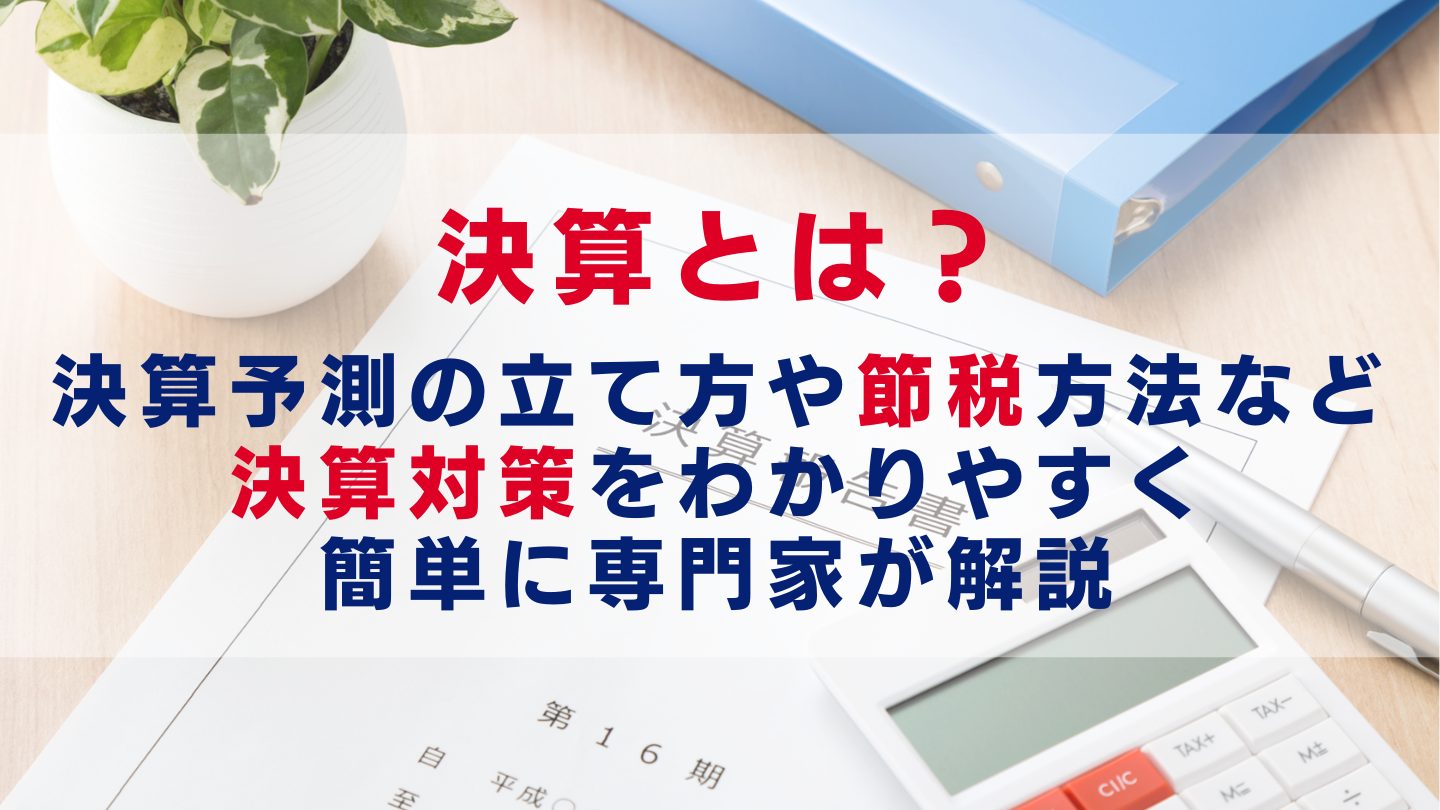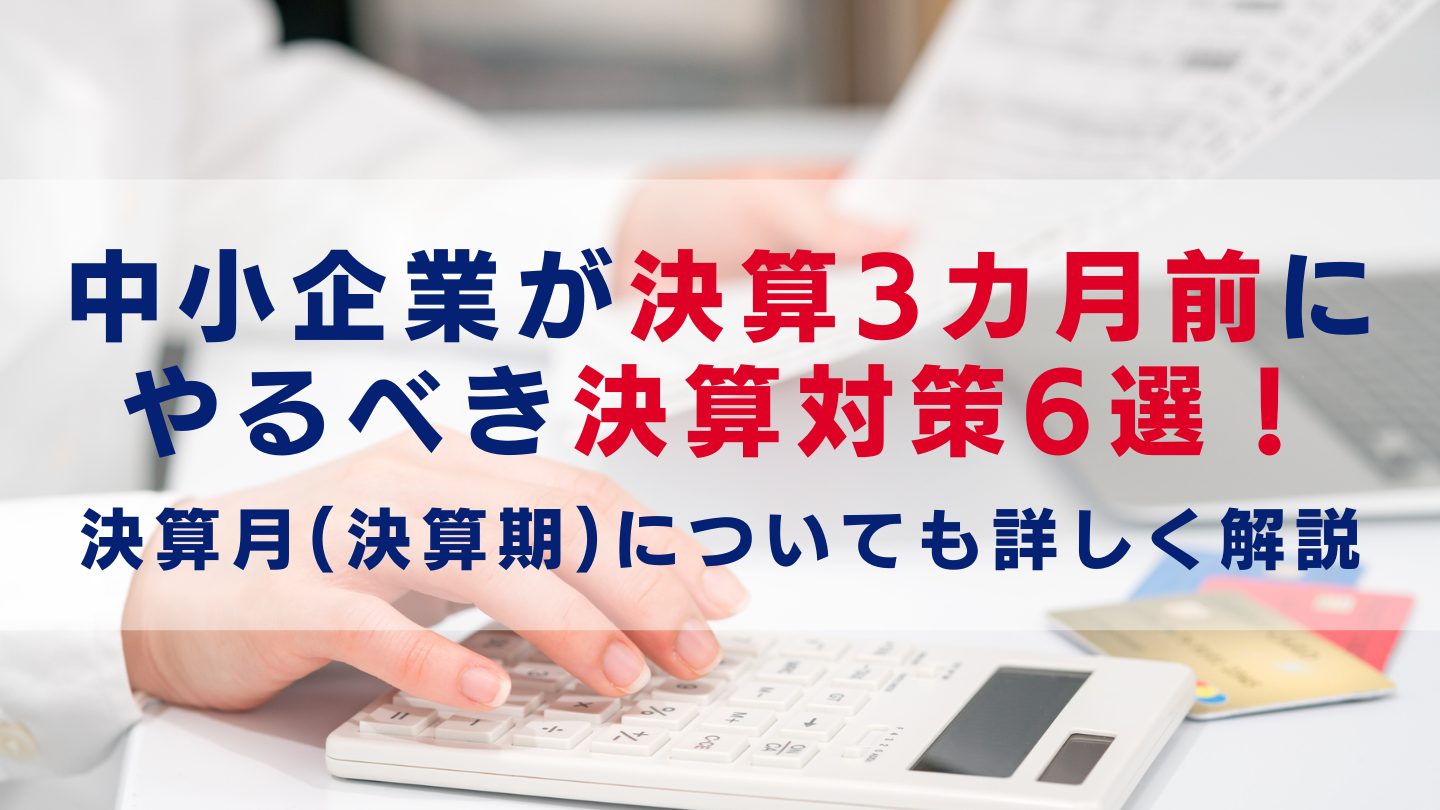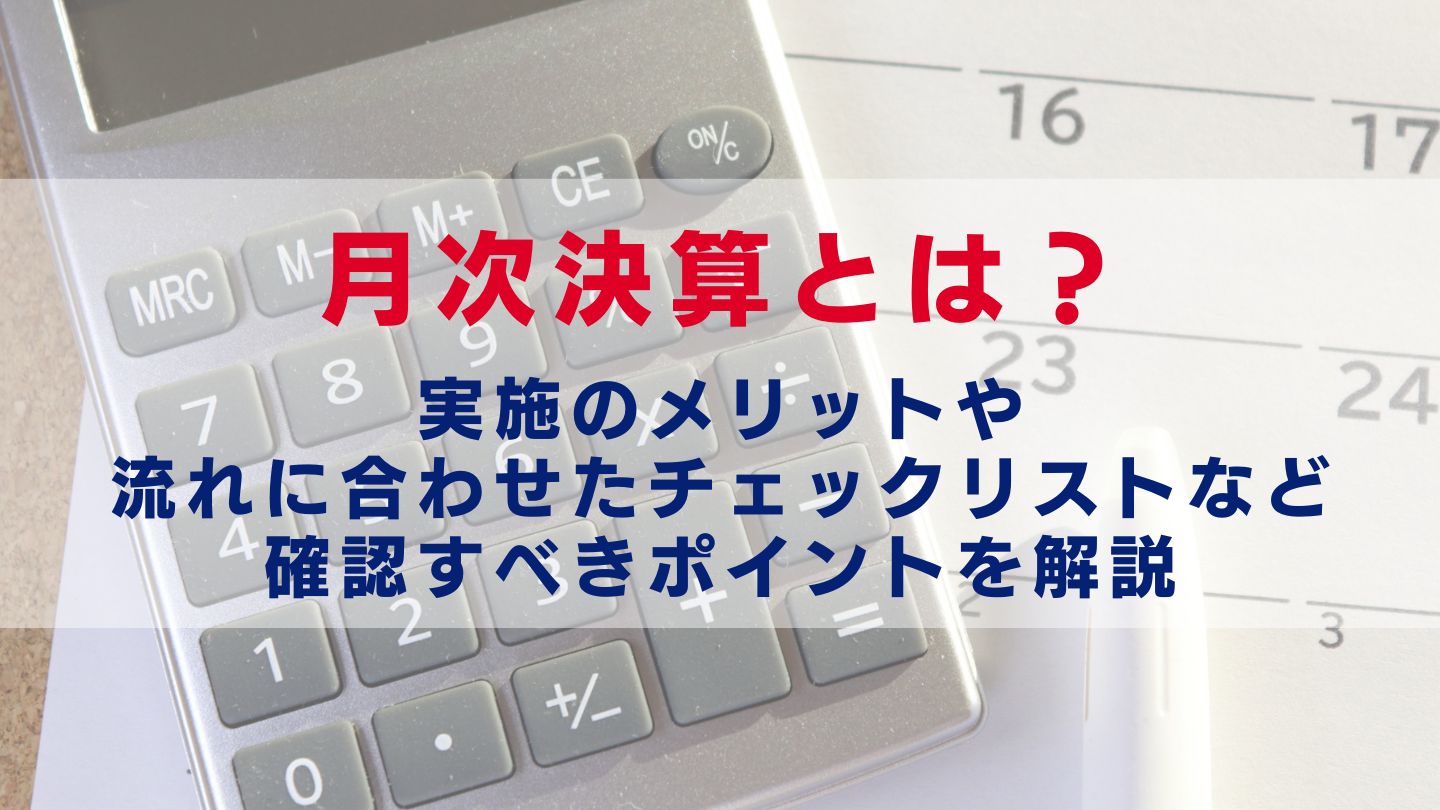法人(会社)を運営すると、法人税や法人事業税といった税金が課されます。手元に残るお金を増やすためには、何らかの節税対策を講じることが重要です。そのため、節税に向けて法人がどのような対策を検討すべきか、具体的に知りたい方も多いのではないでしょうか。
この記事では、節税対策の基礎知識を踏まえつつ、決算前でも間に合う節税対策16選と節税対策の注意点を紹介します。法人が節税を実現するためのノウハウを学べるので、ぜひご一読ください。
「節税対策」とは?

節税対策とは、簡単に説明すると「税負担を抑えるためにする対策」のことです。経費計上をはじめとする対策を講じ、納めるべき税額を減らすことで、手元に多くのお金を残せるようになります。
節税と一文字違いで「脱税」という言葉もありますが、この2つは当然ながら全くの別物です。節税は合法的に税金を減らすための行為ですが、脱税は違法な手段によって納税義務を免れる行為を指します。
脱税が発覚した場合には、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金といった重いペナルティが科されます。
決算前に検討すべき節税対策16選

法人(会社)向けの節税対策と一口にいっても、さまざまなものがあります。そのため、何をどう検討すべきか迷ってしまうかもしれません。
ここでは、決算前でも間に合う節税対策16選を紹介するので、ぜひ参考にしてください。
1.消耗品・備品の購入
オフィス用品や日用品などの消耗品・備品を購入した場合、その金額が10万円未満かつ以下に挙げた3つの要件を満たせば、購入した事業年度の経費になります。そのため、決算前のタイミングで購入すると効果的です。
- 毎年一定数量を購入している
- 毎年継続的に消費している
- 上記処理方法を継続的に適用する
ただし、明らかに事業と関係のない個人的な支出は経費として認められないため、注意しましょう。
2.修繕費の支出
オフィスの修繕・改修や事業で使う設備の修理を行うと、支出として修繕費が発生します。その際の修繕費を経費として計上すれば、節税につなげることが可能です。
ただし、以下の条件にすべて当てはまる場合などは、修繕費ではなく「資本的支出」として扱われる可能性があります。
- 1つの修繕にかかる費用が20万円以上
- 修繕の周期が3年超
- 資産の耐久性や価値を明らかに向上させる修繕
資本的支出は修繕費と異なり、全額を発生年度に経費計上できず、長期的に減価償却されます。支出が発生した年に限って見ると、修繕費よりも節税効果は低下する傾向があります。
3.役員報酬の損金算入
役員報酬は一定の要件を満たせば、損金算入(経費計上)できるようになります。経営者が自分の役員報酬を調整し、法人税額を不当に低くすることを防ぐため、無条件での損金算入は認められていません。
役員報酬を損金算入するためには、以下のうちいずれかの支払い方法を選ぶ必要があります。
- 定期同額給与:1ヵ月以下の一定期間ごとに定額で支給する給与
- 事前確定届出給与:あらかじめ金額や支給時期を確定し、税務署へ届出を行って支給する給与
- 業績連動給与:業績に応じて支給する給与
4.不要な在庫や固定資産の処分
不要な在庫を抱えている場合には、まとめて廃棄処分することで、棚卸資産が減少します。その結果、売上総利益が圧縮されるため、税負担を抑えることが可能です。
また、決算セールや在庫処分セールと称して赤字販売すれば、赤字部分を損金算入でき、節税につながります。
このほかにも、不要な固定資産の廃棄・取り壊しを行い、帳簿から除去すると、廃棄・取り壊し時点の資産時価を固定資産除却損として損金算入できるようになります。
5.社宅制度の導入
法人が借りた賃貸物件を社宅として従業員に貸し出し、従業員から一定額以上の家賃を徴収している場合、法人が負担している家賃を経費計上でき、節税につながります。
社宅制度を導入すれば、住宅コストの軽減によって従業員の生活が安定しやすくなる点もメリットです。結果的に働きやすさや仕事へのモチベーションの維持・向上が期待でき、離職率の低下や求人応募の増加につながります。
6.退職金制度の導入
退職金として支給した金額は全額損金に算入できるため、節税効果が見込めます。
退職金は給与や役員報酬と異なり、社会保険料のような法定福利費が発生しない、分離課税で税率が低くなりやすいなど、従業員・役員にとっても大きなメリットがあります。退職金制度を設けると福利厚生の充実度をアピールしやすいため、求人応募の増加にもつながるでしょう。
7.健康診断を福利厚生費にする
一定の要件を満たせば、福利厚生費として健康診断の費用を計上できるようになります。福利厚生費は基本的に非課税のため、法人の節税対策にとって有用です。
健康診断の費用を福利厚生費で計上するための要件は、以下の5つです。
- 全従業員を健康診断の対象にする
特定の従業員や役員を対象にした健康診断の費用は、福利厚生費になりません。 - 費用の全額を法人が負担する
健康診断を受けた従業員全員分の費用は、法人名義で医療機関に支払う必要があります。 - 労働安全衛生法に基づく健康診断である
労働安全衛生法で義務付けられている定期健康診断の費用は、福利厚生費になります。 - 業務に直接関連しない
業務を遂行するために欠かせない法定健診などの費用は、福利厚生費ではなく「法定福利費」になります。 - 個別の医療行為に該当しない
人間ドックやオプションの精密検査にかかる費用は、福利厚生費として認められない可能性があります。
8.決算賞与を支給する
決算賞与を支給する場合、一定の要件を満たすことで、経費として計上が可能になります。
決算賞与は決算直前のタイミングで配布が決まる傾向にあるので、支給が決算に間に合わないこともあるでしょう。しかし、以下の条件を満たせば、未払いでも当期分の経費に計上が可能です。
- 事業年度終了日までに、同時期に支給する全従業員に対して支給額を通知している
- 事業年度が終了する日の翌日から1ヵ月以内に、通知した支給額を全額支払っている
- 通知日が属する事業年度中に、支給額を損金として経理処理をしている
9.会議費の適切な処理(交際費との区分明確化)
会議費は交際費と混同されることがありますが、実際は似て非なるものです。それぞれの概要をまとめたので、両者の違いを把握しておきましょう。
| 科目 | 概要 | 事例 | ||
|---|---|---|---|---|
| 会議費 | 社内や会議で通常使用する場所での打ち合わせ、商談を行う際に必要となる費用。上限なし。 | ・会議室のレンタル料 ・会議で提供する茶菓などの飲食代 ・資料の印刷代 | ||
| 交際費 | 取引先などの関係者に対し、接待や贈答を行うための費用。上限あり。 | ・接待を目的とした食事の飲食代 ・お中元やお歳暮の費用 | ||
これまで、本来会議費になるものを交際費として計上していた場合には、適切な経理処理を行うことで、節税につながる可能性があります。
10.未払費用の計上
契約に沿って継続的に提供を受けているサービスであり、費用が後払いになるものは「未払費用」に該当します。当期に受けたサービスの支払いが翌期になっている場合、その金額を未払費用として計上することで節税につながります。
未払費用の具体例として挙げられるのは、通信費や広告宣伝費、水道光熱費、給与、社会保険料などです。なかでも、給与や社会保険料は金額が大きい傾向にあるので、高い節税効果が見込めるでしょう。
なお、未払費用とよく似た勘定項目に「前払費用」がありますが、こちらはまだ提供されていないサービスに対して前もって支払った費用のことです。保険料の一括払い、サブスク型サービス利用料の前払いなどが該当します。
翌期以降に提供されるサービスの前払費用は、いったん資産計上するのが原則です。しかし、前払費用のうち1年以内にサービス提供を受けるものは、支払った事業年度に経費計上できます。
上記は「短期前払費用の特例」と呼ばれる例外規定で、未払費用の計上と同じく節税対策に役立ちます。
11.赤字の繰り越しを行う
当期に発生した赤字を繰り越して翌期に黒字になった場合には、赤字と黒字を相殺できるようになります。これは「欠損金の繰越控除」と呼ばれる仕組みで、結果的に課税所得が減少するため、将来的な節税が可能です。
青色申告書を提出する法人の場合、以下の3つの要件を満たせば、国税庁に「欠損金の繰戻しによる還付」を請求できます。
- 前期・当期で連続して青色申告書である確定申告書を提出している
- 当期の青色申告書である確定申告書を期限までに提出している
- 当期の確定申告書とともに欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出している
例えば、前期が黒字で当期は赤字になった場合、前期の黒字に遡って赤字を相殺し、前期に納めた法人税の全部もしくは一部の還付を受けることが可能です。
12.広告宣伝費の計上をする
広告宣伝費は原則、費用が発生した事業年度に一括で経費計上できるため、節税対策に活用できます。
テレビCMや雑誌広告などでの宣伝は出稿に時間がかかるため、決算直前に出稿を決めた場合、決算に間に合わせるのは困難でしょう。しかし、Googleアドセンスやリスティング広告なら、即日で広告を出稿できます。決算前に出稿できれば、多額の広告宣伝費を計上することが可能です。
広告宣伝費に対するリターンが十分であれば、より大きな節税効果が期待できます。
13.設備投資を行う(中小企業経営強化税制・中小企業投資促進税制)
中小企業経営強化税制・中小企業投資促進税制を活用して設備投資を行えば、法人税の節税効果が見込めます。
中小企業経営強化税制は、青色申告書を提出する中小企業の設備投資による生産性や収益力などの向上をサポートするための制度です。中小企業等経営強化法に規定された経営力向上計画に基づいて対象の設備を取得し、指定事業で利用すれば、即時償却もしくは取得価格の最大10%の税額控除を適用できます。
【中小企業経営強化税制の適用要件】
| 類型 | 要件 | 確認者 | 対象設備 | その他要件 |
|---|---|---|---|---|
| 生産性向上設備 (A類型) | 生産性が旧モデル比平均1%以上向上する設備 | 工業会等 | ・機械装置 (160万円以上) ・工具 (30万円以上) ※A類型の場合、測定工具または検査工具に限る ・器具備品 (30万円以上) ・建物付属設備 (60万円以上) ・ソフトウェア (70万円以上) ※A類型の場合、設備の稼働状況にかかる情報収集機能および分析・指示機能を有するものに限る | ・生産等設備を構成するもの ※事務用器具備品・本店・寄宿舎等にかかる建物付属設備、福利厚生施設にかかるものは該当しない ・国内への投資であること ・中古資産、貸付資産でないこと等 |
| 収益力強化設備 (B類型) | 投資利益率が年平均7%以上の投資計画にかかる設備 | 経済産業局 | ||
| 経営資源集約化設備 (D類型) | 修正ROAまたは有形固定資産回転率が一定割合以上の投資計画にかかる設備 |
一方の中小企業投資促進税制は、青色申告書を提出している中小企業などが対象設備を導入する際に、取得価額の30%の特別償却もしくは7%の税額控除を選択適用できる制度です。
【中小企業投資促進税制の適用要件】
| 対象者 | 対象業種 | 対象設備 |
|---|---|---|
| ・中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、農業協同組合、商店街振興組合等) ・従業員数1,000人以下の個人事業主 ※税額控除は個人事業主、資本金3,000万円以下法人が対象 | 製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業については生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業および沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、通信業、損害保険代理業およびサービス業(映画業以外の娯楽業を除く)、不動産業、物品賃貸業 ※性風俗関連特殊営業に該当するものは除く | ・機械および装置(1台160万円以上) ・測定工具および検査工具(1台120万円以上、1台30万円以上かつ複数合計120万円以上) ・一定のソフトウェア(1つのソフトウェアが70万円以上、複数合計70万円以上) ※複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除く ・貨物自動車(車両総重量3.5トン以上) ・内航船舶(取得価格の75%が対象) |
なお、上記2つの制度には適用期限が定められており、2026年度末(2027年3月31日)までとなっています。
14.企業型確定拠出年金を導入する
企業型確定拠出年金は、企業が掛金を毎月拠出し、加入者である従業員が資産運用を行う年金制度です。従業員は60歳以降になると、年金や一時金という形で資産を受け取ることができます。
企業型確定拠出年金を導入すれば、掛金はすべて福利厚生費として扱われるため、経費計上による節税が可能です。
15.経営セーフティー共済に加入する
経営セーフティー共済とは、取引先の倒産による中小企業の経営難や連鎖倒産を防ぐために創設された制度です。売掛金が回収不可になった、半年以上の掛金を納付しているなどいくつかの要件を満たした場合、無担保・無保証人で、以下のうち少ないほうの範囲内で借り入れができます。
- 納付した掛金の10倍(最高8,000万円)
- 回収困難となった売掛金債権等の金額
経営セーフティー共済の掛金もすべて損金に算入できるため、節税を兼ねて加入するのも一案です。
また、掛金を12ヵ月以上納めている場合は自己都合の解約でも掛金総額の8割以上が、40ヵ月以上納めている場合は、掛金が全額返還されます。
16.中退共(中小企業退職金共済)へ加入をする
中退共(中小企業退職金共済)とは、中小企業が従業員の退職金を積み立てるために創設された制度です。企業側は毎月5,000円~3万円の掛金を納めますが、この掛金もすべて損金に算入できるので、節税効果が見込めます。
ただし、加入できるのは、常時従業員数と資本金・出資金のいずれかが、以下の範囲内に収まる中小企業のみです。
| 業種 | 常用従業員数 | 資本金・出資金 |
|---|---|---|
| 一般業種(製造・建設業等) | 300人以下 | 3億円以下 |
| 卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
| サービス業 | 100人以下 | 5,000万円以下 |
| 小売業 | 50人以下 | 5,000万円以下 |
法人が節税対策をする際の注意点
節税対策の基本は経費を増やし、利益(課税所得)を圧縮することです。しかし、過度に節税すると会計上は利益が減少しているように見え、銀行をはじめとする金融機関からの評価に悪影響が生じる可能性があります。
金融機関から「十分な利益を出していない企業」と評価された場合、融資を受けることが難しくなるでしょう。
また、ルールを逸脱した節税対策は「脱税」と判断されかねないため、いかなる状況でもルールに沿った合法的な手段を選ぶことが大切です。したがって、法人(会社)が節税対策を講じる場合は、税理士などの専門家に相談することを推奨します。
決算のご相談は、TOMAコンサルタンツグループにお任せください
法人(会社)向けの節税対策の多くは、実施することで、従業員のモチベーション維持や生産性の向上、退職後の安定した生活の実現など、副次的なメリットの発生が期待できます。決算前から実践できる対策もあるので、自社の状況やニーズに合わせて選択しましょう。
TOMAコンサルタンツグループでは、節税対策を含む税務顧問契約のサービスを提供しています。決算支援や月次監査、次年度の経営方針・計画のアドバイスなど幅広いサポートが可能なので、ぜひご相談ください。