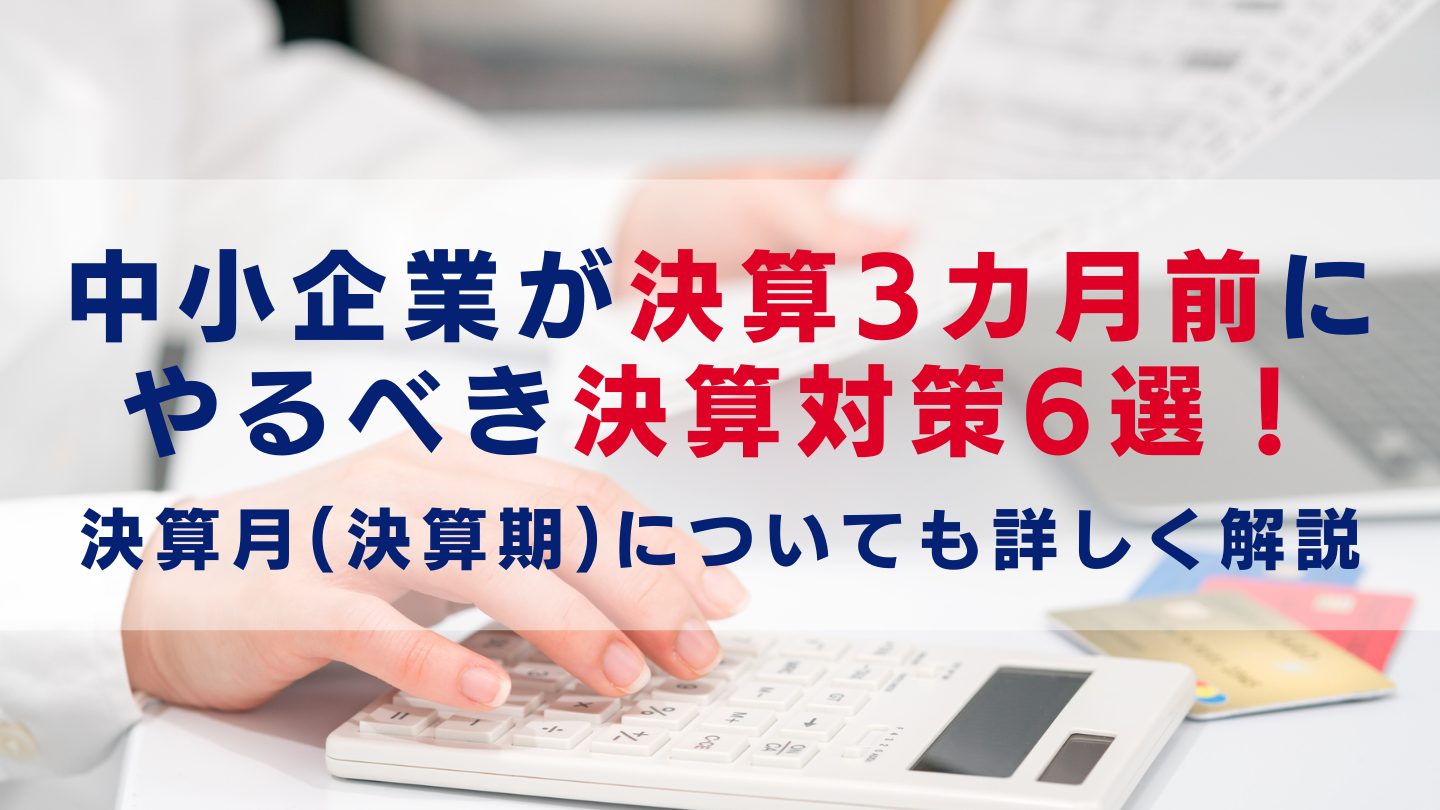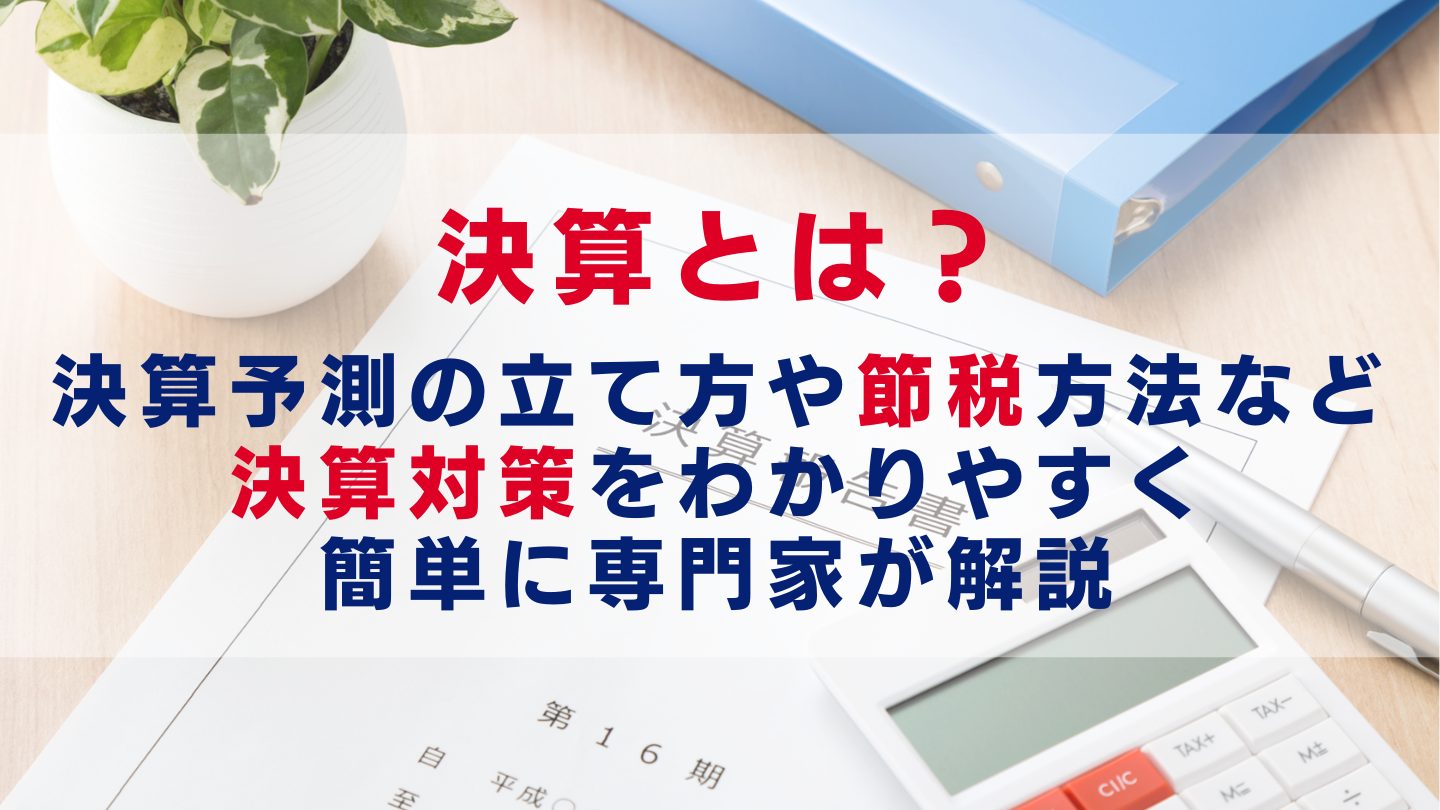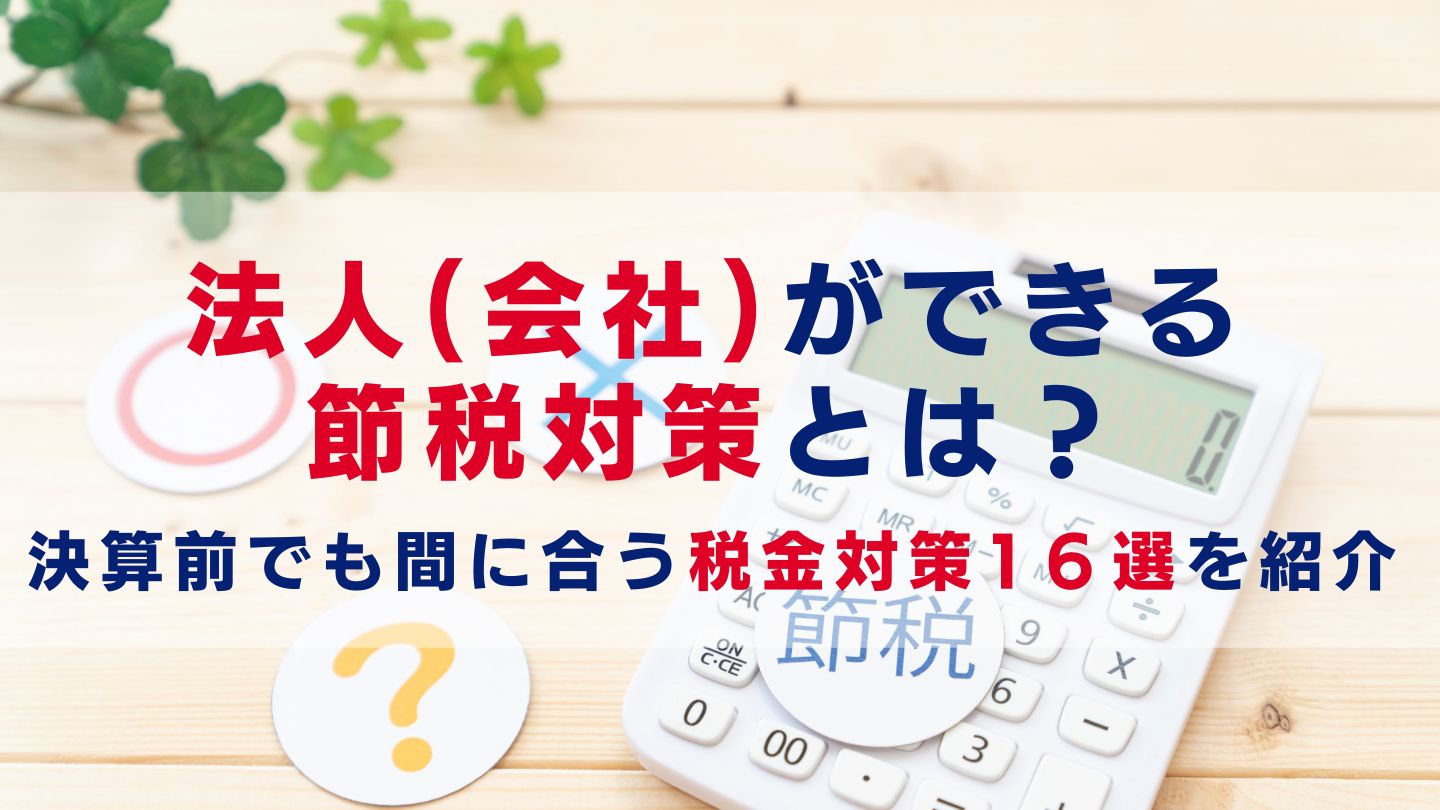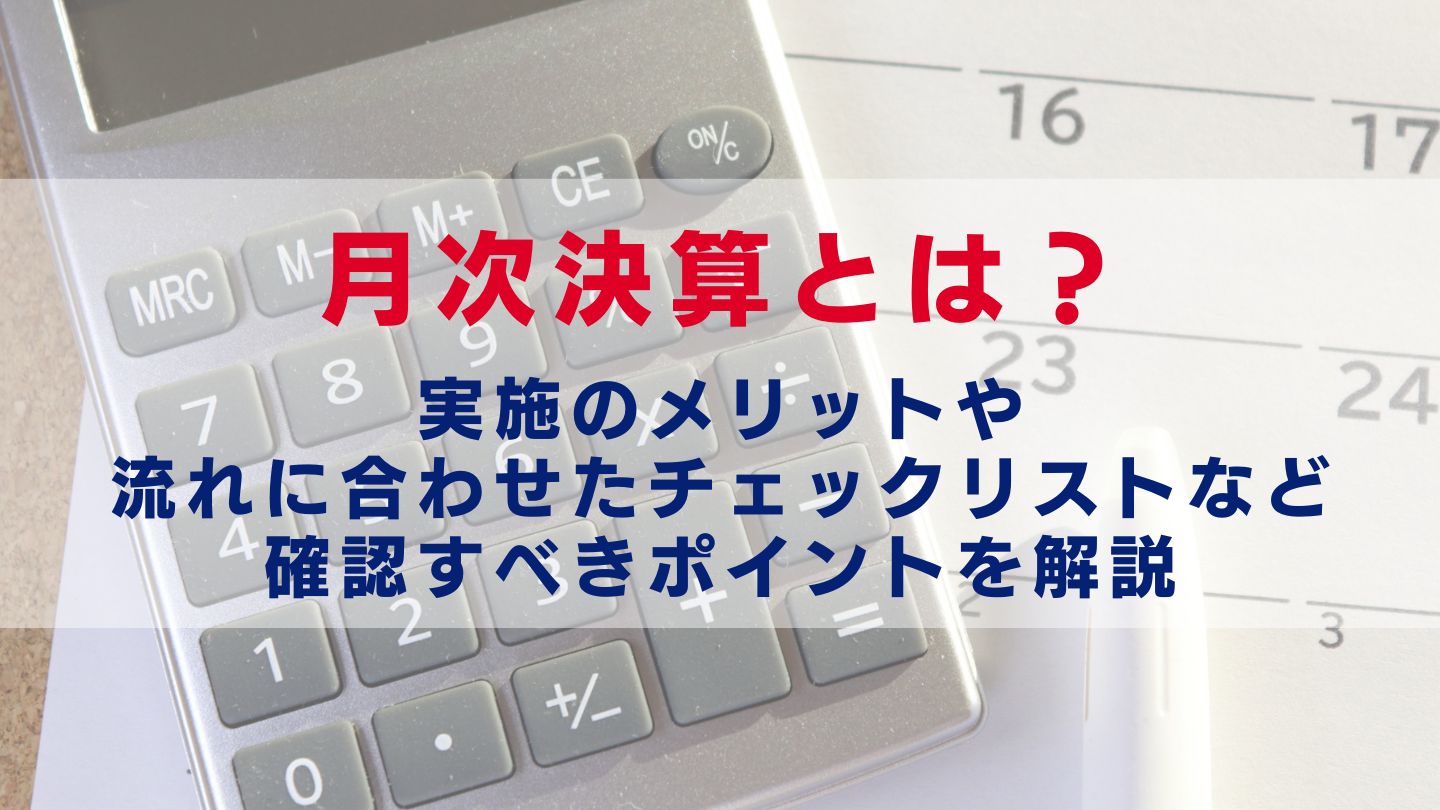毎年、決算対策に頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。決算3ヵ月前であれば、できる対策はいくつもあります。また、急激に利益が増えたり、資金繰りが厳しくなったりした場合には、決算月の変更も可能です。
本記事では、決算3ヵ月前でもできる決算対策を6つ紹介します。また、決算月の概要や決算月を変更する際の手続きなども解説しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
決算月(決算期)とは
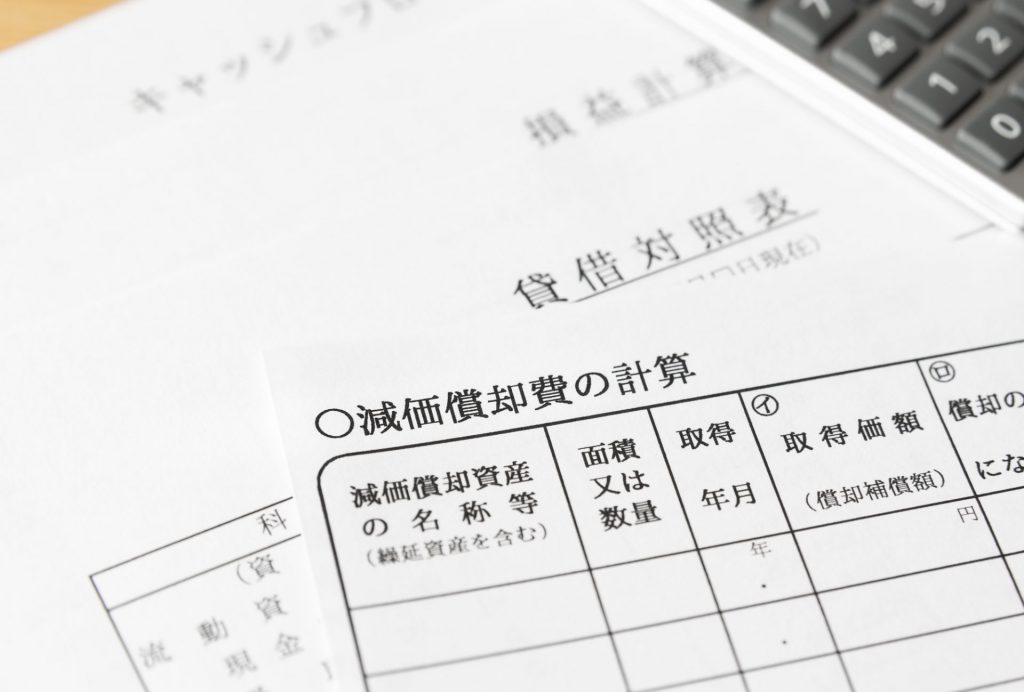
「決算月(決算期)」とは、企業の経営成績や財政状態をまとめる月のことです。具体的には、事業年度の最後の月を指します。例えば、事業年度を「4月1日~3月31日」にした場合は、3月が決算月になります。
事業年度は、会社設立時に各企業の都合に合わせて1年以内の期間で自由に決められ、事業年度を半年にして決算を年に2回行うことも可能です。
国税庁が2023年度に行なった調査によると、年1回決算の企業の中で最も多い決算月は3月で、53万3,389社が該当します。次いで多いのが、9月の32万4,545社、その次が12月の31万2,047社となっています。
3月を決算月に選ぶ企業が多い理由は、日本では国や自治体が予算や計画を4月から組んでいることが一般的で、行政と関わりが深い企業はそれに合わせたほうがスムーズだからです。法律改正も4月に行なわれるケースが多く、決算月が3月であれば法改正にも対応しやすくなります。
一方で、3月は人事異動が重なって業務負担が大きいというデメリットもあるため、9月を決算月にする企業もあります。
また、海外では12月を決算月にしているケースが多いことから、グローバルに事業を展開している企業では、12月を決算月に設定しているケースも増えています。
決算月の3ヵ月前にできる決算対策

決算月まで3ヵ月では、年間を通して行なうような決算対策はできません。しかし、不要な固定資産の処分や未払金の処理、賞与の支給など、3ヵ月前からでもできる対策は複数あります。
ここでは、3ヵ月前からできる決算対策を6つ紹介します。
1.固定資産を処分する
不要な固定資産を処分して「固定資産除却損」を計上すれば、課税所得を減少できます。例えば、新しいパソコンを購入して古いパソコンをそのまま放置している場合、古いパソコンを処分することで固定資産除却損の計上が可能です。
また、机やパソコンなどの償却資産に課せられる償却資産税は、課税標準額の合計が150万円未満であれば課されません。不要な机やパソコンなどを処分すれば、課税されなくなるでしょう。
2.未払金の計上
未払費用があれば、それらの計上により費用が増えるため利益を圧縮できます。例えば、給与の費用計上を実際の支払い月にしている企業では、決算月に従業員が実際に働いた分を未払給与として計上可能です。
給与と同様に社会保険料も計上できます。給与や社会保険料は金額が大きいため、節税に役立つでしょう。
この他にも、すでにサービスの提供を受けていたり、請求書が来ていたりするものは未払費用として計上できます。ただし、これらを未払費用として計上した場合は、翌期に再び経費計上しないように注意してください。
3.賞与の支給
未払金の計上と同様に、賞与の支給も未払賞与として処理すれば、まとまった金額を費用として処理できるため決算対策になります。ただし、支給が決算日後になる場合は以下の対応が必要です。
- 決算賞与を支給する全従業員に、決算日前までに支給額を個別に通知する
- 通知した日が属する事業年度終了日の翌日から、1ヵ月以内に賞与を支給する
- 通知をした日の属する事業年度に損金処理をする
また、役員賞与は未払賞与にはできない点に注意しましょう。
4.備品の購入
翌期に使用する予定がある備品があれば、決算対策として購入を検討しましょう。なお、固定資産を中古で購入した場合は、耐用年数が短くなるため、1年あたりに計上できる減価償却費が相対的に大きくなります。
また、資本金が1億円以下の中小企業では、30万円未満の減価償却資産を購入する際に、耐用年数に関係なく全額を費用に計上できます。ただし、年間の合計取得額の上限が300万円であるなどの適用条件があるため、自社が該当するか事前に確認しておきましょう。
5.交際費課税の特例を活用する
資本金が1億円以下の中小企業であれば「交際費課税の特例」で、取引先との飲食費や接待費などを、年間800万円まで費用として計上可能です。
また、1人あたりの費用が1万円以下の場合は、交際費課税の特例の対象外となります。年間800万円の枠には含まれず、費用として別途計上できるため、より節税に繋がります。ただし、交際費課税の特例は2027年3月末までの適用となっている点に注意しましょう。
他にも、従業員と懇親会を開けば福利厚生費として計上可能です。決算期に合わせて、社内行事として新年会を開くなど、従業員とコミュニケーションを取る場を設けるのもよいでしょう。
ただし、懇親会は全社員を対象としなければならず、一部の部署だけを対象にした場合には福利厚生費として認められません。
6.短期前払費用の特例を活用する
支払いから1年以内にサービスの提供を受けるものは、短期前払費用の特例が適用され、支払った日が属する事業年度に一括で費用計上できます。例えば、オフィスの家賃や保険の支払いでこの特例を利用すれば、決算対策につながります。
ただし、特例を受けるには一定の条件を満たす必要があります。まず、費用を前払いとしている契約が必要です。契約では月払いの家賃になっているものを勝手に年払いにしても、特例は適用されません。
さらに、毎期継続して適用する必要があるため、「利益の多い年だけ特例を受ける」ということはできません。
また、特例を受けるためのサービスは、家賃や保険料のように等質・等量であることが求められます。
税理士や弁護士などへの顧問料は、毎月のサービスの内容が同一ではないため、特例には該当しません。紙の雑誌の定期購読(電子版は除く)のように、サービスではなく物を受け取る場合も対象外です。
手続きを踏めば決算月は変更可能

一度決めた決算月は変えられないと思っている方もいるかもしれませんが、決算月は事業年度が12ヵ月を超えない範囲で変更が可能です。
会社法では最初に決算月を変更した後の事業年度に限って、12ヵ月を超えた設定が可能です。しかし、法人税法では認められていないため、実質的に12ヵ月を超えた事業年度は設定できません。
また、決算月を変更するには、以下の手続きが必要になります。
- 変更した決算月に応じた決算処理や申告納税を行う
- 定款の変更や議事録を作成して、税務署・都道府県事務所・市区町村に届け出る他
決算月を変更すると、通常とは異なるサイクルで決算処理や申告納税が必要になります。例えば、決算月を12月から3月に変更する場合は、1~12月で一度決算処理を行ったあと、翌年1~3月でも処理が必要になり、業務負担が増す可能性があります。
定款への決算月や事業年度の記載は義務ではありませんが、一般的にはそれらが記載されているため、決算月変更の際には定款も変更したほうがよいでしょう。
定款の変更には株主総会での特別決議が必要ですが、小規模な会社では書面で済むケースもあります。
決算月の変更回数に制限はなく、理論上は何回でも変更が可能です。ただし、実際に変更するのは手間がかかる上に、変更前のデータとの比較が難しくなったり、税金の計算で調整が必要になったりするデメリットも存在します。
したがって、以下に紹介するようなケースで、メリットがデメリットを上回る場合には変更を検討するとよいでしょう。
会社の繁忙期と被っているとき
決算月は、通常業務以外に決算業務を行わなければなりません。特に経理担当者が少ない企業では負担も大きく、ミスが発生する可能性もあります。繁忙期がわかっている場合、決算月をずらせば業務負担を分散できます。
また、顧問税理士の繁忙期と被っている場合も、丁寧なサポートが受けられなくなる可能性があるため、決算月の変更が有効です。
資金繰りの状況が厳しい(支出が多い)とき
決算月の2ヵ月後には、法人税や消費税を納めなければなりません。賞与の支給や入金が少ないなどの理由で資金繰りが厳しい時期と、法人税などの支払い時期が重なっている場合に決算月を変更すれば、資金繰りが楽になる可能性があります。
また、期首(事業年度の開始日)から3ヵ月以内なら、原則として役員報酬の増減が可能です。経営状態に合わせて役員報酬を調整するとよいでしょう。
ただし、先に述べた通り、決算月を変更したときは、決算処理や申告納税を一定期間に分けて行う必要があります。
利益が多いとき
特定の月に利益が多いとわかっている場合、その前の月を決算月にすれば、特定の月の利益を次年度の利益として計上可能です。
結果的に節税に繋がる可能性があります。特に、利益が出たあとに損失が多く出そうなときは、利益が出る月を翌期にして利益と損失を相殺すれば、法人税を節税できます。
この他に、大規模な設備の導入などによって減価償却を増やすことでも、翌期の利益を抑えられるでしょう。
また、売上の多い月が期首になるようにすれば、1年間の利益を予想しやすくなり、節税対策が立てやすくなるメリットもあります。
決算のご相談は、TOMAコンサルタンツグループにお任せください
決算月とは事業年度の最後の月を指し、企業の経営成績や財政状態をまとめる月です。
決算3ヵ月前には、決算対策を考えておく必要があります。固定資産の処分や未払金の計上などによって、節税できる可能性があるからです。また、急に利益が増えたときは、決算月自体の変更による対策も検討するとよいでしょう。
TOMAコンサルタンツグループには、上場企業から起業して間もない会社まで1,200件を超える企業の顧問実績があり、貴社の状況に合わせて最適なアドバイスが可能です。決算対策に悩んでいる場合には、ぜひ一度TOMAコンサルタンツグループにご相談ください。