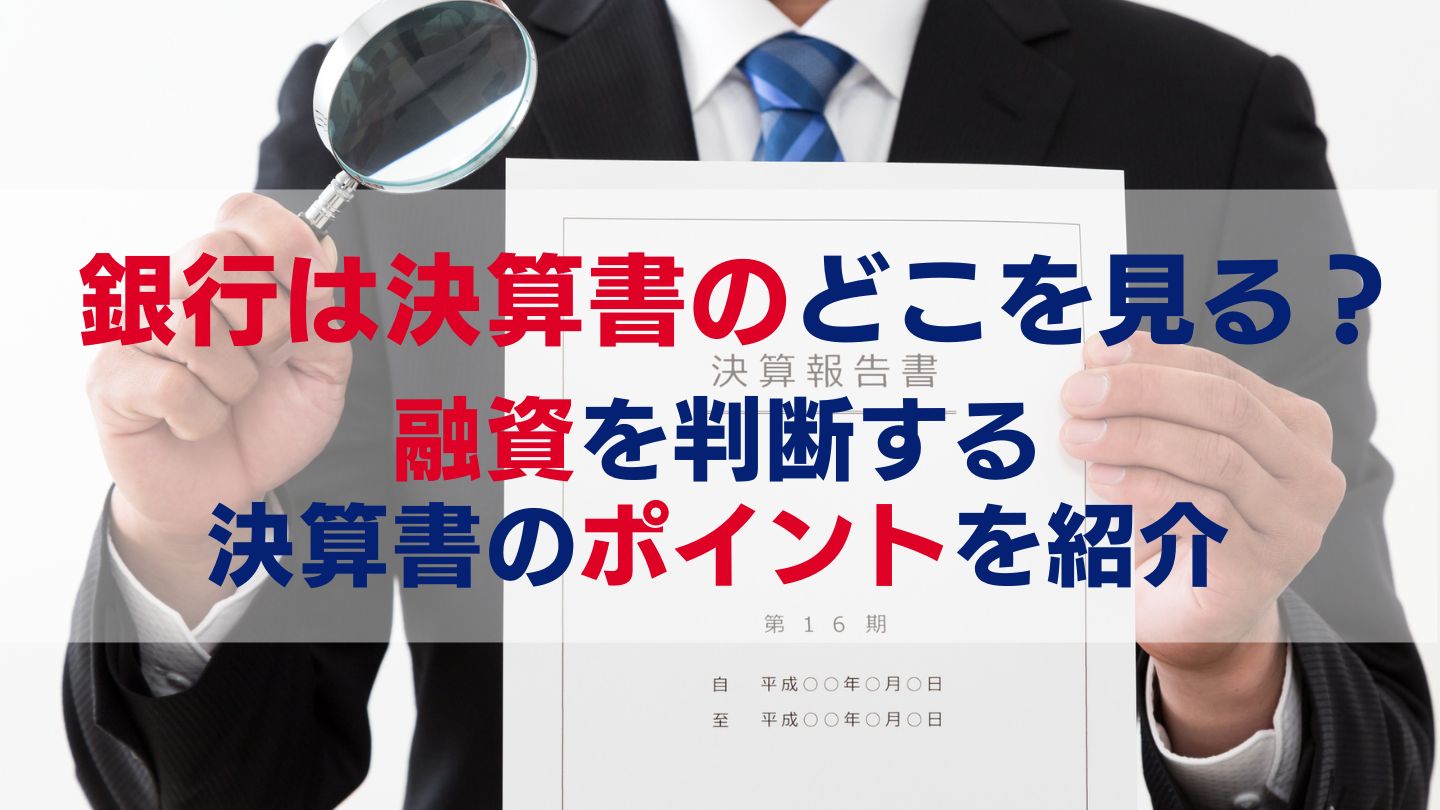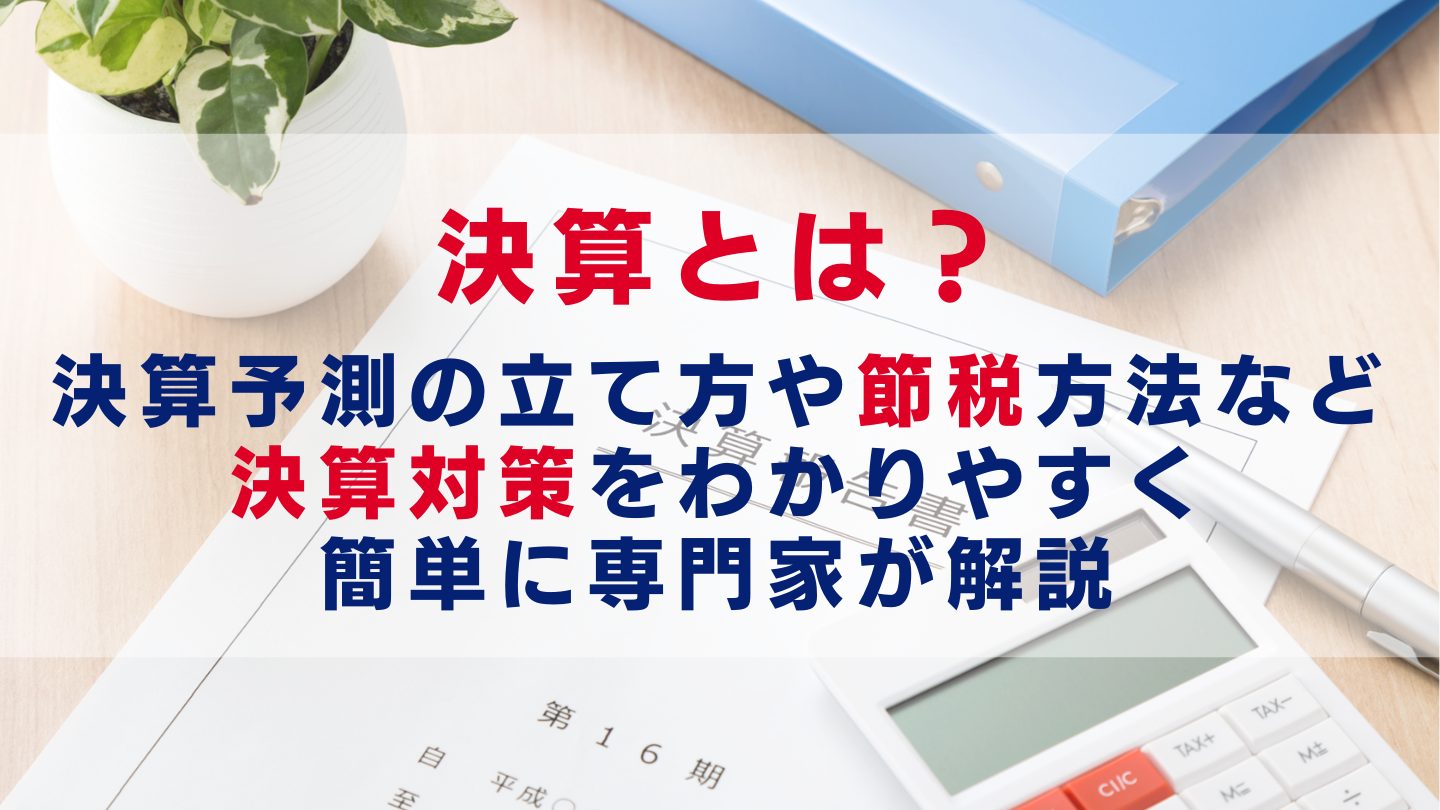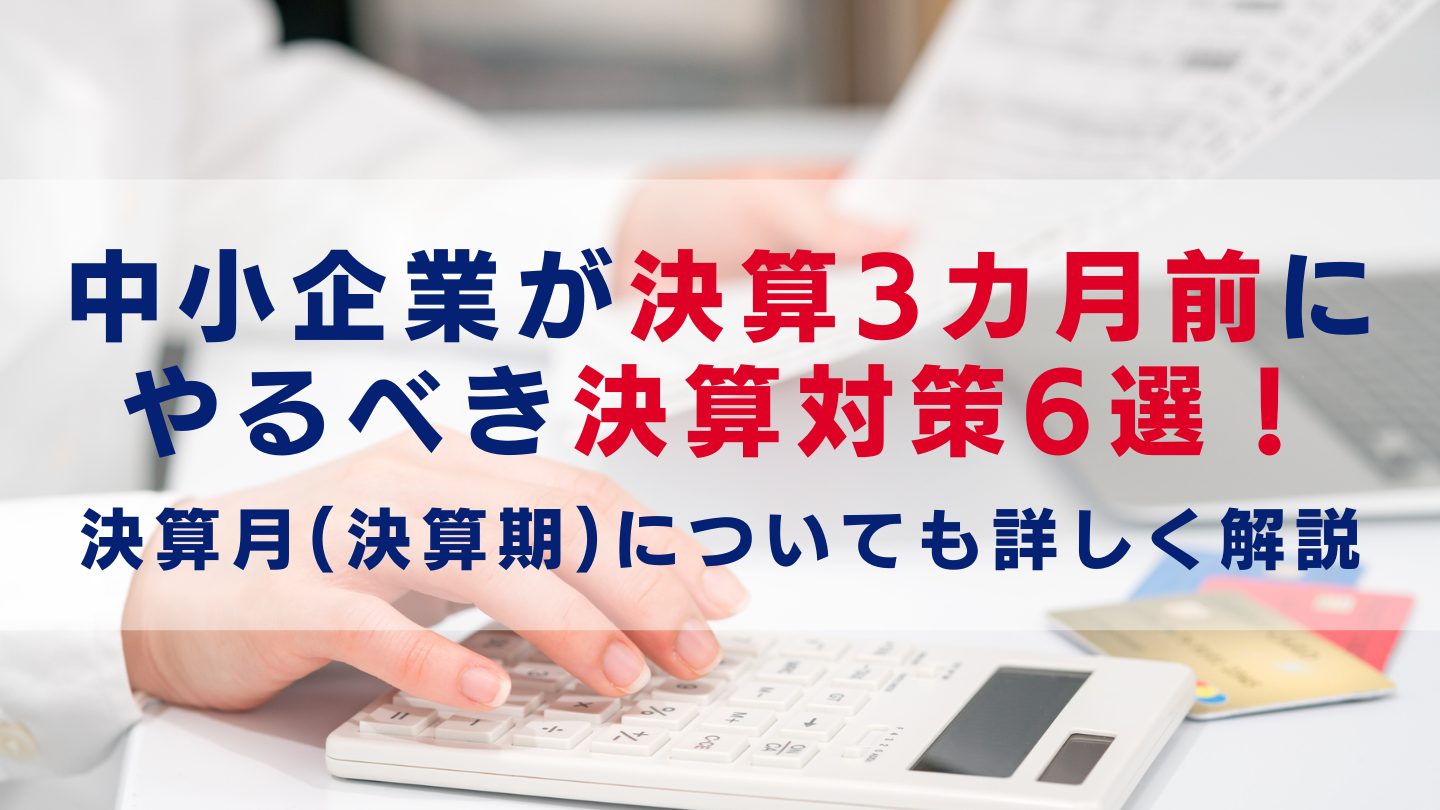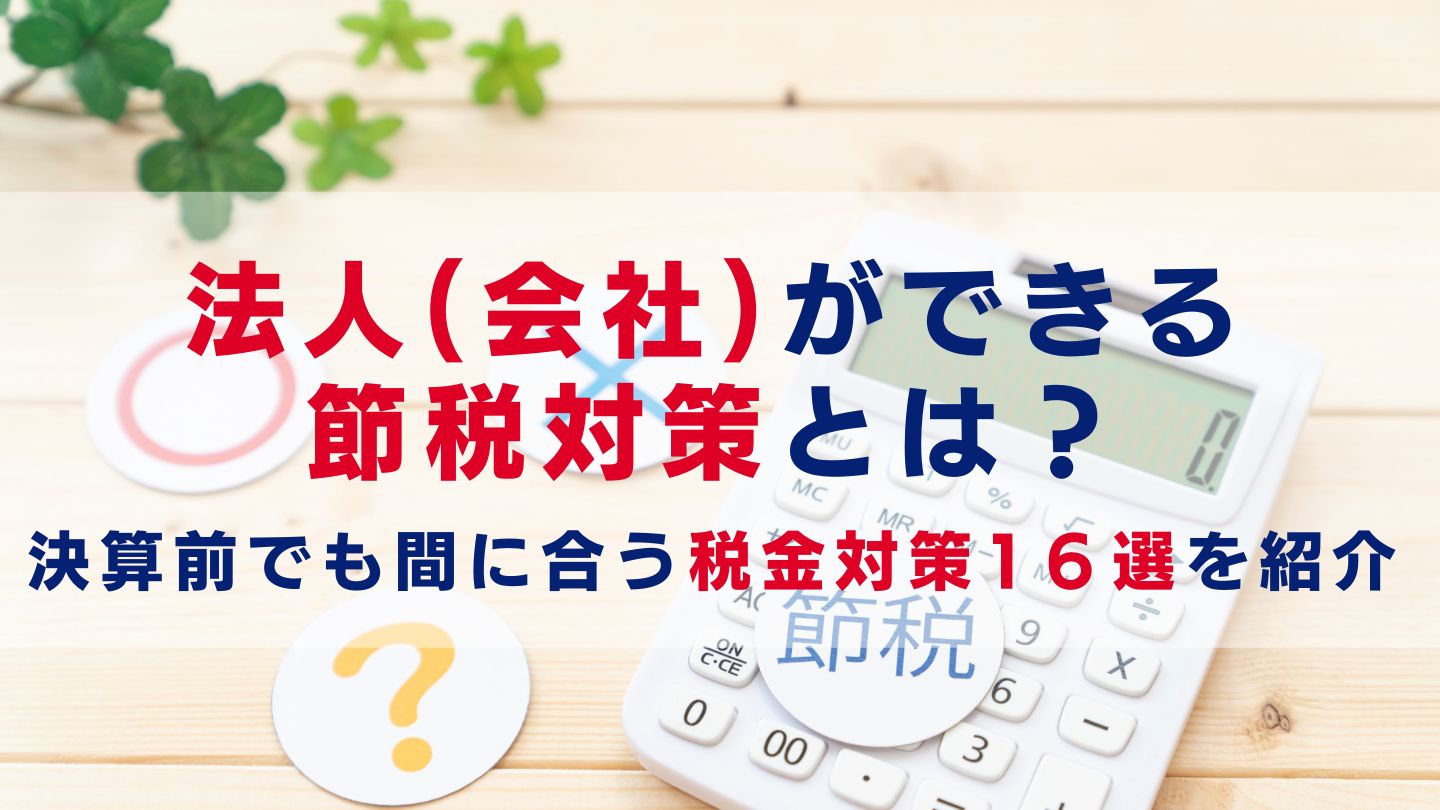銀行による融資審査を受ける場合、事前にいくつかの書類の提出が必要です。そのなかでも「決算書」は、最も重要な資料の一つです。
銀行は決算書のどこを見て融資の判断をしているのか、知りたい方も多いのではないでしょうか。
この記事では、決算書の基礎知識を踏まえ、銀行が融資審査の際に重視する決算書のポイントや、提出が必要な決算書類一式について解説します。
目次
決算書とは
決算書とは、企業の経営成績や財政状態について、事業年度ごとにまとめた書類のことです。原則として、事業年度終了日の翌日から2ヵ月以内に作成し、税務署に提出する必要があります。
決算書は、主に以下の5つに分類されます。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- キャッシュ・フロー計算書
- 株主資本等変動計算書
- 個別注記表
上記の書類のうち、貸借対照表・損益計算書・キャッシュ・フロー計算書は「財務三表」と呼ばれており、特に重要性が高い書類です。
銀行から決算書を求められたら?
銀行に融資を依頼すると、決算書の提出を必ず求められます。
銀行は、融資による資金の未回収リスクを避けるため、事前に企業の返済能力を見極めなければなりません。つまり、経営状況を客観的に把握する手段として、決算書の提出を求めます。
また、決算書は一般的に過去3期分の提出を求められます。これは、勘定科目ごとの金額の増減を比較し、直近1期分のみよりも質の高い財務分析を行うためです。
銀行は決算書のどこを見る?

融資審査を通過するためには、銀行が決算書のどこを見て、どのように判断するのかを把握しておくことが大切です。
ここからは、貸借対照表・損益計算書・キャッシュ・フロー計算書のそれぞれで、銀行が重視するポイントを解説します。
貸借対照表
貸借対照表(BS)とは、会社の一定時点における財政状態(資産・負債・純資産の状態)を示す決算書を、一覧にまとめた表のことです。銀行はこの貸借対照表をもとに、融資先企業の財政状態をチェックします。主に重視されるポイントは、次の5つです。
1.自己資本の充実度
業種によって異なりますが、総資本に対する自己資本の割合を示す自己資本比率が高いほど、「借入金に頼らず、安定した財務基盤を築いている」と判断され、融資審査に通りやすい傾向があります。
一般的には、自己資本比率が40%程度あれば、景気変動や不況が起きても、急激に財政状態が悪化するリスクは低いとされています。
ただし、自己資本比率が極端に高いと「借り入れを避けており、成長投資に消極的な企業」と判断され、審査に不利になる可能性があるため注意が必要です。
2.現預金の状況
現預金を安定して維持できている企業は「突発的な支出にも対応できる」と評価され、融資審査で有利になる可能性があります。
一方、現預金の増減が激しかったり、減少が続いたりしている場合は、資金繰りに問題があると判断され、返済能力に不安を持たれかねません。
また、現預金の金額が多すぎると「資金を有効活用していない」と見なされるケースもあるので、必要に応じて資金使途を説明できるように準備しておきましょう。
3.売掛金の回収状況
一般的に、売掛金の支払期限までの期間(回収サイト)が短いほど、資金繰りが安定していると見なされます。
一方で、未回収金額が多い、または回収サイトが長い場合は、融資審査に悪影響をおよぼす可能性があります。普段から「売掛金はできるだけ早く回収する」「売掛金が増えている場合は銀行に増加理由を説明できるようにする」の2点を意識しましょう。
4.売上に対する在庫の状況
売上に対して過剰に在庫が残っている場合、融資審査での評価が下がりやすくなります。過剰在庫は「在庫の回転率が低い」「棚卸資産を売上に転換できていない(資金繰りが厳しい)」と判断される可能性が高いためです。
過剰在庫の原因は「製造リードタイムが長い」「工程管理ができていない」「仕入れ量が不適切」など、さまざまです。融資審査に通過するためには、在庫状況を多角的に見直しておく必要があります。
5.固定資産の内容
融資審査では、土地や建物、株式といった固定資産の保有状況も影響します。固定資産は、大きく以下の3つに分かれています。
- 有形固定資産:土地、建物、建物付属設備、車両など
- 無形固定資産:知的財産権、営業権、ソフトウェアなど
- 投資その他の資産:株式、長期貸付金、差入保証金、保険積立金 など
固定資産には減価償却が適用されます。減価償却の計上は法人税法上任意ですが、正しく計上されていないと財務状況を正確に把握できません。そのため、融資審査では減価償却の計上状況も重視されます。
損益計算書
損益計算書(PL)とは、企業の一定期間における経営成績を明示した書類のことです。この書類により、期間内の利益や損失の状況が明確になります。
銀行が損益計算書で確認する主なポイントは、以下の3点です。
1.売上高
売上高とは、商品・サービスの販売によって企業が得た収入の合計のことです。売上高が大きいほど、事業規模が大きい、あるいは販売力が高いと評価されます。
融資審査では、過去3~5年分の売上高の推移を確認します。直近の売上高が過去数年分と比較して大幅に減少している場合は、その理由と改善施策の提示が必要です。
2.利益
損益計算書における利益には、以下の5項目があります。
- 売上総利益(粗利益):売上高-売上原価
- 営業利益:売上総利益-販売管理費(人件費や消耗品費など)
- 経常利益:営業利益+営業外収益-営業外費用(支払利息や貸倒損失など)
- 税引前当期利益:経常利益+特別利益-特別損失
- 当期純利益:税引前当期利益-税金(法人税や住民税など)±法人税等調整額
上記のうち、銀行が重視するのは「営業利益」と「経常利益」です。この2つがマイナスの場合、企業の収益性に対する懸念が強まり、融資審査での評価が低くなる可能性があります。
3.販売費及び一般管理費
販売費及び一般管理費とは、事業規模や売上の有無にかかわらず、企業の運営に伴って発生することが多い費用のことです。主に以下のような費用が該当します。
- 役員報酬
- 給与・賞与
- 福利厚生費
- 消耗品費
- 通信費
- 交通費
- 地代家賃
- リース料金 など
融資審査の際は、販売費及び一般管理費に対して、それ以上の利益を上げているかが重視されます。
キャッシュ・フロー計算書
キャッシュ・フロー計算書とは、一定期間内における資金の増減を示す書類のことです。
損益計算書で利益が出ている場合でも、手元資金が不足していては黒字倒産するおそれがあります。そのため、融資審査ではキャッシュ・フロー計算書をもとに企業の現金の流れを分析し、返済力があるかどうかを慎重に判断します。
キャッシュ・フロー計算書において、融資審査時に銀行が確認する主なポイントは以下の3点です。
1.営業キャッシュ・フロー
営業キャッシュ・フローは、以下のような営業活動を通じて発生した現金の流れを示します。
- 商品・サービスの販売
- 商品や原材料の仕入れ
- 人件費の支払い
- 賃料の支払い
- 利息の受け取り・支払い など
営業キャッシュ・フローがプラスであれば、「本業の現金収入で仕入れや経費などを支払えている」と見なされます。一方マイナスの場合、銀行は企業が黒字倒産の可能性があるのか、それとも成長過程の一時的な状況なのかを、原因分析して見極めます。
2.投資キャッシュ・フロー
投資キャッシュ・フローとは、企業の投資活動にともなう現金の流れを示します。具体的には、次のような取引が含まれます。
- 固定資産の購入・売却
- 有価証券や投資有価証券の取得・売却
- 定期預金の預け入れ・払い戻し
- 貸付の実行・回収 など
銀行は投資キャッシュ・フローをもとに、企業が設備や株式など、将来的な成長に向けた投資をどのように実行しているかを確認します。
一般的に、成長段階にある企業では設備投資などがかさみ、投資キャッシュ・フローがマイナスになりがちです。しかし、投資キャッシュ・フローがマイナスであっても、将来性を考慮され、融資審査に支障をきたさない場合があります。
3.財務キャッシュ・フロー
財務キャッシュ・フローは、以下のような財務活動に関係する現金の流れを示します。
- 金融機関からの借り入れ・返済
- 自己株式の取得・売却
- 株式や社債の発行
- 配当金の支払い など
銀行は財務キャッシュ・フローから、資金調達や株式に関連した現金の動きを把握します。
財務キャッシュ・フローは、プラスの状態であることが望ましいとは限りません。新規事業の立ち上げ時と資金繰りが厳しくなった際では、資金調達の性質が異なり、銀行の判断も変わるためです。
銀行へ融資申請する際に必要な決算書類一式

一般的に銀行から融資を受ける場合は、確定申告の際に税務署へ提出する以下の決算書類一式の提出が求められます。
- 決算書
- 勘定科目内訳明細書
- 法人事業概況説明書
- 法人税申告書(別表を含む)
- 消費税申告書
- 地方税申告書
- 税務代理権限証書
ここからは、決算書類一式についてそれぞれ解説します。
勘定科目内訳明細書
勘定科目内訳明細書は、貸借対照表や損益計算書における勘定科目の内訳をまとめた書類であり、確定申告の際に提出を義務付けられています。
取引先や取引内容が決算書よりも詳しく記載されており、銀行は勘定科目内訳明細書を確認することで企業の信頼性を判断します。
法人事業概況説明書
法人事業概況説明書とは、企業の実態や状況に関する以下の情報をまとめた書類のことです。
- 法人名
- 事業内容
- 支店・子会社の状況
- 海外取引状況
- 期末従業員等の状況
- PCの利用状況
- 販売形態
- 株主又は株式所有異動の有無(うち株式交付)
- 経理の状況
- 役員又は役員報酬額の異動の有無
- 主要科目
- 代表者に対する報酬等の金額
- 事業形態
- 主な設備等の状況
- 帳簿類の備付状況
- 税理士の関与状況
- 加入組合等の状況
- 月別の売上高等の状況
- 当期の営業成績の概要
- 年末調整関係書類の 電子化の状況
法人税申告書・消費税申告書・地方税申告書
法人税申告書・消費税申告書・地方税申告書は、企業が税務署に対して税金の申告を行なうために提出する書類です。
- 法人税申告書
申告書のほかに別表が1から20まである。別表1が確定申告書、それ以外は明細書に該当する。融資審査の際は、これら別表の提出も必要。 - 消費税申告書
「一般用」と「簡易課税用」の2種類の申告書があり、課税事業者のみ確定申告の際にいずれかを提出する。 - 地方税申告書
法人事業税・法人住民税・特別法人事業税の確定申告に必要。事業所の所在地である都道府県・市町村へ提出する。
銀行はこれらの申告書から、税金の納付状況や遅延の有無などを把握します。
税務代理権限証書
税務代理権限証書とは、税理士が納税者である企業などに代わり、税務手続きを行なう権限を持つことを証明する書類です。
税理士が確定申告を代行している企業は、委任の事実を証明するために、銀行から税務代理権限証書の提出を求められることがあります。
決算に関するお悩みは、TOMAコンサルタンツグループにご相談ください
銀行に融資を依頼する際は、自社の経営状況を示すために決算書の提出が求められます。
決算書は、返済能力や信頼性、業績悪化や倒産のリスクの有無を評価する重要な材料となります。銀行が融資審査時に重視するポイントを押さえて、対策を講じましょう。
決算書は融資審査だけでなく、確定申告の際にも不可欠な書類です。正確に作成するために、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
TOMAコンサルタンツグループでは、顧問先1,200件超の実績を誇るサービス「税務顧問契約」を提供しています。決算支援はもちろん、月次監査や経営・会計アドバイスなども行なっているため、ぜひ一度お問い合わせください。