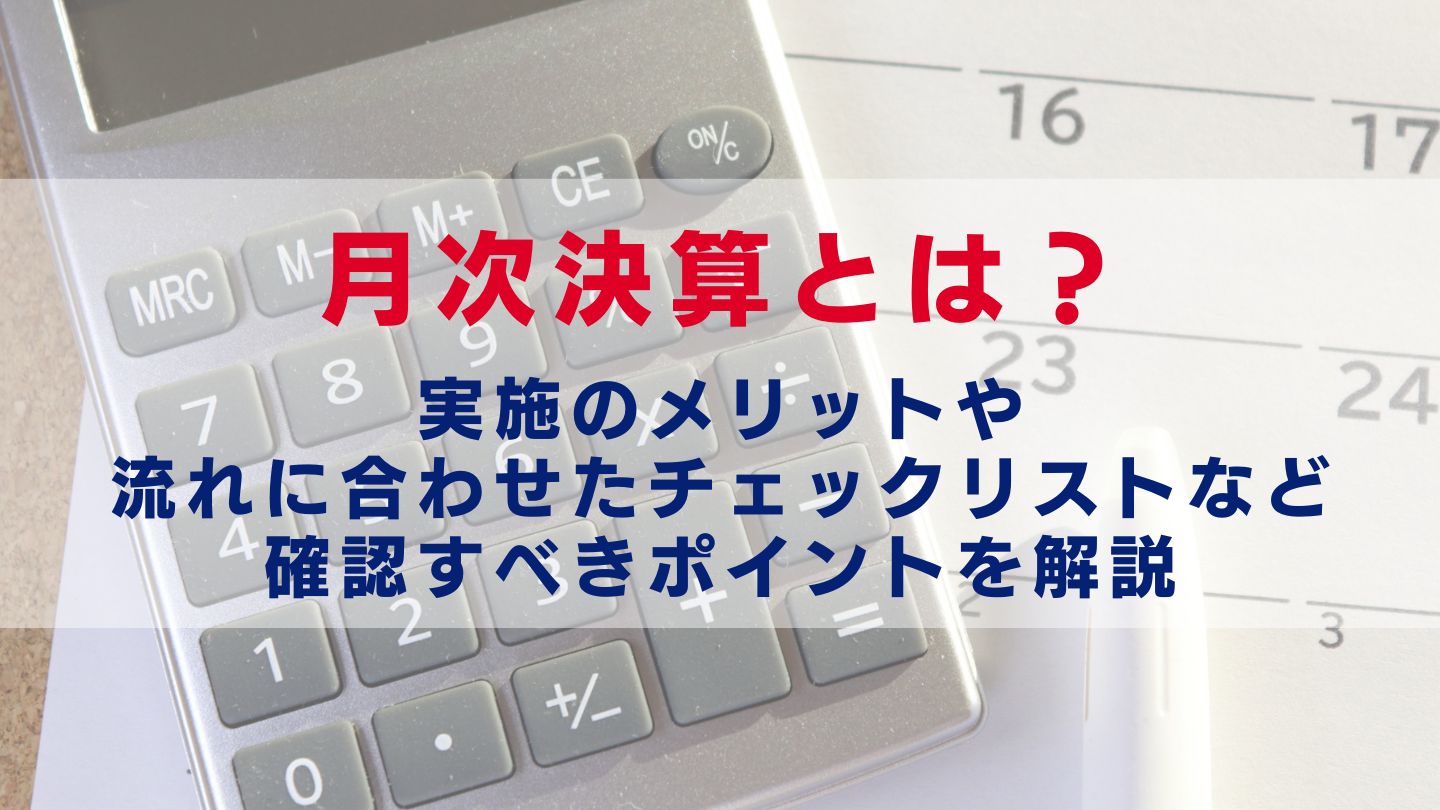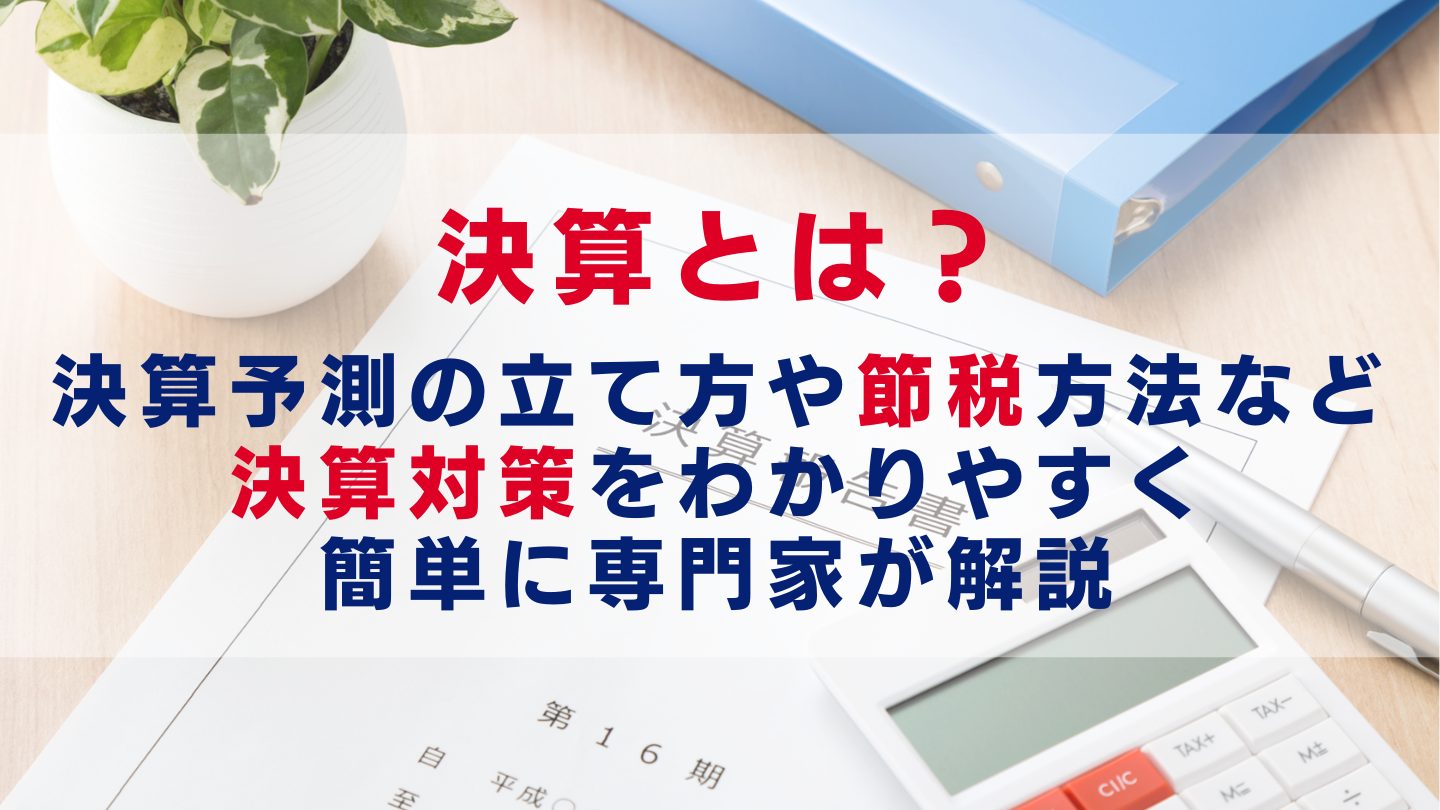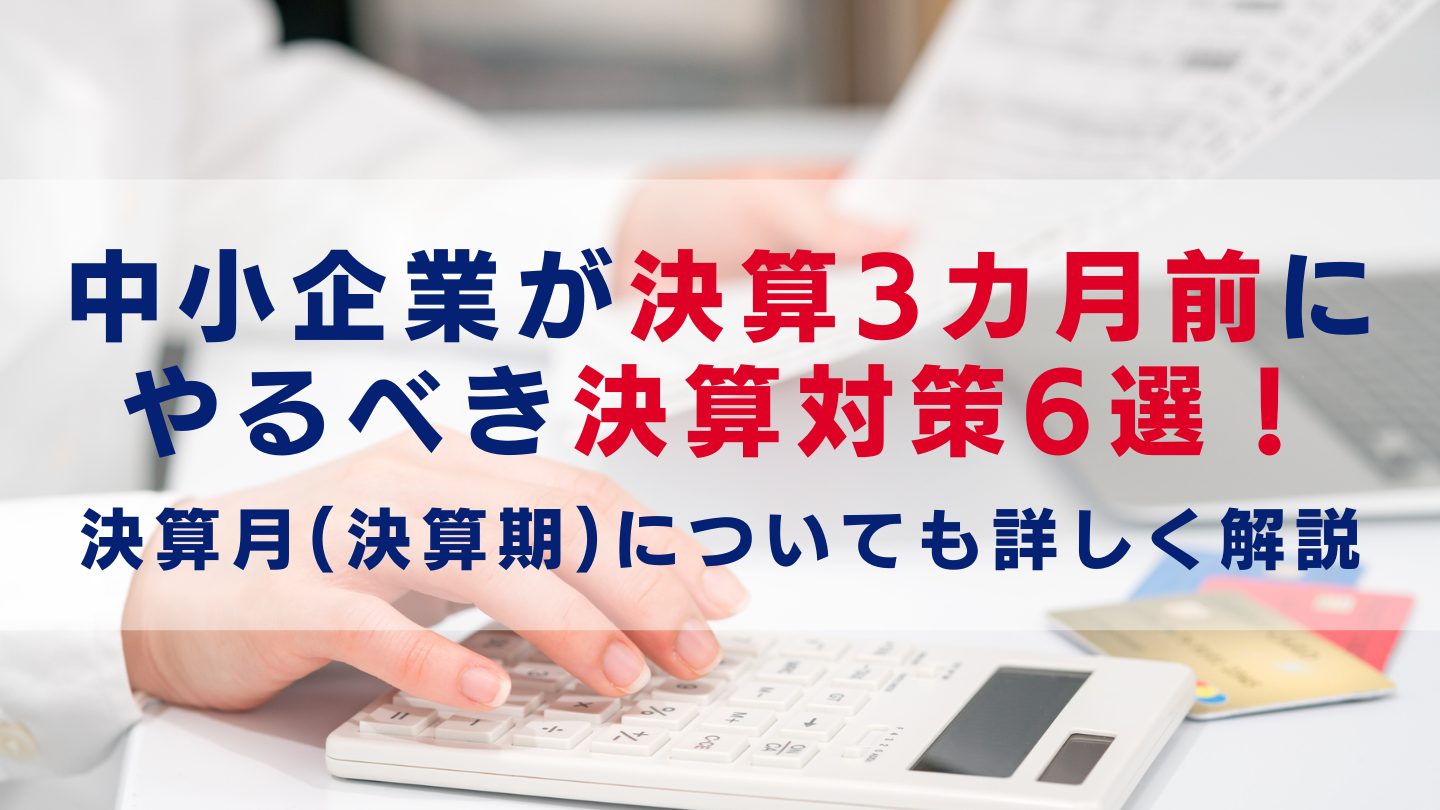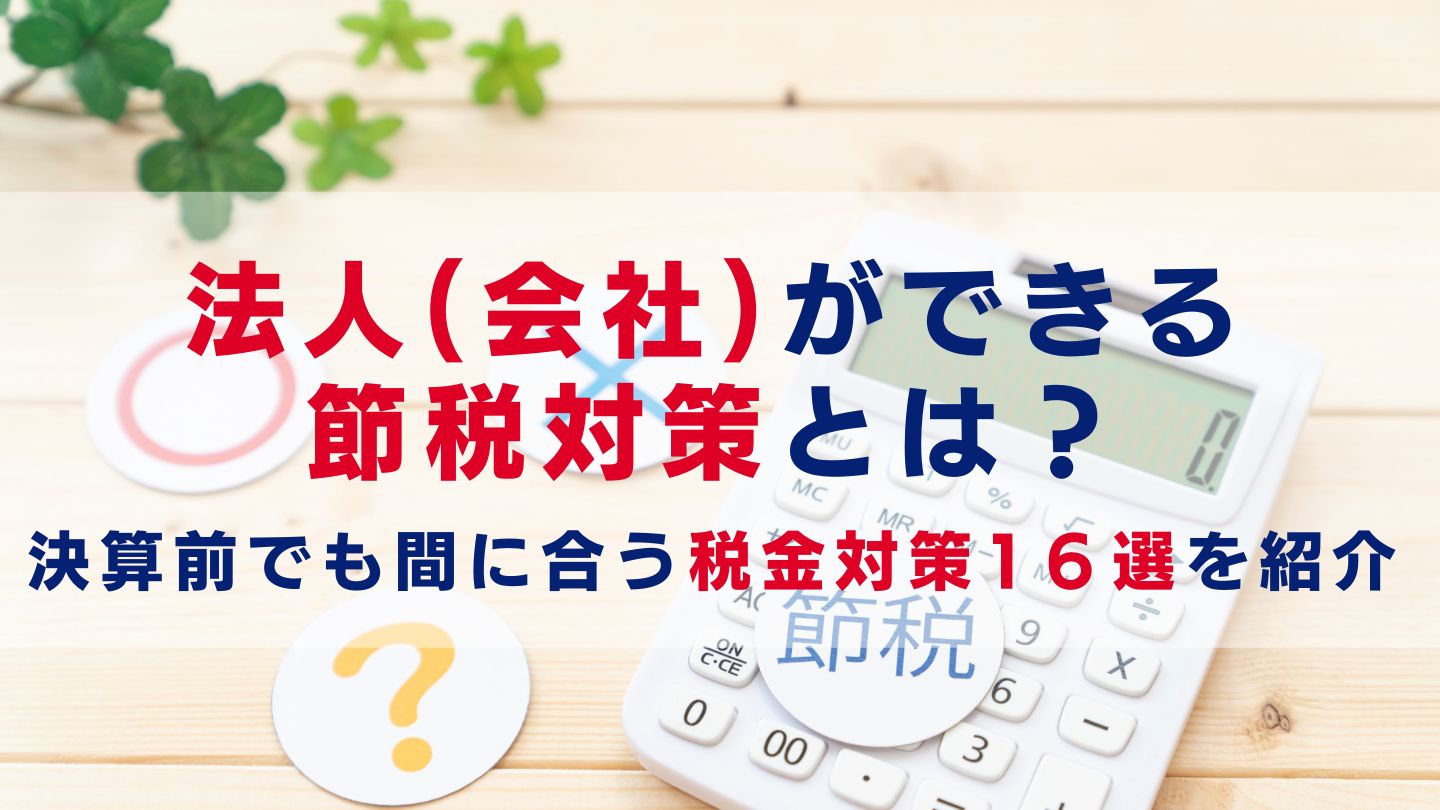企業の経理担当者や経営層の方のなかには、月次決算について気になる方もいるでしょう。月次決算を導入することで、経営状態をタイムリーに把握でき、早期の経営判断を可能にすることができます。また、年次決算時の負担が軽減するといった利点もあります。
本ブログでは、月次決算の概要やメリット・デメリット、作業の流れを紹介します。また、作業ごとに確認すべき項目をチェックリストとしてまとめているので、参考にしてください。
目次
月次決算とは?
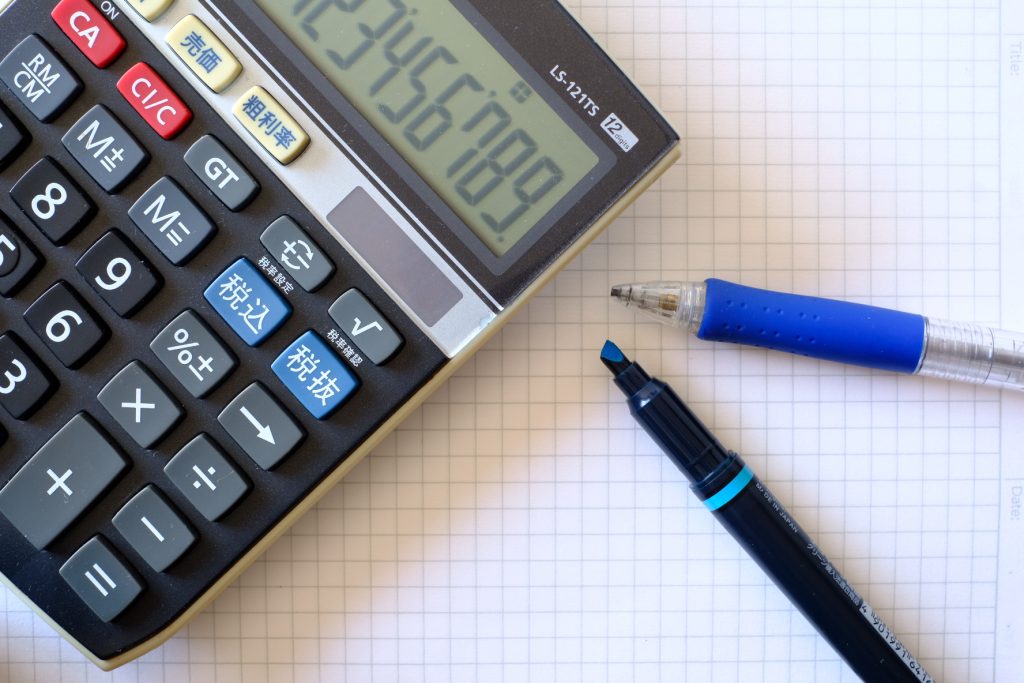
月次決算(げつじけっさん)とは、決算処理を年1回ではなく毎月行うことです。
決算処理を年1回行う年次決算は、法律によって決算処理の実施と株主総会での報告が義務付けられている特徴があります。
対して月次決算は、財務状況をタイムリーに把握するため、企業が任意で取り組むのが特徴です。
月次決算を行うメリット・デメリット
月次決算の実施により、1か月ごとに明確な業績を把握できるため、利益や損失の予測がしやすくなります。短期間ごとに業績を把握できれば、その状況に適した事業戦略や対策を立てられるでしょう。さらに、取引先からの債権の回収遅れや検収遅れなどを発見しやすいこともメリットです。
また、月次決算を行うことで年次決算時の負担が軽減されます。1年間分の情報を正確に把握するには時間がかかりますが、月次決算で処理しておけば、年次決算時にその情報をまとめるだけで済みます。
一方で、計上作業を毎月実施する必要があるため、業務の負担が増加する点はデメリットです。会社によっては、月次決算処理専用の人員配置が必要になるケースもあります。
月次決算の流れ

月次決算は、スムーズなスケジュール管理が重要です。ここでは、月次決算の流れを12ステップで解説しつつ、確認するべきポイントをチェックリストとして紹介します。
1.スケジュール確認・共有
社内でスケジュールが共有できていないと、決算処理がスムーズに進みません。そのため、各部署に月次決算全体のスケジュールや請求書・伝票の提出期限などを共有する必要があります。
また、締め切りや納品の期日を厳守してもらうよう、取引先に協力を依頼することも大切です。
チェックリスト
□イレギュラーな事態が発生した場合の対応策や連絡体制は確立されているか?
□前月の月次決算スケジュールからの遅延はないか?
□書類の提出期限を明確に設定しているか?
□関係部署にスケジュールを徹底して周知したか?
2.現金・預金残高の確認
銀行口座の通帳や残高証明書をもとに、預金が帳簿残高と一致しているかを確認します。併せて、現金の残高と現金出納帳の残高が一致しているかも確かめましょう。不一致であれば、原因を特定して修正を行う必要があります。
チェックリスト
□すべての銀行口座で残高証明書の発行または通帳記帳を行ったか?
□帳簿残高と銀行残高が一致しているか?
□現金残高と帳簿残高が一致しているか?
□差異が生じていた場合は原因を究明し、適切な訂正仕訳を行ったか?
□未渡小切手の仕分けは適切に行ったか?
3.売上金・売掛金の計上
請求書や売上データを確認して、当月の売上をすべて計上します。
チェックリスト
□当月の請求書はすべて発行されているか?
□売上の計上基準(原則、発生主義)が適用されているか?
□返品や値引きなどの処理は適切か?
□未請求・未回収の売上はないか?
4.経費の計上
経費精算書に基づいて、すべての経費を計上します。経費の計上基準は、売上の計上基準と統一するのが基本です。
チェックリスト
□すべての経費精算書を従業員から回収したか?
□未精算の経費はないか?
□経費精算の内容を証憑書類と照合したか?
□経費計上基準は発生主義が適用されているか?
□交際費、会議費、旅費交通費など、勘定項目の分類は適切か?
5.棚卸資産の確認
棚卸しを行い、実在個数と帳簿在庫が一致しているかを確認します。実地棚卸を行う際は、棚卸しの対象範囲や担当者、タイムスケジュールなどをまとめた「実地棚卸計画書」を作成しておくと、ミスを防ぎつつ効率的に作業できます。
実地棚卸が難しい場合は、在庫の受払表に基づいて帳簿棚卸を行うことも可能です。
チェックリスト
□実地棚卸を行う場合、棚卸計画を事前に作成しているか?
□帳簿棚卸を行う場合、在庫の受払表は整備されているか?
□棚卸差異が生じていた場合、原因を究明し、適切な修正処理を行ったか?
6.仮払金や仮受金などの整理
仮払金や仮受金などの仮勘定は、取引内容や金額が未確定の場合に、一時的に使用される勘定科目です。内容が確定したら、適切な科目に振り替えなければなりません。そのため、振り替え忘れや精算漏れがないように、整理と確認が重要になります。
また、仮払金や仮受金が増加傾向にある場合、金融機関から融資を受ける際に懸念されることがあるため、早急に原因を特定する必要があります。
チェックリスト
□仮払金、仮受金の残高は減少傾向にあるか?
□内容が確定した仮払金や仮受金を適切な科目へ振り替えたか?
□未清算の仮払金はないか?
□長期間残っている仮勘定がないか?
7.経過勘定の計上
収支が発生した時期と計上する時期が異なるものは、未払費用や前払費用等として経過勘定に計上します。
チェックリスト
□翌月以降に計上すべき収益が当月に計上されていないか?
□翌月以降に計上すべき費用が当月に計上されていないか?
8.引当金の処理
貸倒れや賞与などの支払いに備える引当金は、年間費用を算出し、月次費用として年間計上額の12分の1を計上します。
チェックリスト
□引当金の年間計上額の設定は妥当か?
□支給対象者が変化した場合は計上額の見直しをしたか?
9.減価償却費を計上
減価償却費も引当金と同様に、年間費用の12分の1を計上します。
チェックリスト
□すべての固定資産に対して減価償却費が計上されているか?
□固定資産台帳と帳簿の突合を行ったか?
□減価償却方法、耐用年数は適切に設定されているか?
□除却や売却した固定資産に対する減価償却の計上は停止されているか?
10.通年でかかる費用の計上
年間契約の保険料、リース料、保守料、地代家賃など、通年で発生することが確定している費用は、年間総額を把握し、月次費用として12分の1を計上します。これにより、月ごとの損益をより正確に把握できます。
チェックリスト
□通年でかかる費用の洗い出しは十分か?
□各費用の年間契約額および月次計上額は正確に計算されているか?
□契約期間の開始・終了、契約金額の変更があった場合、計上額に適切に反映されているか?
□関連する契約書や請求書は適切に保管・管理され、計上内容と突合できるか?
11.月次試算表の作成
すべての計上が完了したら、月次試算表を作成します。月次試算表には「合計試算表」「残高試算表」「合計残高試算表」の3つがあります。
勘定科目の貸借それぞれの合計を記載するのが「合計試算表」、残高のみを記載するのが「残高試算表」、これらの表をまとめたものが「合計残高試算表」です。
チェックリスト
□勘定科目の振り分けや転記にミスはないか?
□貸方と借方、全体の残高が一致しているか?
□計上漏れがないか?
12.月次事業報告と分析
月次試算表を作成後は、売上高や利益、販売管理費などの主要項目を中心に、前月や前年同月、予算などのデータと比較します。また、比較結果をもとに、変動要因を明確にするための分析も必要です。
経営層は、その分析結果に基づいて経営課題を洗い出し、翌月以降の方針を判断します。
チェックリスト
□予算と実績に大幅な乖離はないか?
□商品の在庫量は適切か?
□キャッシュフローや資金繰りに問題はないか?
□売上債権は適切に回収されているか?
月次決算のことは、TOMAコンサルタンツグループにご相談ください
月次決算とは、通常は年に一度行う決算作業を毎月実施することを指します。毎月の数字を正確に把握することで、タイムリーな経営判断が可能となり、年次決算時の業務負担も大きく軽減されます。
しかし、月次決算は工程が多く、スムーズに進めるためには工夫が欠かせません。限られた時間の中で正確な試算表を作成するには、スケジュール管理と業務の効率化がカギとなります。
そこでおすすめなのが、税務顧問のサポートを活用すること。専門家のアドバイスを受けながら進めることで、ミスを防ぎながら精度の高い月次決算が実現できます。「数字に強い会社」への第一歩として、月次決算の導入を検討してみてはいかがでしょうか?
TOMAコンサルタンツグループでは、これまでに1,200社以上の企業と顧問契約を結んでおり、豊富な実績を誇ります。企業ごとに適したアドバイスを提供していますので、月次決算への変更を考えている場合はぜひ一度ご相談ください。