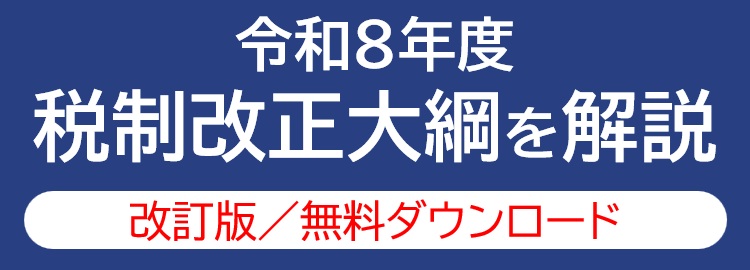横領は新聞やテレビなどにおいてたびたび取り上げられ、企業としてはとても大きなリスクと問題を抱えています。横領は、自社の役員や経理担当者などが架空経費を計上して横領する場合や、売掛金を着服して横領する場合などが考えられます。
今回は横領があった場合の法人の税務上の取扱いを説明したいと思います。
横領があった場合の税務上の取扱い
自社の役員や従業員の横領が発覚した場合には、法人にとって損失が発生しているため、横領が発覚した時点でその横領損失額は損金の額に算入されます。
そして、法人は横領が発覚し損害を受けた時点で、自社の役員や従業員に対して損害賠償請求をする権利が確定しているものと考えられるため、原則として、損失の計上時に損害賠償請求権を益金の額に算入することとなります。
例えば、自社の役員又は従業員が得意先の売掛金10,000千円を横領したことが発覚した場合には下記のような処理となります。
(借)横領損失 10,000千円 / (貸)売掛金 10,000千円
(借)未収入金 10,000千円 / (貸)損害賠償金収入 10,000千円
横領の発覚時に横領損失10,000千円と損害賠償金収入10,000千円の損失と収益の両建てとなります。そして、自社の従業員に対する債権を回収していくことになります。ただし、損害賠償金の回収が不可能となり、一定の要件を満たした場合には、貸倒損失として損金の額に算入できます。
法人において、自社の役員や従業員に対して資力があるにもかかわらず損害賠償金の回収を途中で免除した場合などには、上記の要件を満たさず、貸倒損失として損金の額に算入することが出来ません。
この場合には、給与として取り扱われ、その免除額に対応する源泉税の納税義務が課されます。この場合の給与の取扱いは役員と従業員で比較すると次のようになります。
・従業員の場合には、給与は損金の額に算入されます。
・役員の場合には、役員賞与として回収不能額の全額が損金不算入となり、所得金額が増加し税負担が増加します。
また既に解雇されている元役員又は元従業員に対して、損害賠償金の回収を途中で免除した場合には免除額の全額が寄付金として認定され限度額を超える部分については損金不算入となり、所得金額が増加し、税負担が増加します。
また、過年度に架空経費を計上していた場合には、修正申告で本税と共に延滞税、加算税等が課せられる場合があり、より大きな負担を負うこととなります。
まとめ
今回は横領を税務上の取扱いから説明しましたが、横領は会社にとって絶対に起こってはならないことです。会社としては、万が一に備えて、内部統制の強化などの不正防止の対策を講じる必要があるので、是非検討してみてはいかがでしょうか。