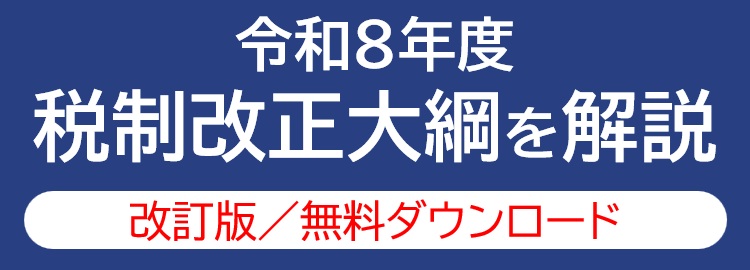22日の衆議院選挙を控え、希望の党の代表の小池百合子氏が公表した公約が今、話題を集めています。その公約は、消費税増税に反対する一方、企業の内部留保に課税するというものです。我々消費者に直結する消費税の増税を避け、企業に留保されているお金に目をつけたわけです。しかし、この内部留保課税は多くの批判を集めることとなってしまいました。その結果、日本経済新聞2017年10月13日の記事によると、小池氏は内部留保の活用について課税はこだわらないと明言しており、公約の事実上の修正をすることとなりました。
では、どうして批判を集めてしまったのか、内部留保課税とはどういったものなのかについて、今回はご説明していきたいと思います。
内部留保課税とは
会社の貸借対照表の純資産の部に「利益剰余金」といった勘定があります。これは、会社が設立してから現在まで稼得した利益のうち、配当等により外部に流失した金額を除いた内部に蓄積されている金額のことです。この利益剰余金がいわゆる内部留保金といわれるものになっています。
この利益剰余金が平成28年度末において、財務省の年別法人企業統計調査(金融業・保険業を除く全産業)によると約400兆円となっています。日本経済新聞2017年10月18日の記事によると、内部留保はここ5年間で4割増えていますが、設備投資については20年前と同水準にとどまっています。この会社が稼得した利益を賃上げや投資に使わずに、景気が悪化したときのために溜め込んでいるため、この内部留保に対して課税を行うことを内部留保課税といいます。
経営面からみた内部留保課税の問題
通常、会社はこの内部に留保されたお金で、新たな固定資産を買ったり、新規事業に投資したりし、会社を発展させていくことになります。そのため、もしこの内部留保に課税されてしまうと、会社を発展させる投資の原資が減り、会社は借入金に頼るほかなくなってしまい、会社の発展を妨げてしまう恐れがあります。経営面から見た場合にこのような問題が生ずる可能性があるため、内部留保に課税するのは慎重にならなければなりません。
税制面からみた内部留保課税の問題
経営の面からみた場合の内部留保課税の問題については、上述した通りですが、税制面からみた場合でも問題が生じます。この税制面からみた問題が、大きな問題であるため、批判を多く集める結果になってしまいました。
もう一度利益剰余金の意味をおさらいしますが、利益剰余金とは稼得した利益のうち外部流失を除いた内部に留保されている金額です。会社は稼得した利益に対して、税金を課され納税しなければなりません。つまり、利益剰余金とは税金を納付した後の利益が積み重なっている金額ということになります。財務諸表をよくみて頂くと、損益計算書の税引後利益が、貸借対照表の利益剰余金に加算されることがわかるかと思います。
もうお分かりの方もいらっしゃるかと思いますが、会社は利益に課税され、内部留保にも課税されると、一度課税されたものがもう一度課税されることになるため、二重課税の問題が発生することになります。これが税制面からみた問題点です。
二重課税を容認すると、担税力以上の課税など様々な問題が生ずることになるため、同一の取引(課税原因)には、1回の課税という租税の大原則があります。現在、国際間の二重課税など多くの二重課税を排除する税法の改正が行われています。そのような中この内部留保課税は二重課税を容認する形になることから、多くの批判を集めることとなってしまいました。
特定同族会社の留保金課税
内部留保課税は、二重課税等の問題が存在していることはお分かり頂けたと思いますが、現行税法において、内部留保に課税される制度があります。それが、「特定同族会社の留保金課税」です。
これは個人が会社を設立し、個人にお金を移すと課税されるため、会社にお金をプールして課税を逃れるといった租税回避を防止する規定です。内部留保に対して課税されるため、特定同族会社という通常の会社より狭い範囲に対して、一定の控除額を超えた部分について、特別な税率を課して課税するといった制度になっています。特定同族会社に該当する場合には、この留保金課税という負担が大きい税金が課される可能性がありますが、会社の規模を表す資本金の額などで対象を限定したり、一定の控除額を設けるなどしたり、慎重な課税がされています。
終わりに
今回、内部留保課税についてスポットを当ててみてきましたが、消費税増税にかわる代替案として留保金課税が行われることは、二重課税の問題等からなかなか難しいのではないかと思われます。税制が企業活動を阻害するようなものではなく、経済と共存していくものであることが好ましいと思います。