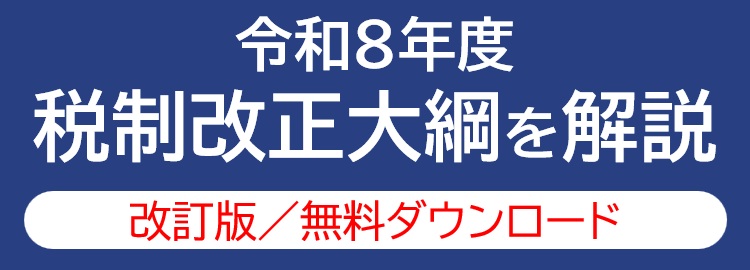事業承継を成功させるためには、現在保有している資産や負債の洗い出し、事業の方向性などを確認することも必要です。「親子だからわかるだろう」という過信や、明確な引き継ぎもなく「あとは頼む」と一言で済ませてはいけません。今回は、事業承継時における遺言書の作成についてご紹介します。
事業承継における遺言の役割とは
準備不足によって後継者や従業員が混乱しないためにも、事業承継の対策は早めにとることが大切です。遺言書を作成しておくことは、自社株や不動産といった資産を後継者に円滑に引き継ぐ役割があります。
遺族間における不要な争いを避けるためにも、遺言書を残しておく必要性は高いと言えるでしょう。
事業承継に最適な遺言法とは
遺言書の作成には3つのパターンがあります。
自筆証書遺言
遺言者が自書した上で押印して作成するのが「自筆証書遺言」です。こちらはいつでもどこでも書くことができますし、費用もかかりません。なお、自筆証書遺言の開封には検認が必要となります。
注意する点は、書き方を間違えてしまうと遺言としての効力を発揮できない点です。また、紛失のリスクもあります。相続に納得していない親族がいる場合、偽造される可能性もあるため、保管時にも注意が必要と言えるでしょう。
公正証書遺言
遺言者が公証人に内容を伝えて、遺言書の作成と保管をしてもらうのが「公正証書遺言」です。自筆証書遺言と違って公証人が作成するため、遺言の効力が発揮できないという事態を避けられるのがメリットです。また、公証役場に保管されるため、盗難や偽造の心配もありません。
秘密証書遺言
遺言者が作成した遺言書を封印して、公証人に保管してもらうのが「秘密証書遺言」です。公証役場に保管されるため、盗難や偽装の心配はいりません。
公正証書遺言と秘密証書遺言はそれぞれ費用がかかります。しかし、相続人が多いとトラブルの発生リスクも高まる可能性があります。秘密証書遺言は内容のチェックはしてもらえないため、公正証書遺言による遺言書作成が事業承継対策として有用であると言えるでしょう。
公式証書遺言を作成する時の注意点
せっかく遺言を残しても、その効力を発揮できなければ、遺言書はただの紙です。経営者が亡くなってから訂正はできないため、慎重に作成する必要があります。内容に不備がないか、人によって解釈が違わないか等に留意して作成するようにしましょう。
また、遺留分に配慮しなかったためにトラブルに発展するというケースもあります。配偶者や子といった一部の相続人には、最低限の遺産の取り分があります。これを遺留分と言い、法律で決められています。たとえ資産を引き継がせたくないという事情があっても、遺族の争いに発展しやすいため、遺留分に配慮した遺言の作成が必要であると言えるでしょう。
また、遺言書を作成した時と、実際の相続が発生した時とでは、状況が変わっている可能性がある点にも注意が必要です。後継者である息子が事業を引き継げなくなった場合は、その孫に引き継ぐという内容を記載することもできます。これを補充遺言と言い、遺言の再作成は不要です。資産の名義変更や登記の移転などの手続きをする遺言執行者も、遺言の中で指定しなければなりません。手続きが煩雑になることも多いため、弁護士などの第三者に依頼すると手続きがスムーズです。
遺言を残している場合と残していない場合の違いとは
遺言がない場合、相続人同士で遺産分割協議によって、話し合いで分け方を決めることになります。法定相続分にしたがって遺産を分割するとなれば、現経営者の夫が亡くなり、妻、息子、娘の3人で10億円を相続する場合、妻5億円、息子と娘が2億5,000万円ずつとなります。
生前経営者であった夫が、後継者である息子に自社株や不動産等の資産を集中させたいと考えていたとしても、遺言書がなければ実行されません。経営者が変わっても事業を発展させていくためには、遺言書を残しておくことが重要であると言えるでしょう。
遺言の作成を適切に行わないと、効力を発揮することなく後継者や相続人の争いの原因になってしまいます。相続する資産の評価算定や、会計・税務などの専門知識が必要になるため、専門家に相談しながら手続きを進めると良いでしょう。